★愛する地球と月を作製して見ました。
今日は天空に満月が輝いていますよ
皆様 たまには星空でも眺めましょうね。(=*^-^*=)にこっ♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★壁紙 宇宙館
様からの画像です。
★型紙はPlanetary Icosahedrons
様からです。
正20面体の型紙でした。作り易い型紙です、皆様もいかがですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★人類全てが素晴らしき地球家族、兄弟ですよね(=*^-^*=)にこっ♪
★リンク、書き込み、虎ーBackは ご自由に
お使いくだシャンハイ (=*^-^*=)にこっ♪
★素敵で壮大な宇宙にに清き一票を
宜しくお願い致します(=*^-^*=)にこっ♪
(笑い♪♪) (笑い♪♪)
★一般庶民が一番望んでいる事です。平和が一番ですね。(=*^-^*=)にこっ♪
私は日々健全な生活を送る事が出来れば良いです。
★上を見上げれば こんなに素敵な宇宙だね(=*^-^*=)にこっ♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*****出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
左中ほどの検索窓に太陽系と入力し表示をクリックてね。*****
★★地球(ちきゅう)は、
太陽系の内側から3番目に位置する惑星。地球は「地球型惑星」に分類されている。誕生してから約46億年経過しており、これは太陽系の年齢とほぼ等しい。
組成は中心からの距離によって異なる。地表付近では酸素とケイ素を主体とし、他に鉄・アルミニウム・ナトリウム・カルシウム・カリウム・マグネシウムなどの金属元素を含む岩石でできている。いっぽう、中心部分は鉄やニッケルが主体である。地球の表面の7割は豊富な水(海)で被われており、地表から約100kmまでの範囲には窒素・酸素を主成分とする厚い大気が層をなしている。
★生命
地球は2005年現在、知られている唯一の生命体の確認されている惑星である。生命は地表だけではなく、地下10km程度から上空100kmに至る広い範囲に存在する。大気の組成は植物によって維持されている。
地球生命圏 (ガイア)
生命、生物、動物、植物
人類の活動が与える惑星地球、特に生命圏への影響は大きく悲観的な意見も少なくない。
★地理学
総面積は5億1007万2000km2で、そのうち海が3億6113万2000km2(地球表面の70.8%)、陸地が1億4894万km2(29.2%)である。
陸地は地球表面全体に均等にではなく北半球に偏って分布しており、陸地の多い側を陸半球(りくはんきゅう)、海の多い側を水半球(すいはんきゅう)と呼ぶ。陸地はランダムに分布するのではなく、大陸という形でまとまって位置している。海洋も深度の分布にはっきりした偏りがあり、深度4000~5000mに全海洋の33%の面積を占める海洋底という構造がある
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★★月(つき)は
地球の周りを公転する唯一の自然の衛星。
(クルイシンは地球近傍天体であり、地球の衛星ではなく小惑星である。)
太陽系の中で地球に最も近い自然の天体であり、人類が到達したことのある唯一の地球外天体でもある(2004年現在)。地球から見える天体の中で太陽の次に明るいが、自ら発光はせず太陽光を反射し白銀色に光る。
英語では moon、ラテン語で Luna と呼ばれる。古くは太陽に対して太陰ともいった。漢字の「月」は三日月の形状から変化したもので、古代の日本語では「ツク」と読んだ。これは月そのものの姿と同時に「憑く」という意味を持っており、神や霊が宿る星として考えられてきた。運がいい、等の意味で使われる「ツキがある」なども同じ「ツク」を語源としている。
また、別の意味として、ある惑星から見てその周りをまわる衛星を指す。例:フォボスは火星の月である。
月は天球上をほぼ4週間ごとの軌道で移動する。天空の移動速度は毎時 0.5 °程度である。また、天球上の軌道である白道も一定しており、黄道帯とよばれる黄道周辺 8 度の範囲におさまる。さらに 2 週間ごとに黄道を横切る軌道を描く。地球上から月を観測すると、毎日形が変わって見え、約29.3日周期で同じ形に戻る。このため、原始的な暦法では、この周期を「月」という、天体名と同じ単位として扱った文明が多い。このような暦法を太陰暦という。詳細は、月を参照のこと。
★物理的特徴
直径は地球の約0.2724倍(1/3.7)。冥王星とカロンの組を除き、惑星と衛星の比率としては最も大きい。月の直径は、木星のガニメデ(5262km)、土星のタイタン(5150km)、木星のカリスト(4806km)、木星のイオ(3642km)に次ぎ、衛星としては太陽系で5番目に大きい。月と太陽の見た目の大きさ(視直径)はほぼ等しく、約30秒である。このため、他の惑星とは異なり、太陽が完全に月に重なる皆既日食や、金環日食が起こる。月の視直径は1m離した1円玉の大きさよりわずかに小さい。
月の形状はほぼ球形だが、わずかに西洋梨型をしている。質量はおよそ地球の0.0123倍(1/81)。地球中心から月の中心までの距離(平均)は、38万4403キロメートル。
月は、太陽系の惑星やほとんどの衛星と同じく、天の北極から見て反時計周りの方向に公転している。軌道は円に近い楕円形。軌道半径は38万4400kmで、地球の赤道半径の約60.27倍である。
月の自転周期は27.32日で地球の周りを回る公転周期とほぼ一致しており、完全に同期している。つまり地表からは月の裏側は永久に観測できない。これはそれほど珍しい現象ではなく、火星の2衛星、木星のガリレオ衛星であるイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト、土星の最大の衛星タイタンなどにもあてはまる現象である。ただし、一致してはいても月の自転軸が傾いていることと軌道離心率が0でないことから、月面の59%は地上から観測可能である。
月の重力は地球に影響を及ぼし、太陽とともに潮の満ち引きを起こしている(潮汐作用)。地球上の生物のホルモンリズムにも影響を及ぼしていると俗説では言われることもある(いわゆるバイオリズム)が、月によって人間に加わる重力は、蚊一匹分と非常に小さいものにしかならないため、科学者の中では否定的な意見のほうが圧倒的である。
月の潮汐作用により、主に海洋と海底との摩擦(海水同士、地殻同士の摩擦などもある)による熱損失から、地球の自転速度がおよそ10万年に1秒の割合で遅くなっている。また、重力による地殻の変形によって、地球-月系の角運動量は月に移動しており、これにより月と地球の距離は、年約3.8センチメートルずつ離れつつある。この角運動量の移動は、地球の自転周期と月の公転周期が一致したところで安定となるため、地球-月間の距離はそこで安定すると考えられている。約50億年後には地球と月は常に同じ面を向けることが予測されている。
月は大気を持たず、表面は真空である。そのため、気象現象が発生しない。このことは月面着陸以前の望遠鏡の観測からも推定されていた。また地質学的にも死んでおり、マントル対流が存在せず火山も確認されていない。そのため鉱石は存在しないと推定されている。地球のような液体の金属核は存在しないと考えられており、磁場も存在しない
★月の起源
月の石の放射性年代測定により、約45億5000万年前に誕生し35億年前までは微惑星の衝突が多発していたことが分かっている。
起源については、地球に捕獲された他の天体とする説や、地球と他の天体との衝突によって飛散した物質由来(ジャイアント・インパクト説)とする説などがある。最近の研究ではジャイアント・インパクト説が優勢。月の比重は3.34であり、地球の大陸地殻を構成する花崗岩(比重1.7~2.8)よりも大きく、海底地殻を構成する玄武岩(比重2.9~3.2)に近い。


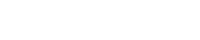

 人気blogランキング
人気blogランキング お慈悲をおかけください
お慈悲をおかけください