帰ってきたヨッパライ 後編
りんねーちゃんと雪男くんのお話。後編
帰ってきたヨッパライ その2
「おッ、おまッ、は、離せ! 離せ、尻尾!」
「やだ。離したら姉さん、どっか行っちゃうじゃないかあ!」
「どこも行きゃしねえよ! 風呂だ、風呂!」
「やだやだやだ! 姉さん、どこにも行かないで!!」
雪男は容赦なく燐の尻尾を引っ張った。
急所の尻尾をロープのように引っ張られたのでは、たまらない。燐は雪男の腕の中へもんどり打って倒れ込んだ。
「なにすんだ、雪男!」
「だって姉さん……姉さんが――」
酔っ払いの弟は、今度はぐすぐすべそをかき始める。
「だぁあ、泣くな! お前、いったい幾つだ!」
「姉さんと同い歳」
「んなこたぁわァってるよ! ヒトの尻尾でハナ拭くなー!」
「うええええん、姉さんが冷たいぃ!!」
とうとう雪男は、赤ん坊みたいに手放しで泣きじゃくり出した。それでも燐の尻尾は離さないが。
「姉さん、どうしてそんな意地悪ばっかりするんだよぅ……」
「はああっ!?」
ふざけるな。それはこっちのセリフだ。
お仕置きだの躾だのと言って、いつもいつも燐に酷い真似ばかりするのは、雪男のほうではないか。
「前は、ぼくがテストでいい点取ったら、ものすごーく誉めてくれたじゃないかあ……。運動会のかけっこで、転んでビリになったって、姉さん、手作りの金メダルをぼくの首にかけてくれて、“おれん中じゃ、いつでも雪男が一等賞だぞ”って……」
「いつの話をしてんだよ!」
「ほらあ。やっぱり冷たいぃー!」
でっかい図体をして、雪男はぐしぐしべそべそ泣きじゃくる。畳にぺったり座り込み、両手で目元をこすって。
その仕草は、遠い昔、いつも燐のあとを追いかけていた、泣き虫で甘ったれの弟そのものだった。
「姉さん。ぼくを置いていかないで……。置いてかないでよぅ……」
「雪男――」
燐はゆっくりと手を伸ばした。
ずれてしまった眼鏡を外し、涙に汚れた雪男の頬をそっと拭ってやる。幼かった日、いつもそうしてやったように。
「どこにも行かねえよ」
こつん、と、おでことおでこをくっつけて。
「どこにも行かない。姉ちゃんはここにいる」
「ほんと……?」
「ほんとだよ。ずーっと、雪男といっしょ」
どうして気づかなかったのだろう。
自分たちは双子の姉弟。どんなに大人びて見えたって、雪男は大事な可愛い弟なのだ。
亡き養父、偉大なる聖騎士・藤本獅郎から、燐の守護者の役目を引き継ぎ、その重すぎる責務をたったひとりで担おうとしている雪男。
いつの間にか燐よりずっと高くなった背丈、広い肩にばかり目を奪われて、つい忘れそうになってしまうけれど。
自分たちは同じ。ふたりぽっちでこの世界に放り出されてしまった子供たち。優しかった父を喪い、声をあげて泣くことすらできずにいる、淋しい、哀しい子供たちなのだ。
「姉さん。姉さん、お願い。ぼくを嫌いにならないで」
雪男はしゃにむに燐にしがみついてきた。まるで迷子の子供がようやく会えた母親にしがみつき、離れまいとするかのように。燐を抱きしめ、肩に額を押しつけて、嗚咽を漏らす。
「ばぁーか。ならねえよ」
燐は優しく、雪男の重みを受けとめた。
「ほんと……?」
「ほんと」
「ほんとに? ほんとに!?」
繰り返される同じ質問に、何度も何度もうなずいてやる。
「ごめんなさい。ごめんなさい、姉さん……。ほんとはぼくだって、姉さんに優しくしたいんだ。でも――でも、どうしても止まんないんだよ……!!」
身体を重ねるたび、雪男は酷く燐を責め苛む。燐はさんざん泣かされ、傷つけられ、気絶するまで苛められる。時にそれは度を超えた暴力に発展してしまうことすらある。
それでも。
――好きだ。好きだ。姉さん、大好きだ……!
熱に浮かされたように同じ言葉を繰り返す雪男を、どうしても拒めない。
「わかってる。ちゃんとわかってっから、心配すんな」
こうやって甘やかしてしまうことは、もしかしたら雪男のためにはならないのかもしれないけれど。
燐は、雪男を抱きしめる手にそっと力を込めた。
そうすると、雪男の体温をさらに近く、しっかりと感じ取ることができる。
――雪男。可愛い雪男。お前、そんなとこは本当になにも変わってないんだな。
お前はおれに、なにしたっていいんだ。
だっておれは、お前から何もかも奪ってしまった。家族も、未来も、夢も、何もかも。おれの弟なんかに生まれなければ、こんなつらい思いをしなくたって良かったのに。
それでもお前が、おれを――こんな魔神の娘を、愛していると言ってくれるなら。
燐を傷つけ、追いつめることでしか、燐の気持ちを確かめられないと雪男が言うのなら、どれほど傷つけられてもかまわない。
雪男に問われるなら、何回でも答える。何回でも、何百回でも、同じ答を。
……好きだよ。
姉ちゃんも、雪男が大好き。
「どこにも行かないで。ずっとここにいて。……だって、ぼく――ぼくには、もう姉さんしかいないんだ……!」
「姉ちゃんもだよ。姉ちゃんにも、雪男しかいない」
世界中から憎まれ、見捨てられた子と。
その子の手以外、何も残されていない子と。
誰からも忘れ去られたような、この古い小さな部屋で、ひっそりといだきあう。ただここだけが、互いの隣だけが、ふたりの居場所だった。
「だから、な。今日はもう布団に入れ、雪男。姉ちゃん、ずっとそばにいてやるから」
「うん……」
ようやく雪男は燐の肩口から顔をあげた。
「コート脱げ。ほら、立てるか?」
「うん」
燐に言われるまま、雪男は大人しく立ち上がる。
ふらつく身体を支えながら、燐はどうにか雪男のコートを脱がしてやった。
が、さすがにパジャマ替わりのTシャツに着替えさせることまでは無理だ。そのまま横倒しにするように、雪男をベッドに入れる。
「姉さん。姉さん――」
それでも雪男は、涙に潤んだ目で燐を見上げ、燐の手を離そうとしなかった。
「お願い。姉さん、ここにいて」
それは幼い日、熱を出して寝込んだ時に、いつもそうやって燐を引き留めようとしたのと同じ声、同じ仕草だ。
「ここにいるよ」
燐はそっと雪男の手を握り返した。
あの頃とは較べものにならないほど、大きく強くなった手。燐を守るために銃を握る手。――けれどまだ、こんなにも燐を必要としてくれる、手。
「姉ちゃん、ずっと雪男と一緒にいるからな。安心しろ」
その言葉に、雪男はようやく幸せそうに微笑み、小さくうなずいた。
そして涙の残るまま、静かに眠りについた。
翌朝。
「あ……た――痛た……。頭が――」
雪男は自分の呻き声で目を覚ました。
頭の芯がずきずき痛む。起きあがろうとしただけで、苦い胃液とともに吐き気がこみ上げてきた。
「う、ぐ……」
どうにも目が開かない。どうしてこんなに体調が悪いのか。
いつも枕元に置いてあるはずの眼鏡を手探りで捜す。が、見つからない。
「あれ……眼鏡、眼鏡――」
普段とは反対側に置かれていた眼鏡を探り当てた瞬間、雪男は昨夜のことをすべて思い出した。
居酒屋での飲み会、シュラに無理強いされた酒。泥酔し、湯ノ川先生と足立先生に寮室まで送り届けてもらったこと。
そして――。
「げ……!」
血の気が引いた。
反射的に室内を見回す。が、燐の姿はなかった。
時計を見ると、午前7時半を回っている。おそらく燐は朝食の準備のため、厨房にいるのだろう。
正直、助かった。昨夜の醜態を思えば、燐に会わせる顔がない。
自分がここまで酒癖が悪いとは思ってもみなかった。泣くわ絡むわ、挙げ句の果てには人前で姉に抱きつき、あんなことやそんなことまで……!
あんなに理性が吹っ飛ぶのなら、せめて記憶も完璧になくなっていてほしかった。
このまま燐には会わず、まっすぐ任務に向かってしまおう。そう思い、雪男はもそもそとベッドから這いだした。
廊下の洗面台で念入りに歯を磨くと、ようやく吐き気が少し治まる。それでも胃は、鉛でも飲み込んだかのように重たい。
昨夜着ていたコートは酒と煙草の臭いが染み付いてしまい、クリーニングに出さなければ、とてもではないが着られない。クロゼットに吊しておいた予備のコートに袖を通し、慌ただしく身支度を整えて、雪男は六〇二号室を出た。
痛む頭を抱えながら一階へ下り、そのままこそこそと玄関へ向かおうとした時。
「こら、雪男! お前、朝飯も食わないで行く気か!」
廊下の突き当たりにある厨房のドアが開いた。おたま片手にエプロン姿の燐が顔を出す。
「あ、ね、姉さん、おはよ……」
「おう。まだ時間あるんだろ? メシできてるぞ」
燐は右手のおたまで、来い来いと雪男を手招きした。
まったく普段通りの燐だ。昨夜のことなどおくびにも出さない。
「ごめん、姉さん。今朝はいいよ。ちょっと食欲が――」
「いーから来い!」
燐に強い口調できっぱり命じられてしまうと、雪男はどうしても逆らえない。我ながら情けないと思うが、子供の頃からの習性が抜けないのだ。
「でもほんとに、今朝はちょっと食べられそうになくて……」
もごもごと言い訳しながら厨房に入った雪男に、燐はそこに座れと、いつもふたりが食卓がわりにしている配膳用テーブルを示した。
「ほら」
雪男の目の前に置かれたのは、湯気を漂わせるみそ汁だった。
ゴボウやにんじん、白菜など、具だくさんのみそ汁。白ごまがふってある。ふわりと立ちのぼるみその良い匂いが、気持ちを落ち着かせてくれるようだ。
「空きっ腹で動くと、よけい気持ち悪くなるぞ。せめてみそ汁だけでも飲んでいけ」
「うん。……ありがとう」
みそとごまの香りに誘われて、雪男は箸を取った。
一口すすると、あったかさがじわっと胸元から胃袋へと落ちていく。昨夜の酒で疲れた体に優しく染み渡っていくようだ。
「旨いか?」
その問いかけに、雪男は素直にうなずいて微笑んだ。
「なんか、ほっとする」
「だろ? 覚えてねえか、それ。親父が飲み過ぎた時によく作ってやってたんだぜ」
「え、そうだったの?」
「ああ。メシは食えなくても、これなら口に入るって言ってな」
火が通って甘みの出た白菜やにんじん、歯ごたえの良いゴボウなどを口に入れると、少しずつ失せた食欲も戻ってくる。そうやって食べ物が入ると、鉛を流し込まれたようだった胃袋もようやく少しずつ動き出し、苦しかったむかつきも治まっていった。
「おかわりは?」
「うん、もらおうかな」
みそ汁のおかわりと、燐はついでに熱い番茶も淹れてくれた。
「昨夜は、ほんとごめん。迷惑かけて」
「謝るんなら、おれじゃなくて湯ノ川先生と足立先生にだろ。ふたりともすっげー汗だくになって、お前をここまで連れてきてくれたんだぞ」
「はい。反省してます」
ぽりぽりと漬け物をかじり、お茶をすすりながら燐は言った。
「ま、おれは気にしてねーから、心配すんな」
「姉さん……」
「けっこう楽しかったぜ。ひさびさに“泣き虫雪男”を見られたしなー」
燐はにかっと、心底楽しそうに笑った。
「お前ってさー、昔からいつもああだったよな。風邪とかひいて熱出すと、急に甘えんぼになっちまって、ひとりじゃ寝てらんなくてさ。“姉さん、姉さん、ここにいて。どっか行っちゃやだー”ってさ。ほんと、可愛かったよなー」
「ね、姉さん。その話はもう……」
「なんだよー、可愛いって言ってんじゃんか。昨夜だってお前、びーびー泣いちまって、“ねーさん、ごめんなさい、ごめんなさい”ってよー! いつもあんなに素直に謝ってくれるなら、おれだって別に怒りゃしねえのによー」
「もう……もう、勘弁してクダサイ……」
みそ汁の椀にすがりつき、雪男は呻くように言った。
恥ずかしいなんてもんじゃない。身の置き所がない。顔をあげることもできない。こんな羞恥プレイをされるくらいなら、頭ごなしに怒鳴りつけられたほうがまだましだ。
「ごちそうさま。ぼく、そろそろ仕事に行かないと――」
雪男は顔を伏せたまま、席を立った。これ以上聞いていたら、どんな話を持ち出されるかわからない。
「おう。気ぃつけて行ってこいよ」
ご機嫌の笑顔で、燐は手を振った。
「今夜は早く帰れるんだろ?」
「ん、まあ……。急な任務が飛び込んでこなければね」
「早く帰ってこいよ。昨夜流れちまった、すき焼きやるからな」
「――うん」
燐が待っていてくれる。そう思うと、雪男の胸の芯にぽっとひとつ、明るい灯がともったような気がする。
ここが自分の戻る場所。姉さんのそばが、世界でたったひとつ、ぼくの居る場所なんだ。
「で、どうする? 晩酌も用意しとくか?」
「……いりません――」
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。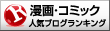
そのうち、燐編(未公開、R18)と合わせてコピー誌にでもまとめようかなあ。
帰ってきたヨッパライ その2
「おッ、おまッ、は、離せ! 離せ、尻尾!」
「やだ。離したら姉さん、どっか行っちゃうじゃないかあ!」
「どこも行きゃしねえよ! 風呂だ、風呂!」
「やだやだやだ! 姉さん、どこにも行かないで!!」
雪男は容赦なく燐の尻尾を引っ張った。
急所の尻尾をロープのように引っ張られたのでは、たまらない。燐は雪男の腕の中へもんどり打って倒れ込んだ。
「なにすんだ、雪男!」
「だって姉さん……姉さんが――」
酔っ払いの弟は、今度はぐすぐすべそをかき始める。
「だぁあ、泣くな! お前、いったい幾つだ!」
「姉さんと同い歳」
「んなこたぁわァってるよ! ヒトの尻尾でハナ拭くなー!」
「うええええん、姉さんが冷たいぃ!!」
とうとう雪男は、赤ん坊みたいに手放しで泣きじゃくり出した。それでも燐の尻尾は離さないが。
「姉さん、どうしてそんな意地悪ばっかりするんだよぅ……」
「はああっ!?」
ふざけるな。それはこっちのセリフだ。
お仕置きだの躾だのと言って、いつもいつも燐に酷い真似ばかりするのは、雪男のほうではないか。
「前は、ぼくがテストでいい点取ったら、ものすごーく誉めてくれたじゃないかあ……。運動会のかけっこで、転んでビリになったって、姉さん、手作りの金メダルをぼくの首にかけてくれて、“おれん中じゃ、いつでも雪男が一等賞だぞ”って……」
「いつの話をしてんだよ!」
「ほらあ。やっぱり冷たいぃー!」
でっかい図体をして、雪男はぐしぐしべそべそ泣きじゃくる。畳にぺったり座り込み、両手で目元をこすって。
その仕草は、遠い昔、いつも燐のあとを追いかけていた、泣き虫で甘ったれの弟そのものだった。
「姉さん。ぼくを置いていかないで……。置いてかないでよぅ……」
「雪男――」
燐はゆっくりと手を伸ばした。
ずれてしまった眼鏡を外し、涙に汚れた雪男の頬をそっと拭ってやる。幼かった日、いつもそうしてやったように。
「どこにも行かねえよ」
こつん、と、おでことおでこをくっつけて。
「どこにも行かない。姉ちゃんはここにいる」
「ほんと……?」
「ほんとだよ。ずーっと、雪男といっしょ」
どうして気づかなかったのだろう。
自分たちは双子の姉弟。どんなに大人びて見えたって、雪男は大事な可愛い弟なのだ。
亡き養父、偉大なる聖騎士・藤本獅郎から、燐の守護者の役目を引き継ぎ、その重すぎる責務をたったひとりで担おうとしている雪男。
いつの間にか燐よりずっと高くなった背丈、広い肩にばかり目を奪われて、つい忘れそうになってしまうけれど。
自分たちは同じ。ふたりぽっちでこの世界に放り出されてしまった子供たち。優しかった父を喪い、声をあげて泣くことすらできずにいる、淋しい、哀しい子供たちなのだ。
「姉さん。姉さん、お願い。ぼくを嫌いにならないで」
雪男はしゃにむに燐にしがみついてきた。まるで迷子の子供がようやく会えた母親にしがみつき、離れまいとするかのように。燐を抱きしめ、肩に額を押しつけて、嗚咽を漏らす。
「ばぁーか。ならねえよ」
燐は優しく、雪男の重みを受けとめた。
「ほんと……?」
「ほんと」
「ほんとに? ほんとに!?」
繰り返される同じ質問に、何度も何度もうなずいてやる。
「ごめんなさい。ごめんなさい、姉さん……。ほんとはぼくだって、姉さんに優しくしたいんだ。でも――でも、どうしても止まんないんだよ……!!」
身体を重ねるたび、雪男は酷く燐を責め苛む。燐はさんざん泣かされ、傷つけられ、気絶するまで苛められる。時にそれは度を超えた暴力に発展してしまうことすらある。
それでも。
――好きだ。好きだ。姉さん、大好きだ……!
熱に浮かされたように同じ言葉を繰り返す雪男を、どうしても拒めない。
「わかってる。ちゃんとわかってっから、心配すんな」
こうやって甘やかしてしまうことは、もしかしたら雪男のためにはならないのかもしれないけれど。
燐は、雪男を抱きしめる手にそっと力を込めた。
そうすると、雪男の体温をさらに近く、しっかりと感じ取ることができる。
――雪男。可愛い雪男。お前、そんなとこは本当になにも変わってないんだな。
お前はおれに、なにしたっていいんだ。
だっておれは、お前から何もかも奪ってしまった。家族も、未来も、夢も、何もかも。おれの弟なんかに生まれなければ、こんなつらい思いをしなくたって良かったのに。
それでもお前が、おれを――こんな魔神の娘を、愛していると言ってくれるなら。
燐を傷つけ、追いつめることでしか、燐の気持ちを確かめられないと雪男が言うのなら、どれほど傷つけられてもかまわない。
雪男に問われるなら、何回でも答える。何回でも、何百回でも、同じ答を。
……好きだよ。
姉ちゃんも、雪男が大好き。
「どこにも行かないで。ずっとここにいて。……だって、ぼく――ぼくには、もう姉さんしかいないんだ……!」
「姉ちゃんもだよ。姉ちゃんにも、雪男しかいない」
世界中から憎まれ、見捨てられた子と。
その子の手以外、何も残されていない子と。
誰からも忘れ去られたような、この古い小さな部屋で、ひっそりといだきあう。ただここだけが、互いの隣だけが、ふたりの居場所だった。
「だから、な。今日はもう布団に入れ、雪男。姉ちゃん、ずっとそばにいてやるから」
「うん……」
ようやく雪男は燐の肩口から顔をあげた。
「コート脱げ。ほら、立てるか?」
「うん」
燐に言われるまま、雪男は大人しく立ち上がる。
ふらつく身体を支えながら、燐はどうにか雪男のコートを脱がしてやった。
が、さすがにパジャマ替わりのTシャツに着替えさせることまでは無理だ。そのまま横倒しにするように、雪男をベッドに入れる。
「姉さん。姉さん――」
それでも雪男は、涙に潤んだ目で燐を見上げ、燐の手を離そうとしなかった。
「お願い。姉さん、ここにいて」
それは幼い日、熱を出して寝込んだ時に、いつもそうやって燐を引き留めようとしたのと同じ声、同じ仕草だ。
「ここにいるよ」
燐はそっと雪男の手を握り返した。
あの頃とは較べものにならないほど、大きく強くなった手。燐を守るために銃を握る手。――けれどまだ、こんなにも燐を必要としてくれる、手。
「姉ちゃん、ずっと雪男と一緒にいるからな。安心しろ」
その言葉に、雪男はようやく幸せそうに微笑み、小さくうなずいた。
そして涙の残るまま、静かに眠りについた。
翌朝。
「あ……た――痛た……。頭が――」
雪男は自分の呻き声で目を覚ました。
頭の芯がずきずき痛む。起きあがろうとしただけで、苦い胃液とともに吐き気がこみ上げてきた。
「う、ぐ……」
どうにも目が開かない。どうしてこんなに体調が悪いのか。
いつも枕元に置いてあるはずの眼鏡を手探りで捜す。が、見つからない。
「あれ……眼鏡、眼鏡――」
普段とは反対側に置かれていた眼鏡を探り当てた瞬間、雪男は昨夜のことをすべて思い出した。
居酒屋での飲み会、シュラに無理強いされた酒。泥酔し、湯ノ川先生と足立先生に寮室まで送り届けてもらったこと。
そして――。
「げ……!」
血の気が引いた。
反射的に室内を見回す。が、燐の姿はなかった。
時計を見ると、午前7時半を回っている。おそらく燐は朝食の準備のため、厨房にいるのだろう。
正直、助かった。昨夜の醜態を思えば、燐に会わせる顔がない。
自分がここまで酒癖が悪いとは思ってもみなかった。泣くわ絡むわ、挙げ句の果てには人前で姉に抱きつき、あんなことやそんなことまで……!
あんなに理性が吹っ飛ぶのなら、せめて記憶も完璧になくなっていてほしかった。
このまま燐には会わず、まっすぐ任務に向かってしまおう。そう思い、雪男はもそもそとベッドから這いだした。
廊下の洗面台で念入りに歯を磨くと、ようやく吐き気が少し治まる。それでも胃は、鉛でも飲み込んだかのように重たい。
昨夜着ていたコートは酒と煙草の臭いが染み付いてしまい、クリーニングに出さなければ、とてもではないが着られない。クロゼットに吊しておいた予備のコートに袖を通し、慌ただしく身支度を整えて、雪男は六〇二号室を出た。
痛む頭を抱えながら一階へ下り、そのままこそこそと玄関へ向かおうとした時。
「こら、雪男! お前、朝飯も食わないで行く気か!」
廊下の突き当たりにある厨房のドアが開いた。おたま片手にエプロン姿の燐が顔を出す。
「あ、ね、姉さん、おはよ……」
「おう。まだ時間あるんだろ? メシできてるぞ」
燐は右手のおたまで、来い来いと雪男を手招きした。
まったく普段通りの燐だ。昨夜のことなどおくびにも出さない。
「ごめん、姉さん。今朝はいいよ。ちょっと食欲が――」
「いーから来い!」
燐に強い口調できっぱり命じられてしまうと、雪男はどうしても逆らえない。我ながら情けないと思うが、子供の頃からの習性が抜けないのだ。
「でもほんとに、今朝はちょっと食べられそうになくて……」
もごもごと言い訳しながら厨房に入った雪男に、燐はそこに座れと、いつもふたりが食卓がわりにしている配膳用テーブルを示した。
「ほら」
雪男の目の前に置かれたのは、湯気を漂わせるみそ汁だった。
ゴボウやにんじん、白菜など、具だくさんのみそ汁。白ごまがふってある。ふわりと立ちのぼるみその良い匂いが、気持ちを落ち着かせてくれるようだ。
「空きっ腹で動くと、よけい気持ち悪くなるぞ。せめてみそ汁だけでも飲んでいけ」
「うん。……ありがとう」
みそとごまの香りに誘われて、雪男は箸を取った。
一口すすると、あったかさがじわっと胸元から胃袋へと落ちていく。昨夜の酒で疲れた体に優しく染み渡っていくようだ。
「旨いか?」
その問いかけに、雪男は素直にうなずいて微笑んだ。
「なんか、ほっとする」
「だろ? 覚えてねえか、それ。親父が飲み過ぎた時によく作ってやってたんだぜ」
「え、そうだったの?」
「ああ。メシは食えなくても、これなら口に入るって言ってな」
火が通って甘みの出た白菜やにんじん、歯ごたえの良いゴボウなどを口に入れると、少しずつ失せた食欲も戻ってくる。そうやって食べ物が入ると、鉛を流し込まれたようだった胃袋もようやく少しずつ動き出し、苦しかったむかつきも治まっていった。
「おかわりは?」
「うん、もらおうかな」
みそ汁のおかわりと、燐はついでに熱い番茶も淹れてくれた。
「昨夜は、ほんとごめん。迷惑かけて」
「謝るんなら、おれじゃなくて湯ノ川先生と足立先生にだろ。ふたりともすっげー汗だくになって、お前をここまで連れてきてくれたんだぞ」
「はい。反省してます」
ぽりぽりと漬け物をかじり、お茶をすすりながら燐は言った。
「ま、おれは気にしてねーから、心配すんな」
「姉さん……」
「けっこう楽しかったぜ。ひさびさに“泣き虫雪男”を見られたしなー」
燐はにかっと、心底楽しそうに笑った。
「お前ってさー、昔からいつもああだったよな。風邪とかひいて熱出すと、急に甘えんぼになっちまって、ひとりじゃ寝てらんなくてさ。“姉さん、姉さん、ここにいて。どっか行っちゃやだー”ってさ。ほんと、可愛かったよなー」
「ね、姉さん。その話はもう……」
「なんだよー、可愛いって言ってんじゃんか。昨夜だってお前、びーびー泣いちまって、“ねーさん、ごめんなさい、ごめんなさい”ってよー! いつもあんなに素直に謝ってくれるなら、おれだって別に怒りゃしねえのによー」
「もう……もう、勘弁してクダサイ……」
みそ汁の椀にすがりつき、雪男は呻くように言った。
恥ずかしいなんてもんじゃない。身の置き所がない。顔をあげることもできない。こんな羞恥プレイをされるくらいなら、頭ごなしに怒鳴りつけられたほうがまだましだ。
「ごちそうさま。ぼく、そろそろ仕事に行かないと――」
雪男は顔を伏せたまま、席を立った。これ以上聞いていたら、どんな話を持ち出されるかわからない。
「おう。気ぃつけて行ってこいよ」
ご機嫌の笑顔で、燐は手を振った。
「今夜は早く帰れるんだろ?」
「ん、まあ……。急な任務が飛び込んでこなければね」
「早く帰ってこいよ。昨夜流れちまった、すき焼きやるからな」
「――うん」
燐が待っていてくれる。そう思うと、雪男の胸の芯にぽっとひとつ、明るい灯がともったような気がする。
ここが自分の戻る場所。姉さんのそばが、世界でたったひとつ、ぼくの居る場所なんだ。
「で、どうする? 晩酌も用意しとくか?」
「……いりません――」
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
そのうち、燐編(未公開、R18)と合わせてコピー誌にでもまとめようかなあ。