読書は体をつかってするものだ、と思う。
頭と、目と、本を持つ手。たぶんきっと、それだけではない。
本多孝好という人は、なにか本格的な身体トレーニングでもしながら、本を書くのではないかとさえ思う。どれだけ微細に、空間を把握しているのか。
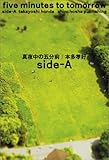 | 真夜中の五分前five minutes to tomorrow side-A 1,296円 Amazon |
 | 真夜中の五分前five minutes to tomorrow side-B 1,296円 Amazon |
真夜中の五分前five minutes to tomorrow side-A 単行本 – 2004/10/29
本多 孝好 (著)
この本の中で、主人公は、やたらと他人の緊張を感じる。
無生物の表情を読み取る。自動ドアと会話する。
声なきもの、言葉なきもののことばを過敏に感じ取る。
この本が出版されたのは、10年以上前のこと。私は高校生だった。
あの時に、読んだ経験があってよかったと思う。
いつか、どこかの作家が、「とにかく、少女の青春物語は、若いうちに読んでおいたほうがいい」というのを言っていたような。
自分が年を取ってしまうと、もうその少女たちに感情移入するのが困難になるから。
主人公は26歳。
この主人公が、わたしより年上で、社会人の先輩として映るうちに、この本の手触りを感じていてよかった。
今、彼はわたしの年下になるけれど、こんな部下がいたら恐ろしいと思うもの。自分の現状と照らして、劣等感にまみれる。
若いころに感じた手触りを、お守りみたいに横において、読み進められたことは、幸福だった。
当時、その描写と、語り口の軽妙さに心酔して、何度もよみかえしていたのだけれど、今回読み直して、これは、枠の話だったと思い直す。
主人公は、強固な土台を探している。崩れない基礎を求めている。
人はたくさんの枠組みをつくる。倒れないための基礎を構築する。たくさんのハリボテをつけて。装飾で着飾って。
枠組みにみえて、役割をなさないものもある。また逆もしかり。
数は無限にある。形もさまざま。
それでも、すべてに共通する譲れない根幹の部分を求め、主人公は、体験を、実験を深めてゆく。
あえて、その土台を真夏の炎天下に野ざらしにしたり、強固な金づちで割ってみたりする。時には自ら地震を起こすことさえも厭わない。
あらゆる実験を超えて、極限まで、簡素化したその枠組みに、主人公は嘆く。
そこに、意味があるのか。
そして、そこに、彼は自分の実態を見出す。
「side-A」の最後のシーンと、「side-B」で、バーテンダーが出てくる部分は、涙があふれて止まらなかった。
悲しい描写は、切ない描写は、ほかにもある。でも、ここが、私のこころをとらえて離さないのだ。
たとえば、急に右足の脛が痛み出し、しばらくして
「ああそうだ、ここを3年前に骨折したのだ、と思い出すような。
あるいは、いきなり吹き出す自分の汗を見て、
ああ、そうか、ずっとミストサウナを浴びていた、と気づくような。
理由があとからやってくるような胸の痛みを、この小説はいつも醸している。
遠いところから、湧き上がるのだ、感情が。
言語表現の限界に屈伏しながら、その可能性を、皮膚感覚から伝えてくる。
才能とか、個性とか、本当に恐ろしいなぁと思う。
