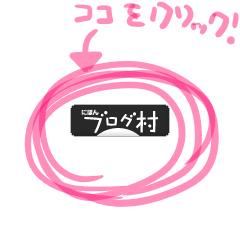10月上旬から今年のノーベル賞受賞者が発表されて、日本からは赤崎勇さん、天野浩さん、中村修二さんの3人がノーベル物理学賞を受賞されました。
おめでとうございます!!
エネルギー効率が良く、環境にも優しいLEDを開発した実績が認められたということでしたが、日常生活で当たり前のように使っているLEDの商品化に日本人がこれほど大きな貢献をしていたとは、恥ずかしながらこの受賞のニュースを目にするまで知りませんでした・・・。
ノーベル賞の選考委員の方が、
「白熱電球が20世紀を照らした。21世紀はLEDが照らす」
とコメントされたそうで、発明王エジソンに肩を並べるような素晴らしい研究として世界的に認められたのは嬉しいことですね。

#31 - LED / Mike Deal aka ZoneDancer
ところで、このニュースと並んで今話題になっているのが、
「特許法の改正」についてです。
特許庁の特許制度小委員会の中で、職務発明制度の見直しが議論されており、職務発明に関する特許を受ける権利を、現行の「社員のもの」から、新しく「法人のもの」としようとしています。
法人に特許権を持たせることで企業の迅速かつ的確な意思決定を促すとともに、開発した社員に対しては現行法と同程度の報償を保障することを義務付ける仕組みです。
現在進行中の議論なので、今後の展開が興味深いですが、これについては賛否両論あるようです。
賛成意見としては、
「発明報酬を巡る企業と従業員との訴訟リスクを減らせる」
「近年は個人ではなくチームでの研究開発が主流で、実態に沿っている」
などがあります。
反対意見としては、
「報償のルール策定は中小企業にとって負担が大きい」
「法人に帰属させると、研究開発者の意欲が失われる」
などがあります。
特に、今回ノーベル賞を受賞した中村修二さんは、かつて特許訴訟を起こした経験もあって、改正に反対の立場をとっています。
中村さんが1990年に青色LEDの製造装置に関する技術を開発した時に、会社からの報奨金は「2万円」だったそうです。
その後、中村さんは会社を相手取って訴訟を起こし、最終的には「約8億円」の支払いで和解が成立しました。
現在では特許に関する報償も改善されてきており、中村さんのようなケースは少なくなってきているようですが、この法律改正の動きで今後がどうなるのか、注目ですね。
CARPで学んでいる「統一原理」の中に、「二重目的」というものがあります。
少し長いですが引用しますと、
「すべての存在は二重目的をもつ連体である。既に述べたように、すべての存在の中心には、性相的なものと、形状的なものとの二つがあるので、その中心が指向する目的にも、性相的なものと形状的なものとの二つがあって、それらの関係は性相と形状との関係と同じである。そして、性相的な目的は全体のためにあり、形状的な目的はそれ自体のためにあるもので、前者と後者は、原因的なものと結果的なもの、内的なものと外的なもの、主体的なものと対象的なものという関係をもっている。それゆえに、全体的な目的を離れて、個体的な目的があるはずはなく、個体的な目的を保障しない全体的な目的もあるはずがない」
ごく簡単にいってしまえば、全体目的と個体目的が相乗効果をもたらすのが理想だ、ということです。かなり強引な気もしますが。

Diagonal arrow made from puzzle pieces / Horia Varlan
この特許法の改正の議論で言えば、全体目的は企業の発展やそれに伴う社会の発展であり、個体目的は研究開発者の喜びや幸福といったようなものでしょう。
この二つの目的がうまく調和していけばいいのですが、中村さんのケースのように全体目的ばかり大きくなると、結局うまくいかなくなってしまいます。
かといって個人の権利ばかりを保護しても全体の幸福(社会の発展など)が損なわれる可能性があります。
特許法の改正で、このバランスがどうなるのかがポイントなのかな、と、個人的には思っています。
改めて、今後の議論の流れを注視していきたいですね。
hoymin
(参考リンク)
第9回特許制度小委員会資料
10/18 日本経済新聞
10/8 産経ニュース
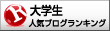
大学生 ブログランキングへ
おめでとうございます!!
エネルギー効率が良く、環境にも優しいLEDを開発した実績が認められたということでしたが、日常生活で当たり前のように使っているLEDの商品化に日本人がこれほど大きな貢献をしていたとは、恥ずかしながらこの受賞のニュースを目にするまで知りませんでした・・・。
ノーベル賞の選考委員の方が、
「白熱電球が20世紀を照らした。21世紀はLEDが照らす」
とコメントされたそうで、発明王エジソンに肩を並べるような素晴らしい研究として世界的に認められたのは嬉しいことですね。

#31 - LED / Mike Deal aka ZoneDancer
ところで、このニュースと並んで今話題になっているのが、
「特許法の改正」についてです。
特許庁の特許制度小委員会の中で、職務発明制度の見直しが議論されており、職務発明に関する特許を受ける権利を、現行の「社員のもの」から、新しく「法人のもの」としようとしています。
法人に特許権を持たせることで企業の迅速かつ的確な意思決定を促すとともに、開発した社員に対しては現行法と同程度の報償を保障することを義務付ける仕組みです。
現在進行中の議論なので、今後の展開が興味深いですが、これについては賛否両論あるようです。
賛成意見としては、
「発明報酬を巡る企業と従業員との訴訟リスクを減らせる」
「近年は個人ではなくチームでの研究開発が主流で、実態に沿っている」
などがあります。
反対意見としては、
「報償のルール策定は中小企業にとって負担が大きい」
「法人に帰属させると、研究開発者の意欲が失われる」
などがあります。
特に、今回ノーベル賞を受賞した中村修二さんは、かつて特許訴訟を起こした経験もあって、改正に反対の立場をとっています。
中村さんが1990年に青色LEDの製造装置に関する技術を開発した時に、会社からの報奨金は「2万円」だったそうです。
その後、中村さんは会社を相手取って訴訟を起こし、最終的には「約8億円」の支払いで和解が成立しました。
現在では特許に関する報償も改善されてきており、中村さんのようなケースは少なくなってきているようですが、この法律改正の動きで今後がどうなるのか、注目ですね。
CARPで学んでいる「統一原理」の中に、「二重目的」というものがあります。
少し長いですが引用しますと、
「すべての存在は二重目的をもつ連体である。既に述べたように、すべての存在の中心には、性相的なものと、形状的なものとの二つがあるので、その中心が指向する目的にも、性相的なものと形状的なものとの二つがあって、それらの関係は性相と形状との関係と同じである。そして、性相的な目的は全体のためにあり、形状的な目的はそれ自体のためにあるもので、前者と後者は、原因的なものと結果的なもの、内的なものと外的なもの、主体的なものと対象的なものという関係をもっている。それゆえに、全体的な目的を離れて、個体的な目的があるはずはなく、個体的な目的を保障しない全体的な目的もあるはずがない」
ごく簡単にいってしまえば、全体目的と個体目的が相乗効果をもたらすのが理想だ、ということです。かなり強引な気もしますが。

Diagonal arrow made from puzzle pieces / Horia Varlan
この特許法の改正の議論で言えば、全体目的は企業の発展やそれに伴う社会の発展であり、個体目的は研究開発者の喜びや幸福といったようなものでしょう。
この二つの目的がうまく調和していけばいいのですが、中村さんのケースのように全体目的ばかり大きくなると、結局うまくいかなくなってしまいます。
かといって個人の権利ばかりを保護しても全体の幸福(社会の発展など)が損なわれる可能性があります。
特許法の改正で、このバランスがどうなるのかがポイントなのかな、と、個人的には思っています。
改めて、今後の議論の流れを注視していきたいですね。
hoymin
(参考リンク)
第9回特許制度小委員会資料
10/18 日本経済新聞
10/8 産経ニュース
大学生 ブログランキングへ