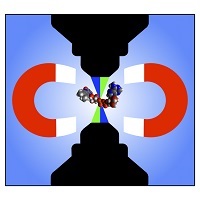前回のブログ『番外編 負ける訳にはいかない・爪の裏側・・次回に続く前に独り言 ・・』
より続きます。
https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12645058424.html
※再投稿(2020/12/29 14:45)
2020-12-29 12:11に投稿の当ブログ、最下部近くに追記を書かせて頂きました。
訂正 2020/12/30 09:25
ブログ内記述
朝鮮半島まで到達した火砕流・・は 訂正いたします。
朝鮮半島まで到達した火山灰・・であります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。
お読み下さった皆様方には心から感謝いたしております。
度重なる自然災害、さらに新型コロナウィルスの感染により、
愛するご家族、親戚やご友人の方々に看取られる事なく、一人で旅立つ事をよぎなくされた
御方々の御冥福を心よりお祈り申し上げます。
ご家族の代わりに、献身的な看護、そして治療に従事なさっていらっしゃる医療現場の方々の御苦労に心から感謝致しております。
この難局を世界中がいち早く乗り切れる日が来ることを心よりお祈りいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初めに
前回、『この植物は一体何でしょう?』と書かせて頂いた、家の元敷地内に生えた「植物」に関して、ツボ様より
テイカカズラでは? とのご教示を頂きました😊
早速、テイカカズラをウィキペディアで調べました(p_-)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%83%A9
テイカカズラ ウィキペディアより抜粋致します。
テイカカズラ(定家葛、学名: Trachelospermum asiaticum)は、キョウチクトウ科テイカカズラ属のつる性常緑低木。有毒植物である。
和名は、式子内親王を愛した藤原定家が、死後も彼女を忘れられず、ついに定家葛に生まれ変わって彼女の墓にからみついたという伝説(能『定家』)に基づく。
茎からは気根を出して他のものに固着する。茎の表面には多数の気根が出た跡が残るので、樹皮には多数の突起がある。大きくなると、枝先は高木層の樹冠に達し、幹は直径数cmに達する。
成木になると樹皮から離れて枝を空中に伸ばし、葉は大きく黄緑色になる。葉は長さ1cm(幼木)から数cm(成木)あり、質感は様々で、一般に幼木の方が革状で光沢がある。
特に幼木の間は地上をはいまわり、地面に葉を並べる。このときの葉は深緑色で、葉脈に沿って白い斑紋が入ることが多い。
6月頃に花を咲かせる。花は房状の花序が垂れ下がったところにつく。花弁の基部は筒状で、先端は5裂して広がる。それぞれの裂片は先端が断ち切られて丸まったような三角形で、それぞれにわずかにねじれ、全体としてプロペラ状になる。花ははじめ白く、次第に淡黄色になり、ジャスミンに似た芳香がある。
分布と生育環境
朝鮮半島、日本(本州 - 四国・九州地方)の温暖な場所に分布する。
古典に「まさきのかづら(真拆の葛)」「まさきづら(真拆葛)」とあるのも本種のことといわれる。
み山には あられ降るらし と山なる まさきのかづら 色づきにけり
—神遊びの歌、『古今集』巻第二十・1077番歌
我が手をば 妹(いも)にまかしめ 真栄葛(まさきづら) 手抱(たた)き糾(あざ)はり…〔下略〕…
—歌謡、『継体紀』
以上 ウィキペディアより抜粋させて頂きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウィキペディア の地上を這う様子(写真)を拝見すると確かに似ています(画像 小)

家の元敷地内の植物
テイカカズラには白い花が咲くようですが、こちらには白い花は咲きません・・・
がしかし!!
ジャスミンによく似た香りの花が咲く木が近くに立っている事に気が付きました!
やはり、この植物はテイカカズラ もしくは近種ではないのか!?と考えた時に気が付きました
※古典に「まさきのかづら(真拆の葛)」「まさきづら(真拆葛)」と
あるのも本種のことといわれる。
み山には あられ降るらし と山なる まさきのかづら 色づきにけり
—神遊びの歌、『古今集』巻第二十・1077番歌
実は、今月15日以降から、こちらは、最低気温が-5℃から-7.5℃といった日が
数日続いていたのですが・・・(九州のヒマラヤか!?😅)
一例 <m(__)m>
お陰で、「謎の植物」も完全に色づきました!
古典に「まさきのかづら(真拆の葛)」「まさきづら(真拆葛)」とあるのも本種のことといわれる。
※み山には あられ降るらし と山なる まさきのかづら 色づきにけり
—神遊びの歌、『古今集』巻第二十・1077番歌
うちの かづらも 色づきにけり です😊
ツボ様 あらためましてありがとうございました!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回のブログのタイトルは人間の地磁気感受性と阿米と繋がる中世の球磨と致しました。
11月27日投稿のブログ
『アニミズム 強磁性と反磁性 球磨は何故祈りの地なのか』に対して
https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12640100141.html
堀ノ内様、青い海様より、とても参考になるご教示をコメントにて頂きました。
堀ノ内様、青い海様 ありがとうございました。
お二人から頂いたご教示を元に私なりに勉強をさせて頂き、気が付いた事等を今回書かせて頂きます。
時間軸の観点から青い海様から頂いたご教示、さらに堀ノ内様から頂いたご教示についてご紹介させて頂きます。
1.地磁気感受性を人間は持っていた
①クリプトクロムとは一体何か?
青い海様から頂いたご教示をご紹介致します。
〉クリプトクロム1aという化学物質が網膜にある磁場を知覚する物質らしい。これと同じCRY1,CRY2は植物にあり赤色、近赤外。光受容体である。これらの化学物質が渡り鳥にあり、磁場を知覚するが、哺乳類にも微量存在するらしい。
〉即ち、地球上の全ての物質は上空の磁場と繋がっているのでないかと独断です。
私も早速、クリプトクロムについて、勉強させて頂きました。
まずは東京大学 公式ページ内
総合文化研究科・教養学部 掲載日:2015年6月5日
動物の磁気を感じる能力の可視化に向けて
微小空間で光化学反応が磁場に反応する様子を直接観測 を拝見致しました。
拝読して、理解出来た事は
ある種の昆虫、魚、鳥、哺乳類は、磁場を感知する能力を持っている=磁気感受能
磁気感受能に関係していると示唆される物質が =クリプトクローム
クリプトクロームとは タンパク質であり、その中でも特にフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)という分子が磁気感受能に関係している
という事でした。
※哺乳類は、磁場を感知する能力を持っている
では人間はどうなのか!?
すでに発表されていました!!
②人間の地磁気感受性
2019年3月19日、東京大学と米カリフォルニア工科大学などの共同研究チームは、
多くの人に地球の「磁気」を感じる能力があることを発見したと発表されていました!
プライムオンライン様
あなたも「地磁気」を感じる“第六感”がある!? 何に役立つのか 東大の研究者に聞いてみた
をぜひ!皆様、ご覧下さい。
東京大学大学院の真渓歩准教授のお話を拝読して理解出来た事をまとめます。
地球と同じぐらいの磁気を発生し、その方向をコントロールできる装置を設置して人間の脳波を計測した結果、地磁気の方向を変えると脳波が変化することを発見!
人間も地磁気を感じることができると結論付けられた。
人間の頭の中の至る所にはマグネタイトと言われている鉄の酸化物が存在
目の網膜にはクリプトクロムというタンパク質が存在
今までは
「人間の祖先は地磁気感受性を持っていたけど今はずいぶん弱っている」と考えられていた。
この研究で使われた「アルファ波の振幅が小さくなる変化によって間接的に反応があったとする」方法は、第六感や意識の研究者にとってひとつの指針になるという。
凄い!!凄いです!!
\(◎o◎)/!
やはり、人間には
磁気感受能が存在していた!
という事ですね!
ブログ『アニミズム 強磁性と反磁性 球磨は何故祈りの地なのか』で書いていた事
古代の祈りにも繋がっているのでは!?
と、私の直感(第六感)が感じております・・・・
※人間の祖先は地磁気感受性を持っていたけど今はずいぶん弱っていると考えられていた
しかし!ご研究で、今でも人間は継続して地磁気感受性を持っている事が証明された
古代の方々は、現代人より、もっと地磁気感受性が強かった・・
その能力を生かして、自然災害、例えば「火山噴火」や「地震」の前の磁気刺激に反応していたのではないでしょうか!?
そう考えると、以前から何度も書いていますように、喜界カルデラの爆発的噴火を
縄文時代の九州南部にいらした高度な文化を持った方々が何も感じずに「滅亡」したとは
私には到底考えられません!
事前に脱出なさったか・・・もしくは
ブログ『(追記あり)動画の補足 姫島・阿蘇・多久との交流 と球磨郡内のシェルター』
で書いたように・・・・
天然シェルターとなる鍾乳洞等に避難されていた可能性も
ありうるのでは・・!?
★縄文早期の遺跡では、球磨村大瀬洞穴遺跡と同村高沢洞穴遺跡が有名である。
いずれも石灰岩地帯にある鍾乳洞の遺跡で、骨や貝殻などの保存に適した条件を備えている。
球磨郡内には球泉洞を含む多数の鍾乳洞があります・・・
例えば 神瀬(こうのせ)石灰洞窟
日本最大の洞口を持つ洞窟
開口部の横が約40m・高さが約17m

天然シェルターとなる鍾乳洞に喜界カルデラの爆発的噴火によるアカホヤが積もっていたとは今まで勉強不足か、拝見した事が無いような気が・・・
しかし、喜界カルデラの爆発的噴火直後は、火山灰が空を埋め尽くし、太陽光は地上には届いていなかったのでしょうね・・・
それは・・まるで 夜が続くような日々が続いたのだろう
と私は推測致します・・
地上には、火山灰が蓄積して、すぐに人が住める環境ではなかったはずです。
移動を決意した方々は 何処に向かったのか・・・
喜界カルデラの爆発的噴火 ウィキペディアより抜粋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E7%95%8C%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A9
先史時代以前に複数回の超巨大噴火を起こしている。約7300年前の噴火は過去1万年では世界最大規模で、火砕流が九州南部にも到達し、九州南部の縄文人を絶滅させたと推測されている
画像 ウィキペディアより
幸屋火砕流と鬼界アカホヤの広がり。九州南部・東部、四国、本州瀬戸内海沿い、および和歌山県で20cm以上あり、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布する。

朝鮮半島まで到達した火山灰・・
もしも・・・私だったら 海を経由して
火山灰の無い、東北か・・もしくは
中国南部まで逃げて新天地を探したかもしれない・・ と考えました。
九州南部には縄文早期から想像を絶する程の高度な文化を持った方々が住されていた事は
ブログ『11万年前以前からの球磨人と、超古代からの球磨のおさらい』でもご紹介致しました
私は・・・九州南部の縄文人は絶滅したとは到底考えられません。
新天地で系を繋げて、弥生時代に戻ってこられた・・
とあらためて、強く感じました。
青い海様 あらためまして クリプトクロムと磁性に関するご教示を頂いた事を
心よりお礼申し上げます。 ありがとうございました。
2.中世の球磨 永里氏の出自
ブログ『アニミズム 強磁性と反磁性 球磨は何故祈りの地なのか』 の中で中世、南北朝期の球磨の国人衆をご紹介させて頂きました。
南北朝時代に登場する国人と城館分布図

当時の国人衆
上相良氏(多良木氏)・久米氏・小田氏・奥野氏・宮原氏・岡本氏・
須恵氏・永里氏・平川氏(平河氏)・下相良氏(人吉)
上記の永里氏に関して堀ノ内様よりありがたいご教示をコメントにて頂きました。
堀ノ内様よりご教示頂いた
人吉庄永里村地頭職系図 をご紹介させて頂きます。
橋口源右衛門所持古系図(この系図の横に橋口家系図があります。)
肥後国人吉庄東郷永里村并 同国合志庄高永地頭職相伝系図
合志九郎季高ー永里次郎季綱ー弥次郎基季ー小次郎保基ー
弥次郎基平ー彦次郎高重(一童名法師房丸)(この人の従兄弟に木場五郎季親)
私は人吉庄永里村地頭職系図を拝見して たいへん驚きました!
合志九郎季高! 最初からもうビックリです!!
以下をご覧下さい。
「建久八年(1197年)肥後国球磨郡図田帳(相良家文書)」に残る各氏をご覧ください(..)
相良氏入国以前の肥後国球磨郡図田帳です。
山江村誌 歴史編より引用
※蓮華王院人吉庄
領家 八条院
預所 対馬前司 清業 (中原清業)
下司 藤原友永 字人吉次良(人吉次郎)
政所 藤原高家 字須恵小太良(須恵小太郎)
地頭 藤原季高 字合志九良(合志九郎)
同 藤原茂綱
同 藤原真宗 久米三良(久米三郎)
同 尼西妙
※鎌倉殿御領 五百丁
預所 因幡大夫判官 (大江広元)
内永吉庄三百丁 地頭 良峯師高子息 字平 紀平次 不知実名
須恵小太良(郎)家基領 百五十丁
※公田 (旧久米郷)
豊富 地頭 藤原真家 字久米三良(久米三郎)
豊永 地頭 藤原家基 字須恵小太良(須恵小太郎)
多良木村没官領 伊勢弥二良 不知実名(伊勢弥二郎 不知実名)
※その後久米氏は寛元二年(1244年)五月十五日の人吉庄起請田以下中分注進状(相良家文書)の署判に「惣公文藤原真憲」として見える。
と山江村誌には記されています。
※地頭 藤原季高 字合志九良(合志九郎)
つまり!この方が、堀ノ内様からご教示頂いた
『合志九郎季高』 でいらっしゃった!と言う事になります。
もう、ビックリして・・感動しました!
建久八年(1197年)肥後国球磨郡図田帳をみると
本来、『合志九郎季高』と言う方は蓮華王院人吉庄内の何れかの地の地頭となられ
後に永里次郎季綱と言う方が永里村(旧上村永里、現あさぎり町上永里)の地頭になられた・・
と言う事が解りました。
おそらく、相良長頼公が人吉庄の地頭職を源頼朝公から正式に補任された「後」の事だと思います。
さらに堀ノ内様は 私の過去記事をご覧になられた上で
〉永里村と高永の所に、小さく永里彦次郎とあるのを見つけました!
系図に名前がある。彦次郎高重という人と同一人物でしょうか!?古文書と系図の人物が一致するのは、珍しいのでおどろきです。
とコメントして頂きました。
私の過去記事とは ブログ 相良定頼并一族等所領注文 であります。
https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12099386694.html
永里彦次郎という御方の名が記されているのは こちらです
画像最後の行「岡本又二郎分」から続きます。
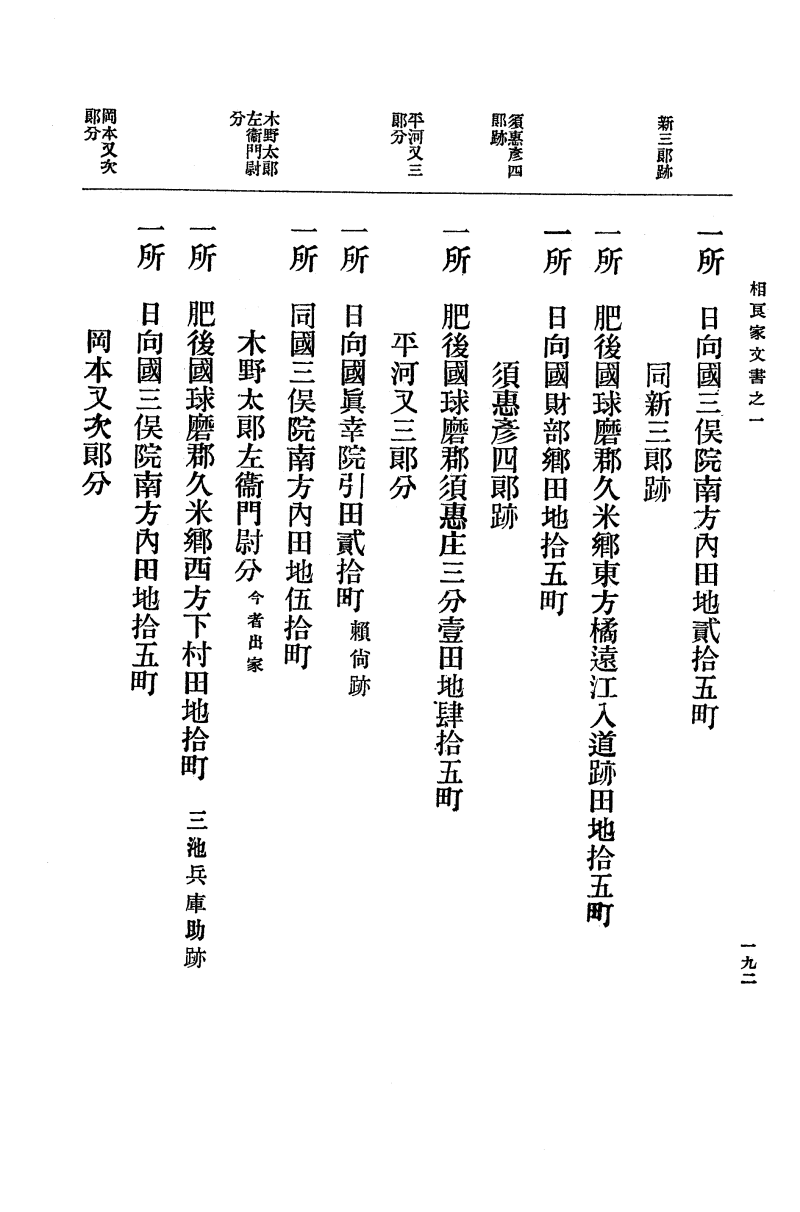
最初の行に 永里彦次郎跡、加庶子 と記されています。

堀ノ内様がご指摘なさった事で、私も永里彦次郎という御方の名前・・
何処かで見た事がある記憶が残っていましたので、再度、過去自分が調べていた事でブログには書いていない事を見直しました。
すると(p_-) ありました!!\(^o^)/
南北朝の内乱について 「山江村誌」より抜粋します。
球磨郡では、人吉の相良定頼が九州の少弐・大友・島津らとともに足利尊氏に呼応した。
ところが・・
多良木の相良孫三郎経頼・須恵彦三郎・永里彦次郎・岡本・奥野・橘佐渡八郎・橘遠江入道道公らは、南朝方として挙兵。
「相良孫三郎以下凶徒」と呼ばれる事となる。
球磨郡の南朝方の拠点は、永吉庄木上城。そして、北朝方の拠点は山田城であり、いずれも、少弐頼尚領である。
※多良木の相良孫三郎経頼・須恵彦三郎・永里彦次郎・岡本・奥野・橘佐渡八郎・橘遠江入道道公らは、南朝方として挙兵。
ありました!「永里彦次郎」
この方が堀ノ内様からご教示頂いた系図に記された
肥後国人吉庄東郷永里村并 同国合志庄高永地頭職相伝系図
合志九郎季高ー永里次郎季綱ー弥次郎基季ー小次郎保基ー弥次郎基平ー彦次郎高重(一童名法師房丸)(この人の従兄弟に木場五郎季親)
彦次郎高重(一童名法師房丸) この方のようです!
〉古文書と系図の人物が一致するのは、珍しいのでおどろきです。
私も非常に驚きました!
堀ノ内様 あらためまして ありがとうございました!
所で・・皆様
先にご紹介した私の過去ブログ 相良定頼并一族等所領注文を
ぜひじっくりとご覧頂きたいと願います。
当時の相良一族が球磨だけではなく、九州南部から九州北部にかけて多くの所領地を持っていた事が良く理解頂けると思います。
相良氏族として記された方々の姓をご覧頂くと、さらに多くの姓がある事にもお気づきになられるはずです(p_-)
久米氏族 秋山氏 も 相良一族の中に名を連ねていらっしゃる事にも私は気が付きました
(p_-)・・・・・(yabutsubakime様へ にこ~っ😊)
※多良木の相良孫三郎経頼・須恵彦三郎・永里彦次郎・岡本・奥野・橘佐渡八郎・橘遠江入道道公らは、南朝方として挙兵。
「相良孫三郎以下凶徒」と呼ばれる事となる。
橘佐渡八郎・橘遠江入道道公らは、南朝方として挙兵
所領地の大半を失う事になるのですが・・・・
でも! 宮原村だけは 重代相伝の地 として 残ったようです\(^o^)/
多良木町史より 橘薩摩公多譲状 小鹿島文書より
橘 公多譲状 『小鹿島文書 』より
ゆつり阿たうる左衛門か所 (譲り与える左衛門か所)
ひこのくに くまのこほり くめのかう東方下ふんミやのはう
(肥後国球磨郡久米郷東方下分宮原)
ふせんのくにそへたの志やう(豊前国副田庄) のうちやしき併にちとう志き(屋敷 地頭職)
の事
右、 所領者、公多ちう いさ うてんのしよりゃやう(重代相伝所領) 也、
したいのてつき(次第手継)御下文以下あいそゑ(相副)ゆつる所也、仍自筆之譲状如件
正平廿 一年三月九日 橘 公多 (花押)
過去ブログで気が付いていた事ですが、
正平廿 一年
南北朝時代、北朝方と南朝方は其々異なる元号を使用していました。
正平廿 一年(1366年)とは北朝方が使用した元号で言うと『貞治5年』です!
「橘公多」が使用された元号は正平廿 一年(1366年)。
使用された元号は南朝方が使用した
「正平」であった!!
つまり・・・橘 公多 という御方は・・・南朝方でいらしたようです(p_-)
さらに(p_-)
南北朝時代の球磨の国人衆 南九州国人一揆の契り状で詳しくご覧頂く事が出来ます。
多良木町史より
一揆神水契状案 (久米氏 相良氏)
続く 一揆神水契状案
拡大して頂くと 平川氏 や宮原橘公冬 といった球磨の国人衆の名を確認して頂けます。
う~む(p_-)
久米郷宮原村は 重代相伝を守る事が出来たようです・・(p_-) \(^o^)/
マタマタ、所で・・・(p_-)
今回のブログのタイトルに 私は※阿米と繋がる中世の球磨 と書いております。
今から書かせて頂く事は次回の予告編でございます。
阿米・・・ この方の名前は松野連系図に記載されたお名前です。
私は、かなり以前から気になる記述に気が付いておりました。
神武天皇様の意を受けて、大久米命様はイスケヨリヒメ様に会いに行きます。
するとイスケヨリヒメ様は、見慣れない風貌の大久米命様に驚きこう答えたのでした。
阿米都都(あめつつ) 知杼理麻斯登登(ちどりましとと) 那杼佐祁流斗米(などさけるとめ)
※天地 千鳥真鵐 など黥ける利目
(大意)あなたはなぜ、いろいろな鳥のように目のまわりに入れ墨をして、鋭い目つきをしているのですか。
阿米都都 知杼理麻斯登登 那杼佐祁流斗米
「阿米」を現代の方々は 「大地」と訳されていらっしゃるようですが、
私は・・・何だか違うようなきがするのですよね・・(ど素人がすみませんが・・)
あなたは=阿米 と訳するのならば・・
大久米命 様 = もしかしたら・・阿米様・・??
ではないのか!? と。
さらに、先にご紹介した球磨の永里氏・岡本氏 は藤原姓菊池一族の方々・・
球磨には藤原姓久米氏もいらっしゃる・・
その球磨を統治した 相良氏は藤原南家 工藤一族であり伊東氏から養子が入られている・・・
そこで、今年最後の謎を皆様にご紹介して、次回の予告編と致します<m(__)m>
皆様方にぜひご覧頂きたい系図がございます。
女王卑弥呼の特使派遣 < 「魏志倭人伝」と伊東氏大系図 > サイト様です。
南家伊東氏藤原姓 大系圖 には
①梨津臣命=梨迹臣命=難升米命 (なしとみ・なしょみ)
②伊世理彦命=伊聲耆命=伊聲耆命 (いせり))
この方々が記されているようです・・・
私も、所有する相良藩史に記載の相良氏系図を見たのですが・・
梨迹臣命 = 難升米命様??
記載されていました・・・
多くの国人衆の中から、室町時代初頭に相良氏が何故?
球磨を統一する事が出来たのか?
南家伊東氏藤原姓 大系圖を拝見して以降、この事が頭の中を
駆け巡っています
追記 2020/12/29 14:45
ご参照下さい・・・ブログ 共通のアニミズム 自然崇拝と・・金印・・
https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12642931490.html
太伯王には子供さんはいらっしゃらなかった・・・
「呉太伯世家」 とは 弟の虞仲(仲雍)王の系 を指す・・・・
つまり 夫差(フサ)王は 弟の虞仲(仲雍)王の系であり 「呉太伯世家」である・・・
つまり・・・つまり・・・
自謂太伯之後 とは呉太伯世家夫差(フサ)王の 後裔である
と言う意味では・・・
球磨の熊津彦様のご先祖様は
春秋時代の呉国国王夫差王となられる・・・・
熊津彦様の御子息が、難升米命様・・・・
天孫族と言われる方々は・・本当は全て繋がっていらっしゃるような気がします。
母系での繋がりかもしれませんね・・・
上記に書いた事は マダマダ次回の予告編でございます。
さらに、気が付いた事が 沢山 ございます(p_-)
皆様
最後までご覧頂き ありがとうございました。
今回が今年最後のブログとなりそうです。
今年一年、色々な事がありました。
コロナはもちろんの事、 100年に一度(実際はもっとでしょう)と言われる大水害も経験した
おそらく、一生忘れない悲しい年でもありました。
皆様方から頂いた ありがたいご教示、そして、辛い時に頂いた励ましのお言葉の数々
心からお礼申し上げます。
ありがとうございました
これからも、どうぞ よろしくお願い致します。
来年はきっと良い年になりますように!
皆様方 お身体十分にお気を付けてお過ごし下さい。
今年最後にご紹介する曲は・・・
川村ゆみさんの KUMAKOI六調子 で ございます😊😊
負けんば~い!!
球磨の地より ひろっぷ でした😊
次回『新年のご挨拶と 球磨弁ひろっぷと共に徒然なるままに・・・』に続きます。