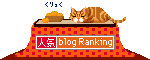この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
翔の蹄は力強く地を蹴る。
逞しい黒馬の筋肉の躍動が日を弾く汗を煌めかせている。
その二人を乗せて神語りの世界を行くに相応しい姿であった。
契りを交わした日と月は、
その契りを地においてまっとうせんがため
朝まだき、
同じ野を駆けて興津を訪れた。
その一日が終わろうとしている。
日を戴く男は、
逞しい体躯に長衣をはためかせて馬を駆り、
花嫁衣装の可憐な月をその腕に抱く。
さながら一幅の絵と見える情景の中で、
朔夜は
夢うつつをさまよっていた。
切れ切れに浮かぶ一日の情景が
幻のように頼りなかった。
赤衣の群れから立ち上った殺気、
〝ころしてはならぬ〟という神渡の声、
頬に触れた見知らぬ男の指先、
その男の顔、
………………不思議な顔だった。
それから先はすべてが茫漠としていた。
ひらひらと揺らめく布やら
ひやっと唇に触れた紅筆やら
ゆらめく視界が定まったのは神渡の姿が見えたときだった。
この腕は神渡様の腕………。
朔夜は覚えず
その腕に頬を寄せた。
「朔夜、
いかがした?」
優しき声が降ってくる。
「我は神渡様のもの………と
思うておりました。」
「我もそなたのものよ。
この命、
いつでもお前のために捨てようぞ。」
明るい男の声に
胸にすがる指に力がこもった。
「いやっ
いやでございますっ」
朔夜は叫んでいた。
はっと見下ろす神渡の目に
張り裂けんばかりに見開かれた朔夜の眸が
みるみる焦点を失っていった。
朔夜の脳裏に
赤衣の群れが浮かんでいた。
そして
声はよみがえる。
〝お前はおれのものだ〟
赤い殺意を背にその声だけが怯える心を鷲掴みにした。
溶明の中に剣が浮かぶ。
それが神渡に振り下ろされる。
裂けんばかりに見開かれた目が
かくんと力を失った。
すうっと翔がその走りを緩やかにした。
神渡が手綱を操る。
翔は己が選んだ男の望みを知るかのように新たに地を蹴った。
池は静かに水を湛えていた。
神渡が手を差し入れると
その鏡面に広がる波紋が美しい。
お山のふもとにひっそりとある池は澄んでいた。
その水を口に含み
神渡は口づける。
コクリと小さく喉が鳴る。
神渡は深く吐息をついた。
天から授かりし月の精は、
この水面ほどに揺れやすい。
広がった波紋のさざめきが消えた池は
畔の二人を映して静かだった。
唇に差した紅が
与えた水に濡れている。
そっと指先で拭うてやると
神渡は華奢な体をそっと胸に抱き寄せた。
さらさらと流れる黒髪が
白き女衣の綺羅に映える。
細腰は女のものではない。
しなやかに伸びる四肢もそうだ。
地を蹴って宙を舞う姿は
天女とも見えたが、
一分の狂いもなく筋骨隆々とした赤衣たちを倒していった。
そなたは強いな
見事であった
そして、
それは己ゆえなのだ。
神渡はそれを思う。
「目を開けておくれ
神渡はそなたの眸を見たい。」
神渡は
その耳に囁く。
そして
その頬に手を添えた。
まぶたが震える。
神渡の願いに応えて
睫毛が
傾きかけた日を受けて眩しげに瞬く。
「朔夜」
すかさず神渡は迎える。
見上げる眸に力が戻るのを確かめほっとする胸中は
見せなかった。
力が戻れば翳りも戻る。
朔夜の眸が潤んだ。
「我は死なぬ。
お前を残して死ぬことはない。」
神渡の声は労りに優しかった。
かわいそうなことをした。
その思いは真実であった。
「神渡様が亡くなられて
どうして我が生きておられましょう。
どうか………。」
その唇に指を押しあて
神渡は朔夜の眸を覗き込んだ。
「そなたを失うて
我が生きておると思うか?」
息を呑んだ朔夜を
神渡が貫く強さで見つめた。
「思うか?」
その視線から逃げるように
朔夜は身を捩った。
その魂そのままに汚れなき白い衣がわななく。
神渡はしばし
その背を撫でてやった。
待つことはできた。
「どうじゃ?」
だが
答えは必要だった。
岩戸で仕合うた男が浮かぶ。
膝に打ち伏したまま
ごく微かないらえが返った。
「………我は
神渡様のために死にとうございます。」
「許さぬ。」
間髪を入れず神渡は応えた。
ぴたりとその衣の戦慄きが止まった。
神渡の手は
その間もただ静かにその背を撫でていた。
日は傾く。
背にしたお山の影がゆっくりと伸び、
池の端がその山影を映して沈んでいく。
薄赤い色がその影を縁取るのを見つめながら
神渡は口を開いた。
「我が間違うていた。
我がそなたを泣かせたな。
そなたを失って生きるなど
我にはできぬのだ。
であれば、
そなたもそうなのであろう。
心ないことを申した。
朔夜
許してくれるか。」
そっと手を添えると
朔夜はおずおずと身を返した。
背けた頬に光るものがあった。
山の端は赤く染まり
池の面はその空を写す。
その赤に挑むように
神渡は朔夜の濡れた頬にもう一方の手を添えた。
斜陽に照らされながら仰向くその顔に
神渡は低く呻いた。
こんなにも………。
その涙が己を刺し貫く。
言の葉はもう無用であった。
重ねた唇が熱い吐息を洩らす。
二人あって一つの影が赤く燃え立つ色に染まった。
「遠出をした。
遅うなってすまなんだな。」
いつもの長の言葉に
館の者たちはほっとしたように甲斐甲斐しく立ち働き、
二人の膳を置くと
それぞれ里に帰っていった。
姫は昨夜から可知の家に移ったのだろうと納得しているらしい。
「姫様は
ご不自由ではないのかのう。」
「いやあ
何でもご自分でなさるお方だから
耳殿の家の方が困っておるじゃろうよ。」
そんな会話が朔夜の耳にも入った。
膳を前にそっと朔夜は囁いた。
〝姫様は明日には
鷲羽に戻ると仰せでした。〟
〝わかった。
では、
今宵は二人だけだな。〟
神渡は微笑み
すっと身を寄せると
朔夜の耳に囁き返した。
燭の仄灯りに照らされた
朔夜の頬が染まる。
その色を愛でながら神渡は思う。
明日には動き出す。
興津が動く。
どう動くとも道はすでに定まっていた。
「朔夜、
我にはそなただけじゃ。
忘るるなよ。」
神渡は膳の前に姿勢を正し、
上気した己の頬に羞じらう朔夜に
優しく語りかけた。
イメージ画はwithニャンコさんに
描いていただきました。
ありがとうございます。
☆プロローグが後になりました。
すみません。
始めてからこれがないと進めぬことに気づき
書き足しました。