この小説は純粋な創作です。
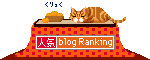
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
はるか はるか
日は照らす
たかく たかく
月はある
たまは こう
たまは こう
日ありて 月あり
月ありて 天は日をかかげる
月が昇った。
その面を雲が流れる。
里は闇に沈みひそとも動かぬ。
鷲羽の館を頂く丘もまた
闇に沈んでいた。
ひたひた ひたひたと近づく二つの足音に
深水は静かに床に直った。
トントンと格子を叩く音はひそやかで
夜鳴く鳥どもの羽音に紛れ
臣の宅が並ぶ丘の中腹に灯火の点る気配はない。
深水は立った。
引き戸にかけた手を引けば
内と外の闇は溶け合う。
闇が流れ込むように二つの影は戸を過ぎる。
深水は引き戸を閉じて、
先に立った。
竈の燠火に手燭を灯し
深水は声を発することなく
居室へと進んだ。
歩き慣れた廊に三つの足音が響く。
その戸を開け
そして閉め
深水は振り向いた。
たづは可知の肩を抱き、
強い眼差しで深水に訴えていた。
可知の眸は洞となっていた。
「可知をお願いしたいのです。
深水殿。」
深水は答えず
手燭の火を燭台に移した。
可知はすたすたと火に寄り
とすんと胡座をかいた。
そのように近々と火に顔が寄っては熱かろうに、
耳となったときの可知は
すべての感覚を失ったかのように動かないのだ。
可知は耳となった。
深水は円座を己の前に置き、
たづに進めた。
「何をお尋ねになりました?」
訳知り顔の深水に、
ここに来たことの正しさは知れた。
たづはほっとしたように
座についた。
「長と巫の歌を。
長は巫一人と契ると歌うと言っておりましたので、
その歌を歌っておくれと申しました。」
やはり、
と言うように、
深水は頷く。
「そして?」
促す。
「口を開きました。
そして、閉じました。
どうしたの?
と尋ねましたが答えません。
目が動かないことに気づきました。
母者に見せたくありませんでした。
深水殿を頼ると決めました。」
「正しく動いてくださいました。
まだ歌ってはならぬものだった。
それだけです。
何度かありました。
歌ってかまわぬ歌を問えば
戻ります。」
深水は
可知を振り返る。
いたずらもののやんちゃ坊主が
凍りついたように動かない。
この童子の命も営みも
〝耳〟の定めの前には塵に等しいのか。
深水は
幼い可知が負う〝耳〟は、
その父や祖父が務めた耳とは訳が違った。
今、
日と月は逢うた。
互いに恋うた。
そして契ったのだ。
その時を知るかのごとく
勾玉は可知から声を奪って待った。
小さな頭に細っこい体、
八歳になった五歳の幼子の
ようやくふっくらしてきた頬が深水を責める。
母は取り戻した我が子を
一心にいとしんでいた。
深水も
たづ同様に
可知に問うてきた。
日の長は、
天の定めた道を行かねばならぬ。
〝耳〟はその道を示す。
だから深水は続けねばならなかった。
たづ同様に。
深水は
向き直った。
「が、
その前にお聞きしたい。
興津の姫………。」
「たづとお呼びください。
興津の者ではございません。
鷲羽の民となりました。」
たづは遮った。
ひどく生真面目な声である。
引き締まる顔に灯火が陰影を添え、
決意の固さを物語る。
「分かりました。
たづ殿、
興津の名をお捨てになったお覚悟、
鷲羽の臣として
ありがたく思います。
が、
危うくはございませんか?」
「危ういとは?」
「日を戴くものは
世に二つあってはならぬ。
それも
拮抗する力をもつものとなれば
争いの種。
朝廷とのいざこざは鷲羽の望むものではございません。
興津の姫、
興津はいかがかな?」
聞いておきたかった。
可知の動かぬ小さな体を目の端に見ながら、
深水は踏み込んだ。
黒猫はいない。
あの者も探っている。
今、
このとき、
何をつかめるかが鷲羽の命運を分けるのだ。
たづは、
目を伏せた。
身にまとうものは鷲羽の民が織り上げた素朴な貫頭衣だった。
その髪を結わえる細布の光沢が際立つ。
その指先が興津の織を確かめるようにその細布を撫でた。
そして、
すっと布を引く。
みどりの黒髪はその肩に広がり、
姫の眸は真っ直ぐに深水をとらえた。
「父とは別れて参りました。
此度の支度は
餞とお思いください。
興津の支度を
どう使うか
鷲羽のため力を尽くせばよいこと。
その覚悟もなく、
川を渡りはいたしませぬ。
深水様の御覚悟は?」
〝いい子は
必ず役に立つのよ。
言ったでしょ?〟
深水は
黒猫の皮肉な声が
聞こえたように思った。
目の前で己を見返して揺らがぬ乙女が
〝いい子〟か。
お前は本当に気楽だな。
「深水様」
いい子の声に
深水は呼び返された。
たづの眸がいら立ちに不穏な炎を揺らめかせていた。
「読めぬことに揺れるより、
今は
可知をお願いします。
このような姿、
いつまでさせておくおつもりですかっ」
可知がいた。
たづの眸を揺らめかせたは
可知の前の燭であったかと深水ははっとする。
耳となって朔夜を導く己が嬉しくてたまらぬ少年は、
いつも元気いっぱいだった。
その彼が〝耳〟のままに動きを止めていた。
深水は
あわてて動いた。
衣の裾に蹴躓いて、
踏みとどまる。
〝耳〟はいた。
深水は
たづをもう一度見返る。
良心に似たものが三十を越えた男の胸をちくりと刺す。
だが、
もう始まったことだ。
深水は
静かに〝耳〟の前に額づいた。
「耳よ
興津より来た姫は
鷲羽の臣 深水に 何と言われたか。
我に語れ。」
己が身を起こせば、
〝告げ〟は始まる。
始まると念じて深水はすっと身を起こした。
小さな頭からぼうぼうと逆立つ蓬髪が揺れる。
その顔がくるっと深水を向いた。
〝鷲羽の民が知ることではございません。
興津は………………〟
子どもの喉から出ると思えぬ
鈴を振るような女声が
生き生きと甦る。
たづが
目を見開いて可知の顔に見入る。
空ろな眸、
動かぬ眉、
唇だけがぱくぱくと動き続けている。
告げのとき、
〝耳〟は〝口〟になるのだ。
やはり聞いていた。
そして、繰り返す。
「あれえ?
深水さま、
どうしたの?」
そして、
戻るのだ。
「あつっ………何だよ、
灯りなんて贅沢だぞ。」
蓬髪頭がころころと床を転げる。
と思ったら
ピョコンと跳ね起きて
深水に突進してきた。
「まーた
何か
おいらに聞いてたの?
ほんとにさあ
深水さまってしつこいよ。
母ちゃんが嫌がるんだからさー。」
膝に飛び乗って甘えながら言っている段階で、
喜んでいるのが見える。
「お前に聞いてもらいたいことがあったのさ。
たづ様のお覚悟だ。
お前の口から語ってももらった。
格別であったぞ。
お前は声音までそのままに語った。
驚いた。
さすがは〝耳〟だな。」
頭を撫でてやると、
可知は
ようやくたづに気づいた。
「姫様だあ………あれ?
どうしたの?」
たづが
涙ぐんだ眦をさっと振り払った。
「なんでもないの。
すごいのね、可知。
あなたはすごい。
驚きました。
特別な 特別な子
天がつかわした子なのだと
よく分かりました。」
「まだ口にできぬ歌があるようです。
長と巫にまつわる歌は
みなそうです。
口は開く。
が、
歌いません。
たづ殿、
それをどう読み解きます?」
大好きな姫に誉められて
すっかり舞い上がった可知が
真っ赤になって照れているのを抱っこしたまま、
深水は問う。
まだ
可知の不思議に呑まれているたづは、
訝しげに小首を傾げた。
初めて年相応の顔を見せるたづに
深水はほろ苦く微笑みかける。
そして、
腕の中の上気した顔を覗き込んだ。
「可知、
前にも問うたが、
今一度聞かせてくれ。
お前が〝耳〟になると、
母は悲しむ。
神の声も鷲羽の口伝も
大事な可知に比べたら母には
塵にも等しい。
お前はつらくはないか?」
可知は
頬を膨らませた。
「母ちゃんは
わかってないんだ。
おいらは
月様の一の家来なんだぜ。
月様のために
天がおいらを選んでくださったんだ。
何がつらいのさ。
おいらはうれしいよ。
月様はほんものさ。
おいらは長が間違わないよう
歌うんだ。
おいらは月様が舞えるよう
歌うんだ。
だから、
おいらの中に、
たくさん歌が詰まってるんだろ?
ちゃんと天の詔をお伝えしなくちゃ。」
八歳の童に迷いはない。
深水は
思わず笑えてきた。
黒猫は
何と言うだろう。
〝子どもは正直なの。
ほんとのことしか言わないんだから〟
とでも言いそうだ。
「そうだな。
そうとも。
お前の歌は
いまだ来ぬものを歌う。
天の意は定まっておるのだ。
日と月が契った。
天地開闢以来のことであろうよ。
我らはお二人の光を守るのみじゃ。」
深水は可知の小さな体を
揺すりあげた。
百戦錬磨の武将でもある深水の腕が
軽々と可知を持ち上げる。
「そうさ
深水さま、
おいらたちは
鷲羽だもん。
あっ 姫さまもねっ」
可知は
すっかりはしゃいでいる。
たづは微笑んで
可知を抱く深水の前に座を進めた。
三人は
小さな灯火を囲むように
顔を寄せあった。
「可知
お前が〝耳〟になるとき、
お前は消える。
が、
消えたお前が〝口〟となって伝えてくれる言の葉、
ありがたく、
ありがたく思うておる。
可知のおかげじゃ。
そう思うておる。
その言の葉けっして仇や疎かにはせぬ。
我も力を尽くす。」
「可知、
わたくしは見ました、
天の意を。
その意に従うのです。
鷲羽の民となることも、
また天の意。
わたくしを信じてくれますか?」
たづは
幼い耳に
真摯に問うた。
美しい頬が紅潮している。
それは燭の炎の色だけではなかった。
「信じるよっ
おいら 姫さまを信じる!」
「我は半分とお思いください。
ですが、
お言葉は信じます。
うそのないお方だ。
そう思うております。」
鷲羽の臣を束ねる男と鷲羽の幼き耳は、
ほぼ同時に答えた。
可知は威勢よく、
深水は口早に。
「けちだなあ、
半分って何だよー。」
可知は
また頬を膨らませる。
たづは華やかに笑った。
「よいのです。
言葉は信じてくださる。
半分は、
わたくしの負うもののこと。
深水殿、
それを承知で信じてくださること、
ありがたく思います。」
たづの言葉に
可知が
不承不承従うが、
座った深水の膝で頬は膨らんだままだ。
「深水殿は、
わたくしの名にも、
姿にも、
惑わされてはくださらない。
それが頼もしいお方なのですよ。」
「おいらだって
まどわされてなんかいないよっ
姫はね、
えっと、
魂がキレイなんだ。」
にっこり
ありがとうと可知の頭を撫で、
たづは艶やかな目を深水へと流した。
「で、
深水殿は、
なぜ惑わぬのです?」
いささか艶めきすぎるな
と思いつつ、
深水は答えた。
「女性はこわいものだと思うようになりました。
そのお陰かと思います。」
「あっ 黒さん!
黒さんのことだあ。
そうでしょ?
ねえ そうでしょ?
深水さま
ぜんぜん勝てないもんねっ。」
黒さんはね、
と可知は語り出す。
その生意気な口を縫ってやりたい気にもなったが、
この際そういうことにしておくのが上策と上機嫌になった可知と
その相手をするたづを眺める深水だった。
半分でよいのだ。
鷲羽に飛び込むにあたって
その父との間に
どんな約定があったのかはわからない。
その半分のたるみがあって自由に動ける幅も生まれる。
黒は都だ。
たとえば、
今それを伝えぬのも自由だ。
ほうと吐息が出る。
まことに女はこわい。
深水は〝ぜんぜん勝てない〟黒猫を思った。
〝ちょっと
子どもはとっくに寝る時間よ〟
黒が呆れたようにずけずけ言うのが
聞こえてくる。
深水はコホンと咳払いした。
「もう
お戻りください。
くれぐれも悟られぬよう。
このような夜半、
姫が我が屋をお訪ねとあっては
いろいろとうるそうございます。」
「深水さま、
送ってくれないの?」
「人目に触れては言い訳も立たぬからな。」
この姫に限っては無用のことだ。
万が一襲いかかる賊あれば、
その賊が気の毒というくらいだろう。
という本音は可知の手前
言わずにおいた。
はしゃぐ幼子を優しく嗜め、
来たときと同じくヒタヒタと去るたづを見送り、
深水は空を見上げた。
月は見えない。
深水の知る女たちは
夜闇など何ほどのものでもない。
その闇の深さを味方にする。
大したものだ。
もう一度
深い吐息をもらし、
深水は引き戸を閉じた。
イメージ画はwithニャンコさんに
描いていただきました。
ありがとうございます。
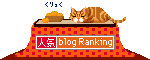
人気ブログランキング
