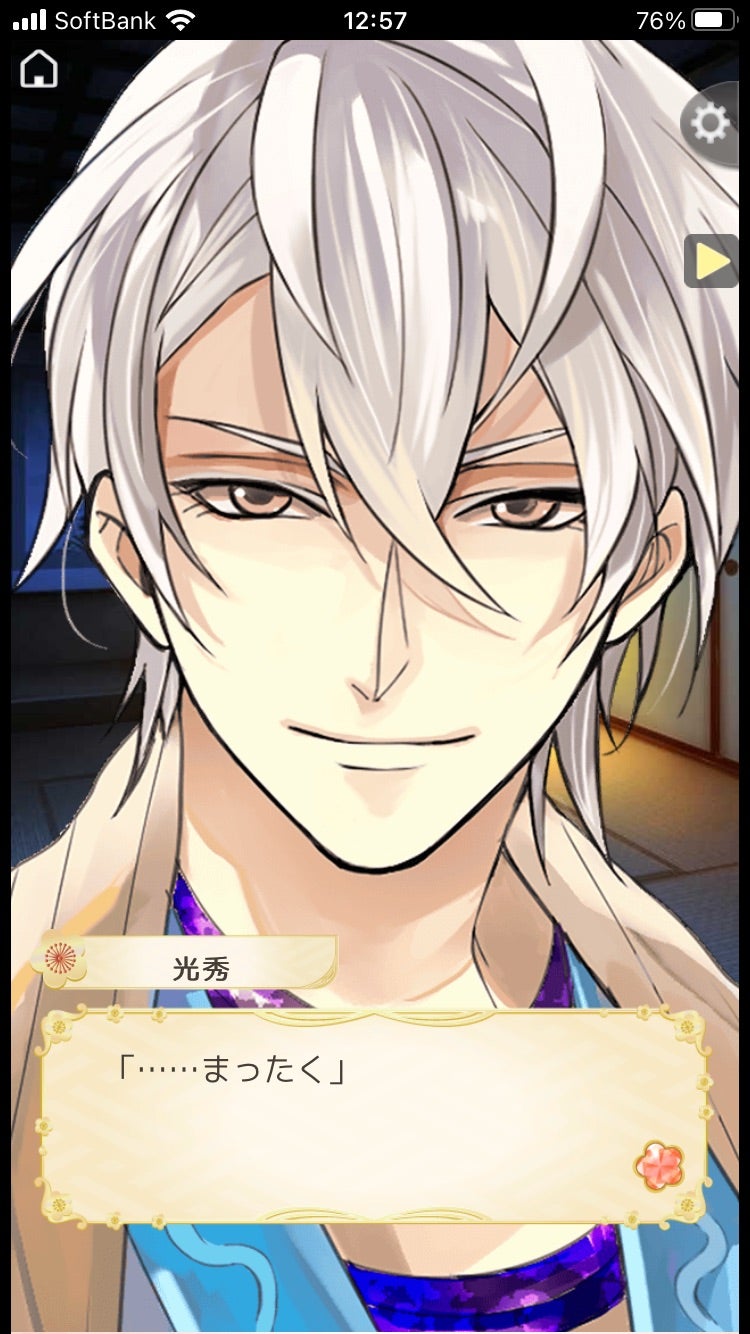(さすがに少し冷えるな・・・・・・でも、おかげで眠くない)
夜明け前------私は光秀さんの御殿の門前で、光秀さんを待っていた。空が薄暗くなってきた頃、待ち人の姿が道の向こうに見える。
(帰ってきた・・・・・・!)
光秀「・・・・・・ゆう?」
光秀さんは私の姿を認めるなり、目を見開いた。
「おかえりなさい」
光秀「・・・・・・」
光秀さんは少し早足になって近づくと、さっと私の手を取った。
光秀「・・・・冷たい。まさか夜通し待っていたのか」
「はい」
光秀「なぜそんなことをした、馬鹿娘」
珍しく怒った様子の光秀さんの身なりを確認する。
(あ・・・・・・やっぱり)
着物には、血の痕が点々とついていた。
(ここで待っていて、正解だった)
光秀「・・・・・・!」
光秀さんは私の視線に気づいた様子で、はっと息を呑んだ。
「それを秘密にするために、水浴びをして着替えて部屋へ来るつもりだったんでしょう」
光秀「それを暴くために、ここへずっと居たのか」
「半分正解です。もう半分は、疲れて帰ってきたあなたを寝顔ではなくて、笑顔で迎えたかったから」
(疲れや苦しみまで完璧にかくしてしまわれる前に、寄り添いたかったから)
「・・・・・・怪我はないですか?」
光秀「ああ」
光秀さんは表情を変えないまま、静かに問い返した。
光秀「なぜ血がついているかは、聞かないのか」
(『なぜ』・・・・・・それは確かに、気にはなる。でも、私がここで待っていたのは、問い詰めるためじゃない)
「私にとって大事なのは・・・・なぜ、ではなくて、今、目の前のあなたが、どういう気持ちでいるか、です」
光秀さんに握られた手に、そっと力を込める。
光秀「・・・・・・お前には、敵わないな」
光秀さんは、きゅっと眉を寄せると、私の手を優しく引いた。
光秀「おいで、秘密を明かそう」
部屋へ入るなり、光秀さんは私に羽織をかけ、
火鉢のそばへ座らせた。
(そんなに冷えてないのに・・・・・・)
優しさが嬉しくて、光秀さんの香が香る羽織の前をきゅっと引き合わせる。
「あの・・・・話したくなければ本当に、ひみつのままでいいんですよ」
光秀「・・・・・・いや。この血の痕を見せた以上、何も語らずには、お前を抱けない」
光秀さんは私の前へ腰を下ろすと、背筋を伸ばして話し始めた。
光秀「結論から話そう。お前が近頃親しくしていた女中は、間者だった」
「やっぱりそうだったんですね」
覚悟していたこととは言え、言葉にされると胸がつきんと痛んだ。
光秀「彼女は、『会談に来る大名が、実は謀反を企てている』という嘘の情報をこの、巾着の中に忍ばせていた」
光秀さんは懐から巾着を取り出して見せた。
(そうだったんだ・・・・・・)
光秀「この嘘の情報を信長様に伝え、そして実際に会談の場を襲うことで、信長様と大名との、内部分裂を図った者がいたというわけだ」
「でも・・・・・・どうして、私づてに?」
(信長様を騙したいなら、直接手渡してもよかったはず・・・・・・)
光秀「巾着に忍ばせた文は、送り主の名が『ゆう』となっていた」
「え・・・・・・私が書いたことになっていた、ってこと、ですか?どうして?」
光秀「嘘の情報だと、後々知れた時のためだ。巾着にお前があとから文を入れたのだと、お前に罪を着せ、言い逃れるために」
「・・・・・・っ!」
みつひで「あの女中は、最初から、お前を利用するつもりで近づいた・・・・・・お前の優しさにほだされ、最後は躊躇していたようだったがな」
(くずりちゃん・・・・・・)
光秀さんが、私の頬へそっと触れた。慈しむように優しく、何度も指先が頬を滑る。
光秀「ゆう・・・・・・」
「・・・・・・はい」
光秀「それらを知らせれば、お前が悲しむのはわかっていた・・・・・・それだけではない。お前が悲しむとわかっていて、女中も、その仲間も・・・・・・然るべき手段え排除した」
悔やむような響きはなく、光秀さんは淡々と告げた。くずりちゃんの愛らしい笑顔を思い出して、胸がずきりと音を立てる。けれど・・・・・・
「そうだったんですね」
私はそっと、光秀さんの手のひらへ手を重ねた。
(本当に、起きて待っていてよかった)
起きていなければ、優しい子の人は、どんな気持ちで私の寝顔を見ていたのか、想像するだけで胸が苦しくなった。
(大丈夫です。隠していたのも、はぐらかしたのも今、私の気持ちを汲んで、隠したかったことをすべて話してくれるのも全部が私のためだって、わかっているから)
「秘密にしようとしてくれて、ありがとうございました」
心からの感謝を込めて、光秀さんを見上げて微笑む。
光秀「・・・・・・」
光秀さんは、にこりともせずに押し黙ってしまった。
「光秀さん・・・・・?」
戸惑って問いかけると、光秀さんの手がゆっくりと頬を離れた。
重ねていた私の手を、光秀さんが確かめるようにぎゅっと握る。
光秀「『俺が今、どんな気持ちでいるか』・・・・・・か」
「え・・・・・・?」
ぐ、と手を引かれて、身体が前のめりに倒れた。広い胸に抱きとめられて、とくりと胸が高鳴る。
光秀「お前のために秘密にしたようなことを言ったが・・・・・・本当は、俺がただ、恐ろしかったのかもしれないな。お前の、優しさが」
(優しさが・・・・・・恐ろしい?)
光秀「この手が血にまみれていようと構わないと飛び込んできたお前を、疑うことはなかったが・・・・・・お前は優しい」
そっと髪を撫でる手が耳元をかすめていく。壊れ物に触れるような手付きに、胸が甘く震える。
光秀「親しい誰かを傷つける様を実際に目の当たりにすれば・・・・・・そんな俺に愛されることを、お前が恐れるんじゃないかと」
「そんなことは・・・・・・っ」
否定しようとする私の唇を、光秀さんの指先が封じる。
光秀「今回は、信長様を守るためという大義名分があった。だが、それがなくともお前を守るためなら・・・・・・俺はお前の知らぬところで、お前が悲しむような残酷なことを平気でできてしまうだろう」
(光秀さん・・・・・・)
光秀「この胸は、お前が悲しむことには痛んでも、お前の大事な人間のためには痛まない。この愛は、善悪を越えたところにある」
断言する声は、まるで裁きを待っているかのように響いた。
光秀「俺はきっと、それを秘密にしたかった」
「・・・・・・光秀さん」
光秀さんの腕に抱かれたまま、私はまっすぐに見つめ返した。
「その恐れは、杞憂です」
(あなたの愛を、恐れるだなんてありえない)
「光秀さんを愛して、愛されると決めた時点で、綺麗なところも汚れたところも、全部ひっくるめて愛すると覚悟していました」
光秀「ゆう・・・・・・」
そっと、光秀さんの胸に手をあてる。
「それは、光秀さんの過去に限った話じゃありません。これからどれだけ光秀さんが汚れようと、綺麗なところを損なおうと、覆るような覚悟じゃないんです」
光秀「・・・・・・」
「だから、ためらわないで・・・・・・ください。あなたらしく、私を愛することを」
強く強く言い切ると、光秀さんはふっと吐息のような笑いをこぼした。
光秀「・・・・・・まったく」
光秀「俺の愛しい連れ合いは、随分と強くなったものだ」
「あ・・・・・・っ」
つい、と顎を持ち上げて、ようやく光秀さんの唇が柔らかく解けた。それが嬉しくて、私も微笑む。
「・・・・・・あなたに鍛えられたおかげです」
そのまま、ゆっくりと近づいた唇が重なる。あまりにも優しい口づけに、触れたところから蕩けてしまいそうだった。
「ん・・・・・・、あっ・・・・・・」
光秀「口づけひとつで、こんなにやわく蕩けるというのに、この目は肝心な時に、凛として強く俺を見る」
するりと目元をなぞられて、それすら甘い刺激になって背が震える。
光秀「ひょっとすると、この目だけかもしれんな」
「何が、ですか?」
光秀「俺の秘密を、洗いざらい吐かせてしまえるものがだ」
ちゅ、と目の端へ口づけられて、くすぐったさに目を閉じる。
「洗いざらい吐かせたりなんて、しませんよ。あなたの抱える秘密は、愛に溢れてる。だから私に明かしてくれようとくれまいと、どちらでもいいんです。その愛が、はたから見て正しいか間違っているかだって、私にはどうでもいいことです。私は、あなたに愛されて嬉しい」
光秀「ゆう・・・・・・」
「愛しています、あなたが抱える秘密も、全部」
言い終わるより前に、吐息ごと飲み込まれるように唇を奪われた。
「あ、・・・・・・んっ」
肌を暴く手は、いつもどおり焦らすように穏やかなのに、口づけだけは、脳髄を蕩かすように激しい。
光秀「寝ずに待っていてくれた連れ合いに、酷なことを言っても?」
「あ、ん・・・・・・なん、ですか・・・・・・?」
光秀「お前が眠れるのは、もう少し先になりそうだ」
悪戯に笑った黄金色の瞳に、身体の奥がとろりと溶け出すのを感じた------