仕事変えず地方に「テレワーク移住者」決断の理由・悩みは?
配信
新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークが普及する中、仕事を変えないまま、都心などから周辺の県に移り住む「テレワーク移住」の動きが出ています。新たな生活を楽しむ人たちなどを取材しました。 ◇ 東京のターミナル駅、新宿駅構内の大型ビジョンに、岐阜県の移住生活の魅力を伝えるPR動画が映し出されていました。 今週から期間限定で流れていて、
「岐阜県」移住者が、自然を楽しみながら生活や仕事している様子などを紹介しています。
動画を見た通行客 「風景とか映像とかみると、やっぱり行きたくなります。(移住を)考えちゃいます」 新宿駅で初めて行った岐阜県の試み。その狙いとは… 岐阜県地域振興課移住定住係 長屋透主査 「在宅勤務が進展してきたことで、仕事を変えずに住む場所を変えることが可能となっているので、これをチャンスというか (PRの)契機にとらえまして」 岐阜県が狙うのは、
転職せずに移住する「テレワーク移住者」。移住をめぐっては、次のようなデータが。
先週、総務省が公表した統計によると、去年、に東京23区から転出した人が、転入した人をおよそ1万5000人上回りました。比較可能な2014年以降で初めての転出超過です。 それとは逆に、初めて転入者が転出者数を上回った茨城県。西部にある境町は、年々、移住者が増えています。 その境町に去年、埼玉県戸田市から移り住んだ池田さんは── 埼玉・戸田市から移住 池田さん(33) 「妻もリモートで仕事していたので、『都内でこだわる必要がないよね』って(移住した)」 「テレワーク移住者」となった池田さんは、都内の電機メーカーに勤務。職場には、時々、出社するといいますが── 池田さん 「高速バスがあれば、だいたい済んでしまうので、通勤が増えても、まだ許容範囲かなという距離と思っている」
境町には電車の駅はありませんが、去年から東京駅への直行バスが開通しています。
関東鉄道 バス運転手 「サラリーマンの方もいるし、若い方、買い物に行ったりする人もいます。『助かる』という声は何人かから聞いたことがあります」 バスで直行できることも、「テレワーク移住」の後押しになっているようです。 ◇ 神奈川・逗子市から長野・佐久市に移り住んだ伊藤さんも「テレワーク移住者」です。 神奈川県から移住 伊藤侑果さん(31) 「(コロナ禍で)商談などもリモートでオッケーだよ、というふうな格好になり、『どこでも生活できるぞ!!』というところで、息子も生まれるし、子育てしやすい環境をというところが一番のきっかけになっている」
個人でWEBコンサルの仕事をする伊藤さんは、去年、移住を決断。一方、悩みも──
伊藤さん 「最低気温マイナス10℃という世界なんですけど、エアコンはほとんどきかないので、石油ストーブを併用したりするんですけど、そうなってくるとお金がかかってくる」
寒い地域ならではの問題もあるといいます。 佐久市移住交流推進課 荻原あゆみ課長 「都会からの仕事を、そのまま引き継いで持ってくるというのは、移住に関してはハードルが低くなります。田舎ならではのデメリットもありますので、そういうことも、しっかりこちらの方から説明しながら、失敗のない移住にしてもらいたい」 佐久市では「テレワーク移住者」などを対象に資金援助などを行っているということです。
地方の環境整備が進むに従い、今後もテレワーク移住が広がりそうです。
>テレワークで移住だとトレンドになって、
なんと今年は初の転入超過になった県が3つもあったそうだ!!
それは素晴らしい。大成果。で、、その三県って言うのが、群馬、茨城、山梨…。
結果全部関東圏。これで田舎にも光がさしたと思ったら大間違い。
今年10都府県が転入超過だったが、その内7都県が栃木以外の関東と山梨。
つまり関東の中で人が移動して内輪の共栄圏が出来ただけ。
水戸や甲府や高崎が救われるかもしれないが、秋田や松江が恩恵を受けるのは不可能。
結局今年の統計が教えてくれたのは、東京通勤圏で無ければテレワークも何もないって事実。
だってさ、呼ばれた時は出社しなきゃいけないからね。
通勤電車のある茨城の取手やつくば、山梨の大月以東なら朝一の出社も可能だが、地方からじゃ無理。
新幹線はでかい駅しか止まらないからね。その駅に行くための電車が1時間に1本なんです…。通勤費用も一日で万単位だ。とても無理
木造+鉄骨のハイブリッド構造オフィスビル建設へ
仙台・広瀬通
河北新報社
七十七銀行グループや日本政策投資銀行(政投銀)などは24日、仙台市青葉区の広瀬通沿いに木造と鉄骨を組み合わせたハイブリッド構造のオフィスビルの建設計画を発表した。両社などが出資して設立した特別目的会社が8月にも着工し、2023年末に完成予定。地域の木材を活用して二酸化炭素(CO2)削減を図り、環境問題への対応を進める企業の入居を狙う。
建物は地上10階(約48メートル)で敷地面積約1250平方メートル、延べ床面積約1万200平方メートル。1階は店舗、2階以上をオフィスとする。総事業費は数十億円規模の見込み。
各階に設けるバルコニーや内装などに木材200立方メートルを使用。通常の資材を使う場合と比べ、約190トンのCO2削減につながるという。新型コロナウイルス対策として、エレベーターや部屋の出入り口に非接触機能なども導入する。
設計・施工は竹中工務店が担う。一部に国の耐火構造の認定を受けた同社開発の耐火集成材「燃エンウッド」を使用。集成材の材料に東北のスギやカラマツを取り入れることで、地域の森林資源循環も図る。
建設主体の合同会社「ウッドライズキャピタル」は20年11月設立。七十七銀と子会社の七十七キャピタル(仙台市)による「77ストラテジック・インベストメントファンド」と政投銀、長谷工コーポレーションが出資する。各社の出資比率と出資額は非公表。
七十七キャピタルの担当者は「今回の投資で(20年7月公表の)SDGs宣言に即した事業に積極的に取り組んでいく」と言う。
オフィスビルの管理・運営は、ウッドライズと契約を結んだみずほ不動産投資顧問が行う。同社の担当者は「全て木造にするとコストがかかるが、一部を木造にすると採算面と環境への配慮が両立できる。
社会的な機運の高まりを期待したい」と話す。
コロナで移住者増続く 田舎暮らしに魅力
若い世代も伸びる/兵庫・丹波市
兵庫県丹波市の移住相談窓口「たんば移充テラス」を介して移住した人が、2021年度12月までで
56世帯115人と、これまで最も多かった昨年度1年間の50世帯101人を上回り、過去最多となっている。
新型コロナをきっかけに、田舎での暮らしに目を向ける人が増えたことが影響しているとみられる。
移住世帯と人数の推移
今年度移住した人のうち、52・1%が40代以下。前の居住地は、県内が22世帯46人で、人数ベースで40%を占める。次に多いのが大阪府の19世帯41人で、35・7%。京都府が5世帯8人、奈良県が3世帯5人、徳島県が2世帯7人など。県内は5世帯11人の西宮市が最多。
昨年度から移住者が急増。定年退職後の田舎暮らし需要が根強い上、40代以下の若い世代の移住者が増加。昨年度は、移住者の64%が40代以下だった。 同窓口を運営する、市移住相談有限責任事業組合によると、今年度は、コロナで減っていた、就学前、学齢期の子どもがいる30代からの相談が回復。リタイア世代と合わせ、相談件数が増えており、12月末で471人、3595件と、前年度(371人、2715件)から大きく伸び、こちらも過去最多を更新中。 今年度、若い世代とつながるため、地域に関わりたい人と地域の人をつなぐマッチングサイト「SMOUT」に登録したことも奏功。同サイト経由での相談が増えた。
相談、移住者とも阪神地区からが多く、京都府からは少ない。阪神地区のうち、神戸市民からの相談の多さが際立って多いものの、移住に結びつく人は少なく、今年度で2世帯5人。 相談から移住まで平均して9カ月かかっており、今年度途中から増え始めた30代らの移住は今年度末から来年度にまたがる見通しという。
移住者増の理由を、同組合の中川ミミさんは、「コロナ以外の要因が見当たらない」と言い、「リタイア世代には、丹波の『いい田舎』イメージが強い。それより若い30、40代は、私達の発信に興味を持ってもらっているんだろう。県内他市町の移住相談担当者と情報交換していても、県北部をのぞいて、移住者の世代は似た感じ」と分析する。若い世代の移住者は、田舎でサラリーマン生活を望む人が多いという。 移住者の増加で、紹介できる物件が減っているのが悩みの種。空き家を売りたい、貸したい人は、市空き家バンク「住まいるバンク」への物件登録を呼び掛けている。 隣の丹波篠山市が開設している「丹波篠山暮らし案内所」でも、今年度は12月末時点で51世帯、132人が移住と、過去最多。昨年度は50世帯、124人だった。
>丹波市です。そう言われたらここ2~3年で近所に家が建ったり空き家に越してくる人がいたり。
こんなド田舎に住もうと思ってくださるだけで嬉しくありがたいです。
でも…田舎になじめるかどうかはその人次第。ご近所と一線を画しておられると地元民からはなかなか近寄りがたく、結果的に孤立してしまう。村人全員と仲良くしてとは言わないけど、2~3人の親しい人を作っておけば田舎なのですぐに人の輪は広がるよ。
祭りや草刈り・寄り合い・子供会などの行事はコロナ禍で今は最小限になってる。
焦らず徐々に村人になってほしいです!
>たまに遊びに行くにはいいとこだよ。でも住むと大変よ。
草刈り、溝掃除、お祭り、土日無くなるで、
>全国組織の高齢者団体の役員をして居ます。 都市部の近郊でも、通院やリハビリ 介護等や日常の所用に
交通の便が悪く交通費が高額に為って居ます。その実情を頻繁に聴いて居ます。
失礼ですが、慣れない地方には良く考えてから移住をして下さい。
地方の行政も、前に居た街と比して行政サービス等が悪いと言っても即時改善等はしないでしょう。
山こそ資源…小水力発電で地域振興なるか
鳥取県若桜町の集落
日本農業新聞
標高260~700メートルにある人口100人の集落が、住民主体による小水力発電事業で地域振興に挑む。
鳥取県若桜町糸白見地区は3月、発電事業の合同会社の設立を予定する。次代に新たな産業をつなぐ狙い。山や川を“資源”として年間1000万円の売電収入を見込み、脱炭素社会へ山間地の産業基盤づくりを目指す。(鈴木健太郎)
試験設置した小水力発電の水車を点検する山根さん(鳥取県若桜町で)
県東部の同町は兵庫・岡山両県の県境に位置する。同町中心部の若桜鉄道若桜駅から車で約10分の所にあるのが糸白見地区。面積は約1300ヘクタールだ。 林業で栄え、300人以上が暮らした集落も、今は約100人。水稲や野菜など基幹産業は農業だが、若者の多くは鳥取市などに職を求める。 人口減少に危機感を覚えた住民が着目したのが小水力発電だ。「何もない村だと思っていたが、山も谷も川も、全てが小水力発電に適した“資源”だと気付いた」と話すのは、糸白見水力発電事業計画実行委員会委員長の山根幹博さん(47)。2019年に60歳以下の住民で構想をまとめ、地区の総会に提案した。 事業のモデルは岐阜県郡上市の石徹白地区。小水力発電で年間約2400万円の売電収入を得て、街灯の無料化や土地改良施設、畦畔(けいはん)の管理など活動に充てている先進地だ。
住民主体で会社 収益1000万円見込む
山根さんらの提案には当初、不安の声が多かった。「農業用水に影響はないのか」「本当にもうかるのか」。合意形成のため、石徹白地区の事業に関わった小水力発電の専門家を招いて勉強会を開くなど説明を重ね、理解を得た。 20年に40~60代の6人で実行委員会を結成し、試験的に農業用水路に発電用の水車を設置。装置の組み立てや設置工事は住民一丸で取り組んだ。
合同会社を設立し、銀行の融資や県の補助事業で本格的な発電施設を建設する。工費は約1億円。県は50年の二酸化炭素(CO2)排出実質ゼロを目標に掲げ、再生可能エネルギー発電事業の支援を充実させている。 固定価格買い取り制度(FIT)の活用などで年間1000万円の売電収入を見込む。
集落には現在5人の小学生がおり、若い世代の将来の雇用創出も目指す。地区や町の事業者に融資もするなど、新たな産業基盤につなげたい考えだ。返済も含め、20年以内の黒字化を計画する。
企業と協力することも考えたが、必要な技術、経営ノウハウを自ら身に付けるため、住民だけで運営することを選んだ。「昔はまきを取れる山村がエネルギーの供給源だった。石油中心の社会になり人、物、金が都市に吸い取られた。エネルギー産業の主役の座を田舎に取り戻したい」と、山根さんは力を込める。
>日本には、川という資源がある
昔から水車を使って加工品を作っていた
水枯れもあるが枯れない地域も多い
重力を使ったシンプルだけど
システムのコストも格安の永遠のシステム
是非利用してほしい
>日本ほど小水力発電に向いている土地は世界中探してもないんじゃない。
日本全国でやればいいけどやりたい自治体だけやればいい、やったもん勝ちになるよ。
>川を塞き止め湛水せず、流水の落差だけで発電出来るなら河川環境は破壊されずに済む。
画像のような小規模な設備を本流ではなく沢に複数設置することで集落の電原かつ売電が可能ならやる価値はありそう。また地元で起業し地元で運営することに意味がある。河川はその昔より人間が生きていく上で火よりも一次的な資源であったはず。その源は当然豊かな山林にある。沢を利用するなら尚のこと山林を荒廃させてはならない。この事業のために自然河川をただのインフラにしないことを祈る。
>千葉県での暴風雨で東京電力が復旧工事に四苦八苦されていましたことが記憶に新しい。
大規模電力開発は一見効率がいい良いようで被害が広範囲に及ぶと回復に手間取り日常生活に支障が多大ですから。
小規模の電力開発は自然災害の多い日本には適してるんじゃないですかね。山間部などは特にそうでしょう。
山・谷に恵まれていますからね。豊富な水量は開発を待っているのではないでしょうか。
「住まい・買い物・医療・防災」一体型で再開発…
安心安全な新しい"まち"誕生
札幌市豊平区平岸エリア
配信
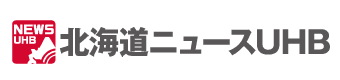
札幌市豊平区平岸で大規模な再開発が行われています。 住まいに買い物、医療に防災まで一体型で進む新たな"まち"の最前線にカメラが入りました。 一つの敷地にマンションと一戸建てエリア。スーパーや家電量販店、そしてクリニックに総合病院も… 住民:「電気店もなかったので便利になった。スーパーも安くて来やすい」 住民:「総合病院などが建つと聞いている。すごく便利になる」 再開発が相次ぐ札幌市で新たに作られる"まち"の形とは…
長谷工 アーベスト 広域販売部 高橋 大樹 部長:「こちらが107世帯のマンションの模型です。10階建ての棟と8階建ての棟になっています。駐車場にはロードヒーティングを採用しています。雪でも車の出し入れが容易にできます。屋上にはソーラーパネルがあります。共用部の照明とかコンセントは災害時(の停電)でも使用できます」 札幌市豊平区平岸の新たな分譲マンション。大雪にも災害にも強いといいます。準備中のモデルルームを特別に見せてもらうと… 長谷工 アーベスト 広域販売部 高橋 大樹 部長:「ちょうど西側に藻岩山を望めるような形になっているので、上層階では眺望が楽しめます」
眼前に広がる景色に四季の変化も感じられます。価格は、中層階の70平方メートルほどの3LDKで3000万円台半ばから後半くらい。1月から始まるモデルルーム見学の予約はほぼ埋まっています。 長谷工アーベスト 広域販売部 高橋 大樹 部長:「商業施設と一体の開発の中でこの価格というのは評価いただけると思う」 三宅 真人 記者:「こちらでは10階建てのマンションが建設中です。このマンションを含めた広大なエリアに病院や商業施設を含めたひとつの"まち"が作られます」
札幌市豊平区平岸。元・自衛隊札幌病院の跡地で大規模な再開発が進んでいます。地下鉄の駅から徒歩10分ほど。周囲には学校も多い便利な地区に作られるこの新しい"まち"の名前は「札幌リードタウン平岸ベース」です。 面積は約4万8000平方メートル。敷地内には、すでにオープンしているスーパーや家電量販店のほか、総合病院やマンション2棟が建設予定で、48区画が整備される戸建て住宅のエリアもあります。
住宅のエリアは、プライバシーや日当たりを守るため、庭や家の向きも決められています。 積水化学工業 住宅カンパニー まちづくり事業推進部 山地 晋二朗 部長:「戸建て街区は『まちなみデザインガイドライン』を設定していて、道路に面して植栽を数多く入れる。シンボルツリーを必ず一本入れるとかルールを定めている」 積水化学工業 住宅カンパニー まちづくり事業推進部 山地 晋二朗 部長:「戸建て街区と病院に挟まれた緑地帯になります。夏は緑地や地域イベントに使えるように、冬は雪の堆積場として使えるようにした」 一体で開発することで住みやすさを目指す"まち"。住宅は主に3タイプから選べるようになっています。すべての家にある設備が…
北海道セキスイハイム 札幌支店 葛西 高行 支店長:「屋上にある太陽光パネルのサンプルです。蓄電池にためて非常用電源として活用出来ます。通常通り使って一晩は越せると思います。こちらの電源を押すと停電状態が作られますが、すぐに電気が復旧し蓄電池から電気が供給されます」 北海道セキスイハイム 札幌支店 葛西 高行 支店長:「実際はもっと早く復旧して、子どもが停電したのに気がつかないぐらいだと(客に)説明しています」 北海道内では、ほぼ全域に及ぶ大規模停電、ブラックアウトの経験があることから、防災にも重点を置いた住宅となっています。
土地は40坪から50坪ほど。2月から販売が始まります。お値段は… 北海道セキスイハイム 札幌支店 葛西 高行 支店長:「土地建物で5000万円半ばから6000万円超える価格帯。太陽光、蓄電池の標準搭載や、敷地内の植樹など、きっと満足いただけると思います」 商業施設や病院が近いだけではない安心安全のまちづくり。エリア全体の完成は、2024年9月を予定しています。
UHB 北海道文化放送
人口激減、住民の半数は高齢者…
なのに若者が次々移住 異彩を放つ町
配信
朝日新聞社
人口が激減し、住民の半数は65歳以上の高齢者なのに、若い世代が次々に転入してくる――。こんな自治体が人口減少が進む山口県内にある。県北東部で日本海に面した阿武町だ。人口3千人のこの町で、起きていることとは。
【写真】地域おこし協力隊員として「無角和牛」の振興に携わる藤尾凛太郎さん=2022年1月25日午後2時8分、山口県阿武町福田上、寺島笑花撮影
潮の香り漂う漁港に近い阿武町奈古浦地区の旧街道沿い。いまは多くが店を閉じているが、昭和期までは呉服屋や貸本屋、病院などが並び、「奈古銀座」と呼ばれていた。
その一角に、町が2018年に設けた暮らし支援センター「shiBano(シバノ)」がある。元薬局の空き店舗を改修した建物で、移住希望者らが住まいや仕事を探す「玄関口」の役割を果たしている。 昨年7月に下関市から移住してきた渋谷英利子さん(44)は利用者の一人だ。菓子づくりを仕事にするのが夢だったが、踏み出せずに悩んでいた。シバノを拠点に活動する集落支援員の吉岡風詩乃さん(31)に相談すると「母親の工房があるよ」。間借りして、菓子づくりと移動販売をしている。 町の手厚い支援も背中を押した。U・Iターンの単身世帯には10万円の奨励金、起業に対しては最大60万円の補助金が出る。渋谷さんは「この町に来てからびっくりするほどいろんなことがするする進んだ」と驚く。 町の人口は20年国勢調査で3055人。5年前から11・8%減少し、65歳以上の高齢者が人口の49・8%を占める。人口減少率、高齢化率とも県全体よりずっと高い。 ところが、近年は転入者が転出者を上回る「社会増」を実現している。総務省統計局のデータを集計すると、18~20年は計17人の転入超過だった。
県内の市町の大半が人口流出に頭を抱える中、異彩を放つ。
■「居場所をつくって一緒に考えてくれると思えた」 町は15年、20~30代の職員を中心に
「阿武町版総合戦略」を策定。多様な働き方の実現に重点を置き、若者世代の移住促進などに力を入れている。 「1/4worksプロジェクト」もその一つ。
基幹産業である農業や漁業の働き手が年々減少し、特に農業は繁忙期の人手不足が深刻だ。そこで苗植えや収穫など、季節ごとの仕事をパッケージ化。空き家や車を用意して、農業に関心のある人や移住を考えている人を受け入れた。
18年からスイカやホウレンソウ農家で実施し、18人が参加。
うち20~40代の男女6人の定住につながった。町は住まいの補助にも力を入れ、空き家の取得に最大30万円、リフォームには最大100万円を出す。
都市部から移住する「地域おこし協力隊」も重要な人材だ。町は19年から3年間で9人を受け入れた。その一人、神奈川県出身の藤尾凛太郎さん(24)は、山口県のみで飼育される「無角和牛」の振興を担う。「大学を卒業したばかりで経験がない自分にも、居場所をつくって一緒に考えてくれると思えた」 社会増が進む阿武町について、県の政策企画課の担当者は「施策が届きやすい小さな町で、総合力の効果が出ているのではないか」とみる。
とは言え、高齢化が進むなか、社会増を上回る人口減少は避けられない。町まちづくり推進課の井上豊美さんは「全国的な人口減の中で人が減るのは仕方ない。いかに町に活力を生み出すか」と話す。
町はこの春、「道の駅阿武町」横の遊休地にキャンプ場をオープンさせる。野菜の収穫や漁業体験を通じて地域にお金が落ちる仕組みを目指している。企画立案に携わる一般社団法人STAGEの田口壽洋代表(43)は「家族を養える仕事がなければ人は住めない。いまここにあるものに光を当てて、出ていくお金を減らし、入るお金を増やすことが必要だ」と言う。
知事選のさなか、県に期待することは何か。井上さんは「町の財源でできることは限られる。県単位で補助事業が広がれば、私たちも動きやすい。県の広域的なキャンペーンを通じて、関心をもってもらうことも重要だ」と話した。(寺島笑花、武井宏之)
>なんだか希望の光が見えたような気がしました。若い人を呼び込んでその人が結婚して
家庭をもっても不安のない生活ができるような金銭的援助や働く場、生活環境の整備をどんどんして 田舎の良さも活かしながら魅力ある街づくりをもっと活性化してほしいな。
過疎が過疎で居続ける理由 地方活性化は本当に必要なのか?|『田舎はいやらしい』
配信
本が好き
2014年9月、第二次改造内閣を発足した安倍元首相は、記者会見の席でローカル・アベノミクスとも言われる「地方創生」を発表した。 地方創生? 物・人・金と、長く東京に一極集中し続けた結果、すっかり斜陽化してしまった地方に活力を取り戻す……と言う掛け声なのだが、そんなたわ言で何かが変わることは無い。
しかし、そんな折に、海の向こうから「黒船」よろしく大変革を余儀なくする新型コロナウィルスが到来した。勢い世論は、「リモート・ワーク」や「在宅勤務」を推奨し、それ以前から高まっていたスローライフなどと相まって、地方移住の機運が高まった。しかし、気運こそ高まったものの、実際は思ったほどの動きは無いように感じる。それならそれで良かった。と、四国出身の私は思う。なぜなら、都会で暮らす人が思うほど、「田舎暮らし」は素敵ではないからだ。
『田舎はいやらしい 地方活性化は本当に必要か?』(光文社新書)の著者は、宅建取引士や1級ファイナンシャルプランニング技能士など多様な資格を有し、自身も戯曲やシナリオを書くなど多才な花房尚作氏。 著者自身の、埼玉県川口市のマンモス校から、鹿児島県の全校生徒50人ほどの小学校に転校し、その後も福岡~アメリカ(ボストン)~東京~過疎地という移住体験をもとに記された、過疎の抱える問題点を浮き彫りにした一冊だ。
私たちはついつい日本人は同じ行動様式で暮らしていると思いがちである。それがじつは違っていた。過疎地域には過疎地域の行動様式があり、都心には都心の行動様式があった。 (中略) 都心で暮らしている者が持つ過疎地域に対する誤った認識。過疎地域で暮らしている者が持つ保守性と閉鎖性に依存するという、行動様式の中の幸せ。この二つの橋渡しとしての役割を果たし、現行の過疎地域対策とは違う選択肢を提示したかった。
本書の冒頭で語られる、著者の本作に対する思いである。
都会から田舎へと移転した著者とは逆の形でだが、同じく田舎暮らしの「良さ」と「悪さ」を十二分に経験している私にもこれはその通りだと思えた。方言が持つ独特のイントネーションとニュアンス。仕事に対するスピード感。祭りや行事に現れる風俗・風習。「勝ち・負け」の概念。などなど、事々に都会と田舎(過疎地)では異なる。それらをひとくくりにして、永田町や霞が関の論理で対策するなど、無理というより無茶というものだ。
一口に地方といっても、県庁所在地のように交通の便が整っている地域もあれば、陸の孤島になっている地域もある。過疎地域の中にも都市に近い場所に位置する過疎地域もあれば、都市から遠く離れている過疎地域もある。都市から遠く離れている過疎地域の中にも山村や漁村、離島もあり、それぞれ置かれている状況が違う。それらをすべてまとめて「地域の活性化は正しい」と論じてしまって本当によいのだろうか。過疎地域の活性化は本当によいことで、過疎地域が衰えるのは本当に悪いことなのだろうか。
高校進学を控えたある日の夕方。夕日に紅く染まった教室で、クラスメートの何人かと、将来の夢を語り合った。青春の1ページを彩る一コマである。そしていち早く都会を目指した私は、帰省する都度、あの日語らった仲間に上京を強く勧めた。私に勧められたからではないだろうが、出てきた者もいれば出ず仕舞いで終わった者もいる。そして、出てきた者も、私を除く全員が今は郷里で過ごしている。それぞれの事情があり、選択肢がある。
様々なわけを知る間柄だからこそ勧めた上京のつもりなのだが、彼には彼の、いかんともし難い事情というか思い・性分があったのだ。 本書には、著者が行った様々なインタビューが紹介されている。そんな中から、鹿児島県曾於(そお)市役所企画課の職員にしたものを一つ。
Q 「曽於市は寂れていく一方ですね」
A 「そうなりますね」
Q 「いずれ曽於市は立ち行かなくなりますよね」
A 「そうですね」 Q 「何か対策のようなものはありますか」
A 「う~ん、ないですね」
Q 「たしかにやりようがねいですよね」
A 「そうですね」
Q 「私も曽於市に住んでいるので分かります」
「インタビューになっていない」とのご指摘があるかもしれないが、過疎地域の人々が持つ雰囲気はよく表れている。(中略) なぜなら過疎地域がいくら廃れても、職員の収入は中央政府が保証しており、現状維持で何ら問題がないのである。
問題意識そのものがなく、むしろ問題にされることが問題意識として認識される。
たしかにこのインタビューは、過疎地域の行政との不毛なやり取りをよく表している。
私が40代半ばで帰省した際にも、同じような感覚を味わった。
それは、県下でも有名な高齢者ばかりが暮らす過疎地域の活性化に対するディスカッションとプレゼンテーションに招かれた時のこと。担当課長以下数名の課員と地元商工会や青年会の面々と、私たちプレゼンサイドの12名ほどが、およそ2時間に及ぶ会議を3度繰り返した。
今思っても悪くないプランをプレゼンし、彼らも相当食いついていたように記憶している。
市内から1時間半ほどの山間の町まで出向いた私には、「お車代」と称する謝礼が振り込まれた。 しかし、待てど暮らせど何らの返答もいただけない。業を煮やして、同行した地元代理店に問い合わせてみると、「あれはもう終わってると思いますよ」とすげない返事をいただいた。
後日、同じく地元市役所に勤める友人に聞いてみると、
「ディスカッションしたという事実だけが欲しかったんだよ」 と教えられた。
要は、自分たちでは思いもつかなかった新規事業を始めるよりも、
役所として「地域活性化」に取り組んでいるという事実だけが必要なのだ。
そして、この三度に渡る会議の議事録は、彼ら役所の活動履歴として上申して完了するのだ。
冷徹な市場原理の中で生きてきた都会生活者にとって、これほどのギャップは想像の域を超えていた。本書の中には、同じく意識レベルのギャップに慄く著者の姿がいたるところに浮き上がってくる。 本当の意味での活性化は、そこで暮らしている人びとが楽しむことで生まれる。小さな楽しみの積み重ねが生き生きとした生活につながる。そこに意識の高さや競争といったものは不要なのではないだろうか。
私も都心で暮らしていた頃は、過疎地域の活性化は正論だと考えていた。過疎地域の発展は地域の人びとの幸せにつながると信じていた。活気のある町がよい町であり、寂れた町はよくない町だと思い込んでいた。なぜなら、過疎地域の人びとは、都市で暮らす人びととは全く違う価値観の中で暮らしていたからだ。
そこには変わらないことを望む人びとの姿があった。何一つ変わることなく、どこにも飛び立たず、廃れ、寂れ、衰えていくことを望む人びとの姿があった。(中略)
中央政府は、過疎地域の活性化を止めて、過疎地域のゆるやかな後退を目指してはどうだろうか。そのような選択肢があってもよいのではないだろうか。 「地方創生」「地域活性化」などなど、いい加減、その手の謳い国民を惑わすのは止めて欲しい。
『田舎はいやらしい 地域活性化は本当に必要か?』(光文社新書)は、常日頃、永田町に憤りを感じ、ましてや著者と同じく、田舎のいやらしい部分をよく知る者も唸らせる鋭い考察が記されている。是非とも、過疎化を懸念する地域に住まう方々に読んでいただきたい一冊だ。
文/森健次
まあ、だからこそ、やる気のある人ほど進学して都市部に出て行き、
行動したくない人ばかりが選別されて残る、活力のない地域が生まれて
何かやる人がいても、笛吹けど踊らずの周囲に埋没していくしかなくなるのだ。
他の条件がいくら良くても、結局はそこの住民次第なわけだろう。
やるところは、もう十数年も前から動こうとして動いてきたから、今、成果をみせているわけで、
今もって何もしようとしないところは、とにかく活力ある人が少ないのだから、どうしようもない。
役所は色々な案内やパンフレットを印刷するだけして、用がなくなるまで、
誰も見ない役所や施設の入り口に積み上げてあるだけ。
誰に見せようと言う気もないまま、予算だけが執行されて、発注先の印刷屋さんが仕事ができる。それだけだ。
空き家だらけのエリアはそのまま放置されている。
しかし、ポツリポツリと、家の建て替えをしている様子とか
何かを始める人もいる。ただ、住民はそれについて行かないような人ばかりだと、
やってみただけ、で終わる。
>困った事に、過疎地域の大多数の老人達が
変化を望まないのは事実である
若者は生まれてから自身の成人式まで人口推移が減り続けて居るなら
故郷を見捨てて他の場所に移住した方が良い
あなたが生まれて成人するまで人口が減り続けているなら
老人達が行政改革を行う可能性の欠片も無いからだ
市議会議員の数や給料が町の人口や税収により変動するなら
市議員の待遇に直結するからもっと違った結果だったね
>過疎自治体が緩やかに人口が減っていってやがて自然消滅、なら別に悪い事ではないと思う現在日本は人口減少社会なのだからそれが自然な姿
どんどん社会を支える人口が減っていくのだから、住む場所をなるべく集中させて
効率良くインフラを整備しなければ財政が立ち行かなくなってしまう
そりゃどんどん人口が増えて過疎自治体に流入し活性化、となれば理想だけどほぼ実現不可能な理想を掲げても始まらない
地方創生といっても、もう手の施し様のない過疎自治体を再生させようとするより、他のまだ何とか再生の目もある自治体への移住を推進して力を合わせる方が現実的だと思う
>「地方が廃れたのは仕事がないから」「買い物やサービスなどが都会より見劣りするから」というような金銭的、物質的な面をテコ入れすることが地方活性化と誤解されているが、
他にも既得利権や閉鎖性、身分差別やムラ社会など
精神的に暮らしにくいというところにつける薬は無いのです。
>私も地方の県庁所在地の郊外出身(今は過疎地域で母校の小学校も統合でなくなりました)、親の実家は今限界集落だけど、過疎地域はいつまでたっても人権とかプライバシーとかの意識が希薄で、独特の陰湿さがあった。
建築家が「日本の大規模再開発は恐ろしい」と警鐘を鳴らす深い理由

井上 章一,青木 淳
プレジデント・オンライン東京の街並みはどのようにして今の風景になったのか。その背景には、ヨーロッパとは違う日本ならではの建築の歴史があった。国際日本文化研究センター所長の井上章一さんと建築家の青木淳さんの対談をお届けしよう――。
※本稿は、井上章一・青木淳『イケズな東京 150年の良い遺産、ダメな遺産』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
「外観は公共のもの」という考え方
――コロナ禍に見出すポジティブな面ということでいうと、日本は「自粛の要請」というかたちで中国や欧米のように都市をロックダウンせず、私権を極端に制限しないで対応してきたことを政府は誇っています。もちろん、これは評価が分かれるところですが……。片や、本書の3章のリレー・エッセイでお二人とも触れているように、日本の都市は欧米に比べて規制が緩く、自由なデザインの建築が多いという面もありますよね。そこで、あらためて公と私の関係や、「自由」というものについてご意見をお願いいたします。
【井上】青木さんが本書の3章で触れていた、フランスから来た留学生のエピソードが印象的です。ファサード(外観)は設計者のものじゃなく、公共のものだというふうに彼らは考えている。これには、ああなるほどと思いました。
【青木】ロンドンで、水上に建つ建築を建て替えるというプロジェクトを設計したことがあります。日本と同じで、イギリスでも建築確認申請が通らないと建設できないのですが、その前に「プレ建築確認申請」という事前審査があって、デザインや、環境問題、水中の生物に対する影響について、専門家たちと議論する場が設けられるんです。案のかなり初期から始まって、案の進行と並行して何度も議論します。本番は法文による審査なので、法律で禁じられてさえいなければ通るのですが、プレ建築確認申請は、法律より上位にあるとされている「常識」に照らし合わせての議論なので、実はこちらのほうがずっと通すのが難しいんです。
クライアントが求める案が、プレ建築確認申請でNGに
【青木】私の設計は、波打つ水面のような外壁から成るデザインでした。でも、設計の途中、クライアントがもっと窓をいっぱい、また大きく開けたいというので、そういう案を試すと、窓だらけになってしまって、普通のオフィス・ビルのようになってしまうのです。私としては納得がいかないのですが、クライアントがそうでないと商売にならないというので、その案をプレ建築確認申請で見せたら、デザインとして許容できないと拒否されたんですね。前の案は、ここに建てるのにふさわしかったが、これだと環境破壊だと。それで元の案に近づけることになって、やっと審査に通って実現しました。私は、日本よりこの国のほうがずっと、建築家の「自由」が守られていると思いました(笑)。
【井上】まあ、そういうケースもあるんでしょうね。でも何ていうか、水上だから地権者ではないけれども、クライアントの「自由」は阻害していますね。
商業的な意味合いとは違う何かがヨーロッパにはある
【青木】ええ、クライアントの自由を阻害している。だからそのとき、公的なというのかな――何を公的というかは難しいんですけれども――商業的な意味合いとは違う何かがヨーロッパにはあると実感したわけですね。
【井上】わかります。資本主義になり切っていないわけです。
【青木】経済効果よりも、もっと大事なことがある。パリでの設計は本当に制約だらけで大変なんですけれども、公益の観点から守ろうとする理屈はわかる。その制約の中にあって、それでも自由にできるのかどうかが、建築家の能力として問われているのかなという気がしますね。
【井上】ときどき大統領勅令があって、全ての制限を突破できそうなレアケースもあるんですけどね。ボーブールのポンピドゥー・センターみたいな例がね。でもそれはごく特異な場合で、普通はがんじがらめですよね。
【青木】ええ、がんじがらめ。
ヨーロッパの施主は貴族、日本は下町の商店主
【井上】私がこの現象を社会問題として、最初に感じたのは、安藤忠雄さんが世に出られた頃です。「住吉の長屋」だけではなく、安藤さんは大阪の下町で、施主がお好み焼き屋さんとか文房具屋さんとかの店舗併設住宅もてがけておられました。それらはコンクリートの打ちっ放しですが、みなちっちゃなおうちです。それこそ十数坪の地主を施主とする住宅です。そういうちいさい土地持ちがアーキテクトに作品を要求する国って、すごいなと思ったのがはじまりです。
【青木】確かに(笑)。
【井上】ヨーロッパの都会地で、十数坪の地主ってありえないじゃないですか。東京で東(あずま)孝光(たかみつ)(1933~2015年)さんがつくられた「塔の家」に至っては6坪ですか。それに比べて、ロンドンの地権者はおそらく4~5人なんです。何ヘクタールというような地主しか、あちらにはいません。
【青木】そうなんですか。
【井上】しかも、みんな貴族です。私は学生のときにイギリスのお城を結構回ったんですが、まだ公爵や伯爵らが住んでいたんですよ。だけど日本に残る江戸時代の大名屋敷とか城郭はほとんど、地方公共団体が管理して一般公開もしているじゃないですか。つまり、市民の財産になっているわけです。ロンドンにかぎらずイギリスはまだ廃藩置県が終わっていないんかと。
【青木】領主がいる(笑)。
【井上】そう。どうしてそういうイギリスを、我々は近代化の先駆けみたいにして教わってきたんだろう。十数坪の文房具屋がアーキテクトに設計を依頼する日本のほうが、はるかに近代的なんじゃないか。ただ、ロンドンとちがって、日本では、ささやかな人民が自分の狭い土地へ勝手な建物を建てるから、ごちゃごちゃした街並みになるという問題もあるのですが。
混乱した都市風景は日本の魅力でもある
【青木】ヨーロッパでは、建築家は大富豪のため、あるいは国家プロジェクトのために仕事をしますが、少なくとも戦後の日本では、建築家は小さい事業主というか地権者のために仕事をしてきました。そのため、日本ではバラック的なものが建ち並び、混乱した都市風景になった。町中、電信柱だらけで、空中には電線が蜘蛛の巣のように張っている。でも、私はそれが結構好きなんです。大きな権力ではなく、小さな権力の欲望でできている都市風景は、日本の魅力でもあるんじゃないか、と。ところが昨今、そんな有象無象が買収され、一つの資本にまとめられ、再開発されていく。日本的大富豪が生まれ、それが国家戦略と結びついて、彼らが思うヨーロッパ的な都市に変えていっている。
【井上】まだヨーロッパに憧れる心性がなくなっていない。
【青木】とはいえ、ヨーロッパの都市は、時代を跨いだ長い試行錯誤を経て、できあがってきたものですよね。そこでさえ、今や経済論理の力で急速にその姿が変わっていっています。過去と現代とのガチンコがあるからまだそれでも、というところはありますが、日本の場合は、過去はスクラップ・アンド・ビルドで総浚(そうざら)いした上での、大資本の論理だけでつくられる「都市美」です。急ごしらえの美意識で都市をつくるのは、いつだって危険なことだと思いますね。
首都高は結果的に素敵な風景をつくりだしている
【井上】青木さんは混乱した都市風景がお好きだとおっしゃいます。たとえば東京オリンピックのレガシーである首都高は美しい。そう思おうよ、あれは素晴らしいじゃないか、と。セーヌ川の上にあんなものは到底通らないんだけど、これを通すことのできた日本を肯定しようよ、ということでしょうか。
【青木】微妙なところですが、首都高はところどころで、結果的に素敵な風景をつくりだしていると思っています。たとえば『惑星ソラリス』(アンドレイ・タルコフスキー監督、1972年)の映画の冒頭は、首都高を走るシーンです。1970年代における、未来的であると同時にノスタルジックな風景の美しさが、フィルムに定着されています。高架下から見上げると、飯田橋あたりはいいですね。それは、首都高の設計に変な美意識は入っていないから生まれた偶然の産物ですが。美意識がないので日本橋の上も頓着なく通しちゃうという暴挙もあり、問題も多々ありますが、全体的には……肯定したいなと思います。
【井上】わかりました。私はちょっと……いや、ちょっとどころか、かなり違うんです。そこで二人の物別れというオチができますね(笑)。
【青木】(笑)
「バチカンが燃えていいのか」ローマを守るために降伏したイタリア
【井上】イタリアで教えられて知ったのですが、第二次世界大戦中の1943年7月19日に、初めてローマは連合軍の空爆を受けたんです。この翌日にイタリアの参謀本部はもう戦争をやめようと、国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世に掛け合いました。ムッソリーニの逮捕と連合国への休戦申し込みを、初空襲の翌日に決めるんですよ。
【青木】なるほど。
【井上】彼らは、ローマに爆弾が落ちると思っていなかったのです。で、あらためて考えだしました。コロッセオを焼いていいのか、バチカンが燃えていいのか、と。ローマはそこら中に建築の宝がある。これを維持するのは自分たちの務めだ、という思いがかなり強かった。フランスだって、ナチスの前に早々と敗北を決めたのは、パリを焼くわけにいかんという思いがあったからです。ごく近年も、ノートルダム寺院の屋根が焼けおち、脱魂状態になったフランス人はおおぜいいました。ナチスの戦車とパリでドンパチするわけには、いかなかったと思います。
だけど東京は、連合国の空爆に3年4カ月持ちこたえました。軍の一部では、国土が焦土となっても戦闘を継続する途さえ、さぐられたんですよ。後世へ伝えなければならない建築などというものはただの一つもなかったんだなと、非常に切なく感じます。建築という文化財が戦争への抑止力となることに気付いたとき、私はイケイケドンドン風の建築観を改めました。
自分たちが築いてきた環境への愛情が希薄な日本
【青木】まったく同感です。日本においては、自分たちが築いてきた環境への愛情が希薄ですね。自分たちが生活している日常的な風景が失われることにかなり無頓着です。自分の人生が周りの環境よりずっと短く、私たちはその環境をただ通り抜けていっているだけという感覚がない。シェークスピアではないけれど、ヨーロッパだとどこかに、人間はこの世という舞台に登場しては消えていく役者にすぎないという感覚があるんでしょうね。
そんな日本ですが、一人一人の、その時々の欲望でできあがる建物の集合である町もまた、それでもなぜか、固有の空気の質をもってしまうのが、私は面白いと思っています。荻窪という東京の中央線沿線の住宅地がありますが、いろいろな時代につくられた、ほんとうにさまざまな意匠の家が立ち並んでいます。でも、そこにはなにかひとつの空気が漂っている。それを象徴するように、高架となった中央線に乗って町を見ると、ひとつひとつの個性は消えて、一面に広がるじゅうたんのように見えるんです。それぞれの細胞が次々に自由に建て替えられて行っても、全体の空気はさほど変わらない。その安心があったから、自分の周辺環境に無頓着だったのかな、と想像しています。
そういうなかで、もっとも怖いのは面的な大規模再開発です。都市における細胞である建築の交換なら大丈夫、首都高のような血管である道路の増設もまだいい、でも違う臓器が移植されたらひとたまりもない。
---------- 井上 章一(いのうえ・しょういち) 国際日本文化研究センター所長 1955年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒、同大学院修士課程修了。京都大学人文科学研究所助手、国際日本文化研究センター助教授、同教授を経て、2020年より現職。専門の風俗史・意匠論のほか、日本文化や美人論、関西文化論など、研究範囲は多岐にわたる。『つくられた桂離宮神話』(講談社学術文庫)サントリー学芸賞受賞、『南蛮幻想』(文藝春秋)芸術選奨文部大臣賞受賞、『京都ぎらい』(朝日新書)新書大賞2016受賞など著書多数。 ----------
---------- 青木 淳(あおき・じゅん) 建築家・京都市美術館館長 1956年横浜市生まれ。東京大学大学院修士課程を修了。91年青木淳建築計画事務所(現在、AS)を設立。住宅、公共建築、商業施設など作品は多岐に渡る。《潟博物館》で日本建築学会作品賞を受賞。京都市美術館の改修に西澤徹夫とともに携わり、2回目の日本建築学会作品賞を受賞。2019年4月から同館の館長に就任。東京藝術大学教授。著書に『原っぱと遊園地』など。04年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。 ----------











