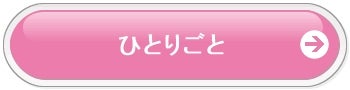徳川家康生誕地の愛知県岡崎市・岡崎城の西に矢作川(やはぎがわ)が流れています。そこに日吉丸(後の豊臣秀吉)と蜂須賀小六正勝の石像が建っています。
実は矢作橋の上で野宿していた日吉丸が蜂須賀小六と出会ったという逸話を再現した石像なのですが、結論から言うとこの石像は史実ではありません。
なぜかというと、矢作川に初めて橋が架けられたのは関ケ原合戦の翌年・慶長6年(1601)といわれており、この時点で秀吉も小六もすでに亡くなっているからです。つまりこのハナシは江戸時代の創作なのです。
ではなぜ矢作川に戦国時代に橋が架けられなかったのかというと、橋を架けたら敵が橋を渡り岡崎城に攻めてくるからです。
そんな中、もし重要なVIPが橋を渡る時は、船橋(ふなはし)というものが臨時に架けられました。
船橋って?
船橋(ふなはし)とは、その名の通り船を並べて板を通した橋のこと。船で渡ると揺れますが、船橋はイカリでガッチリと固定してあるので揺れずに渡る事ができます。
近くの漁師達の船を総動員して臨時に橋にするのです。無事にVIPが渡ると船橋は解散。これでもし敵が攻めてきても川を渡ることができないのです。
実際に織田信長の一代記・信長公記(しんちょうこうき)にも、甲斐武田氏を滅ぼした後、信長のために天竜川(静岡県)に船橋を架けた事が書かれています。
船橋の模型はここで見れる!
かつての船橋の様子は一宮市尾西歴史民俗資料館に詳細な展示やジオラマがあるのでここで見ることができます。
一宮市尾西歴史民俗資料館周辺は、かつての街道・美濃路に面しており、尾張と美濃の国境だった木曽川に何度か船橋が架けられた歴史があるのです。
私が講師を務める愛知ウォーキング城巡りクラブの街道見学会で美濃路・起宿に残る船橋跡も見学してきました。
当日参加者から出た意見は次の通り
・船橋作る労力とお金が凄そう
・工事で亡くなった方もいたのでは?
・実際に見てみたかった
・何艘くらいの船で木曽川を渡れるのか?
など。
素朴な疑問の中にもスルドイ意見がありますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【一緒に愛知の城巡りしませんか?】
愛知県の城址や戦国史跡を現地集合解散で巡る城の会・【愛知ウォーキング城巡りクラブ(AWC)】。活動は夏季を除く毎月第一土曜、もしくは日曜日。城好き、戦国好きの集まりですが知識の多い少ないは関係なし!好きならそれでOKです。入会費や年会費などもないので、あなたも気軽に遊びに来てみませんか?