12月10日の新聞記事によると、今回の衆議院総選挙にあたり、公明党・創価学会が、旅行会社大手のJTBに対して、公明党に協力するよう圧力をかけていたとのことです。

JTB、社員に公明支援要請 国交省所管、大臣は党公認|朝日新聞
旅行業は国土交通省が管轄しており、太田昭宏国交相は公明党公認で東京12区から立候補しているという、極めてわかりやすい構図です。
JTBの社内では、11月27日付で取締役旅行事業本部長の名義で2通の文書が社員に送られたそうです。公明党公認の候補者がいる東京12区と神奈川6区に住む社員には、支援者名簿をつくるための署名を集める内容。他の社員にも、公明党への支援を表明する趣旨の署名を集めるよう求める内容だったそうです。
JTBの広報室は、「あくまで任意のお願い」と記者に回答しそうですが、これは文書を受け取った従業員の側としては、どうなんでしょうか。
2.企業(団体)の団体構成員の思想・信条の自由の問題
一昔前ですが、私のかつての職場で、ある署名活動に参加・協力するようお願いする趣旨の「社内通達」の文書がPC上でまわってきたことがあります。もちろんそれぞれ仕事も忙しいですし、その通達もタイトルからして「お願い」であったため、私も含め我々職場の従業員の取り組みは低調でした。
それに見かねた庶務担当の課長補佐が、ある日の朝礼で、「先日の署名に関する通達は、あくまでも社内通達ですので、会社からの業務命令です!任意ではありません!業務の一環として取り組んでください!従わないのは規律違反です!」と一喝し、その後、数日であっという間にその署名の職場での目標が達成されたのをよく覚えています。
そういった意味で、企業で働く従業員の感覚からすれば、うえのJTBの広報室の弁解は形式論にすぎないと言わざるを得ないでしょう。
かりに文書のタイトルに「任意のお願い」などと書かれていたとしても、取締役本部長名の文書であれば、管理職が「必達!」と血眼になり、組織の下にいけばいくほど、それは業務命令として強制力を伴うでしょう。
また、こういう形で、会社の経営幹部が従業員に、特定の政党への支持などをうながすことをどのように考えるべきなのかが問題となります。
この問題については、著名なものとして、
八幡製鉄事件(最高裁昭和45年6月24日判決)
南九州税理士会事件(最高裁平成8年3月19日判決)
群馬司法書士会事件(最高裁平成14年4月25日判決)
などがあります。
たとえば、群馬司法書士会事件は、群馬の司法書士会が、阪神淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に復興支援金を寄付する為に、自らの特別負担金を徴収することを決議しました。これに対して、一部の司法書士の会員が決議の無効を求めて出訴したものです。
ごくおおざっぱにいえば、これらに共通する問題には、
①その団体(法人、企業、税理士会など)の目的の範囲内(民法34条)なのか否か
②その行為が団体構成員の思想・信条の自由(憲法19条)を侵害しないかどうか
という2つの論点があります。
群馬司法書士会事件について、最高裁は、①目的の範囲内であるとして、また、②思想・信条の自由を侵害するともいえないと判断しました。
ところで、うえの判例のように著名ではないのですが、一応最高裁まであがった事件で、「政治献金」といったギラギラしたものではなく、うえの群馬司法書士会事件と同じように「善意」をモチーフにしつつ、反対の判断をしたつぎのような興味深い最高裁判決があります。
3.滋賀県自治会赤い羽根共同募金強制徴収事件(最高裁平成20年4月3日判決)
(1)事案の概要
滋賀県甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」は、従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して任意で集めてきました。
しかし自治会の役員に集金にかなりの負担がかかることから、自治会の定期総会で、年会費6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして強制徴収することを定期総会で賛成多数で決議しました。
これに対して、一部の住民から、「寄付するかどうかは個人の自由のはずだ」と強制徴収に反対の声があがり、訴訟の提起に至ったものです。
(2)判決
(a)第一審
第一審である、大津地裁平成18年11月27日判決は、自治会側の勝訴としました。
(b)第二審
ところが、第二審の、大阪高裁平成19年8月24日判決は、募金及び寄付金は、その金銭の性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」、自治会の役員の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体が、希望ケ丘自治会の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」と判示しました。
また、募金及び寄付金に住民が応じるか否かは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、住民の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるとして、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」と判示し、公序良俗(民法90条)に反するとしました。
このようにして、大阪高裁判決は住民側を勝訴としました。
これを受けて、自治会側が上告しました。
(c)最高裁
最高裁第1小法廷平成20年4月3日判決は、上告をあっさりと棄却し、大阪高裁の住民側勝訴の判決が確定しました。
この滋賀県自治会赤い羽根共同募金事件の判決をみて思うのは、裁判所は、自治会の住人・構成員はさまざまな属性、社会的・経済的状況におかれていて均質ではないことに着目していることと、また、善行であるとしても、募金に応じることを事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害になるとしっかり判断していることが注目されます。
つまり、この滋賀県の判決は、うえであげた私の昔の職場での体験であった署名活動のような活動のようなことも、職場の人間を均質な「イエスマン」として扱うのはおかしい、さまざまな属性、社会的、経済的、思想的状況に置かれているはずだと判断するでしょう。
また、署名活動自体に関しても、それがたとえ社会通念に照らして良い目的を目指すものであったとしても、それを事実上強制することは、従業員の思想・良心の自由の侵害になると判断するかもしれません。
(やや余談ですが、それ自体は善行であるとしても、なぜ「赤い羽根共同募金」が強制徴収を全国で励行しているのか、それがよくわかりません。「善意」であり「募金」であって、「税金」ではないはずなのですから、なぜ自体会内でこういった訴訟沙汰が起きるまでに赤い羽根共同募金が我々市民に対して募金をあたかも税金のように「強制」し「強要」するのか、よくわかりません。これでは「ヤクザのシノギ」や「善意の押し売り」ではありませんか。募金とは、本来、市民が自分の意思で任意で主体的に行なうものではないでしょうか。)
ひるがえって、今回のJTBの取締役本部長が従業員に対して発出した2通の文書についてですが、これも同様のことがいえるのではないでしょうか。
JTBという企業の役職員がどのようなメンバーで構成されているかが問題となるでしょう。これがたとえば、端的に言えば、国会議員の政党のように、ある政策のために一致団結したメンバーの政党であるならば、その構成員は均質であるといえるでしょう。
あるいは、世の中には、「わが社は仏教系の団体です」といった、思想・宗教あるいは政党的な色彩をあらかじめはっきりと打ち出している企業や団体もあります。そのような企業などに入社する構成員の人達も、ある程度は均質なメンバーであると思われます。
一方、世の中の多くの企業は、会社の社是として思想・宗教・支持政党などを明確に明示しているとはあまり思えず、逆に、「中庸」こそが一般的な企業のスタンスな気がします。
私はJTBのことは直接よく知らないのですが、普通に旅行代理店などの店頭であるとか、新聞紙面などで読む限りは、ごく一般的な大企業であるように思われます。
そして、そのような一般的な企業の構成員である役職員は、とくに近年は非正規社員化が進行していることもあって、よりさまざまな属性、社会的・経済的状況、思想、信条にわかれるものと思われます。
(そして、近年は「ダイバー・シティー取り組み」を経営理念のひとつとして掲げて、多くの企業が、「多様性」であることこそを推進しています。)
そのような状況下で、取締役本部長名義の文書で事実上の職務命令として、特定の政治政党への支持を事実上強制することは、従業員の思想・良心の自由の侵害になると裁判所に判断される可能性があります。
4.国家vs市民・民間企業の問題‐立憲主義的な意味での憲法
なお、ここまではJTB内部の問題について書きましたが、本来もっと問題となるべきは、公明党が国土交通省大臣の威光をかさにかけて民間企業であるJTBに対して自分の政党に投票をするよう圧力をかけてきたということでしょう。
うえで書いた、赤い羽根共同募金の自治会と住民との訴訟や、JTBにおける取締役と従業員との関係は、私人と私人との関係であり、国家権力を制御しようとする機能を第一とする憲法は、民法の90条、同1条2項などの一般条項を通じて間接的に適用されます(間接適用説)。
一方、この「公明党・国土交通省という国家権力vs民間企業JTB」という関係は、まさに憲法が想定するところの、「暴走する国家権力vs抑圧・弾圧される市民・民間企業」という、教科書通りの展開です。
日本を含む近現代の諸国が採用する憲法は、国家権力の暴走(専横)を防ぎ、国民の人権や個人の尊重を図ろうとすることを第一義としています(立憲主義)。
つまり、今回公明党の事件は、完全に国家権力が暴走して民間部門につかみかかっている状況です。これは国家権力が民間企業に対して特定の政治政党への投票への圧力をかけているのですから、思想・良心の自由の侵害(憲法19条)となり、また、公明党がそのバックに創価学会があって密接不可分であることから、信教の自由の侵害(憲法20条)にもあたります。
さらに、公明党に投票しろ、それ以外には投票するなと圧力をかけてきているのですから、選挙権の侵害(憲法15条)にもあたります。
また、こうも露骨に創価学会が顔を出してくると、やはり信教の自由とパラレルな関係にある、政教分離の原則の問題がどうしてもやはり論点となってくるでしょう。政教分離原則に関しては、憲法20条、同89条が規定しています。
たとえば、憲法20条1項は、「いかなる宗教団体も(略)政治上の権力を行使してはならない」と規定しています。
憲法論的にも、つっこみどころ満載ですね。
公職選挙法などの観点からみたらもっとつっこみどころがあるのではないでしょうか。
たしかにJTBの監督官庁が国土交通省でその大臣が公明党で、JTBが逆らえないというのは、社会人として肌感覚としてよくわかるのですが、しかしここはあえて毅然とNo!とJTBの法務部やコンプライアンス統括部などは発言すべきなのではないでしょうか。
多くの従業員が精神的に嫌な思いをされていることはおそらく間違いないでしょう。また、この公明党からの圧力を受けたJTB内のさまざまな役職員の費やしたマンパワーは大変な損害であったはずです。そういった意味で、役職員だけでなく、企業そのものが被害者だと言うことができます。
さらに、今回の騒動を新聞などで読んで、もし外国のヘッジファンドがJTBの株式を売って、その価格が下がったとしたら、JTBの株主全員が公明党や日本政府の被害者となります。
このようなさまざまなステーク・ホルダー達が被害をこうむり、JTB本体も損害を負っている情況であれば、JTBは毅然と公明党・日本政府に「困ります!」と言うべきではないでしょうか。主権者としても、納税者としても。
まさにそのために近代的意味の立憲的な憲法は存在します。そして、そのような企業の態度は、反社会的勢力に対する断固とした拒否の態度と同様に、各層のステーク・ホルダーからの支持を得るものと思います。
また、今度の衆議院選挙を、自民、公明の政府・与党は、「アベノミクスの信を問う選挙」と位置付けているようです。
しかし国民の側としては、憲法尊重擁護義務(憲法99条)を無視し、集団的自衛権の認容を閣議決定で済ましてしまうということ等など、自民党、公明党の現憲法へことさら侮蔑の念をたびたび表明する政権の反動・復古的な全体主義的なあり方そのものが問われる選挙であるように思えます。
総選挙で与党が圧勝ということになれば、憲法改正も現実的な問題となるでしょう。
・自民党憲法改正草案(PDF)
自民党の憲法改正草案をみると、たとえば、現在の憲法21条が一切の表現の自由を保障すると規定しているところを、「公益及び公の秩序に害」しない限り、という権力者の使い勝手がよいように表現の自由の保障の範囲を狭めています。
憲法20条の信教の自由の部分では、さりげなく政教分離の原則を緩和して、公明党への配慮をしています。
また、憲法9条の部分では、自衛隊を国防軍にするのはもちろんのこと、軍法会議の復活を規定しています。
さらに、現憲法の99条の憲法尊重擁護義務にあたる部分では、なぜかその名宛人に国民を加える一方で、天皇を除外しています。
今回の公明党のJTBへの圧力の事件は、まさにこのような現政府・与党の反動・復古的な全体主義的な体質を改めて浮き彫りにしたものでした。
■参考文献
・有斐閣『判例セレクト2007』6頁
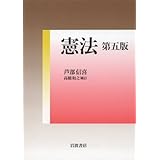 |
 |
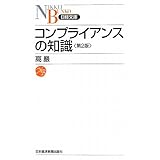 |
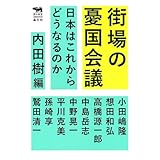 |
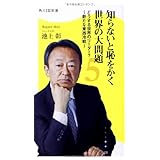 |
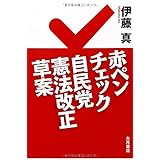 |
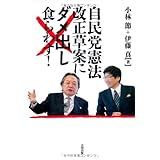 |
法律・法学 ブログランキングへ
にほんブログ村