『恬淡(てんたん)にして虚無ならば真気これに従い、精神を内に守れば病いずくんぞ従いきたらんや。』
これは、「黄帝内経(こうていだいけい)」という東洋医学の医学書の最初にでてくる言葉です。
少し難しいかもしれませんが、意味としては「心にわだかまりがなくとらわれのない状態であれば、気の流れが心の状態に従って淀みなく流れるので、どうして病気になることがあるだろうか。」ということを言っています。
実は東洋医学では、身体と心はつながっていて一体のものとして捉えます。
ゆえに、病気を発生させる大きな原因として、常日頃の精神状態のあり方を、極めて重要視しています。
人間には様々な感情があり、多用な精神作用があるのは当然のことなのですが、ある特定の感情(例えば憤り、嫉み、自己憐憫、不安等)を過度に、あるいは長期にわたって持ちつづけると、気の流れに不調和をおこして病気を形成する大きな一因になるということなのですね。
そこで今回は、経営の神様・松下幸之助さんの逸話を参考にして、気の流れをよくするための心の持ち方についてのヒントを得ることができればと思います。
松下さんが若かりし頃の話です。
松下さんが船の舳先に腰掛けていた時に、前を通りかかった船員が足をすべらして倒れてしまい、その拍子に松下さんをつかんだため、二人とも海におちてしまったということがあったそうです。
自分で落ちたのではなく、他人に落とされてしまったという状況で、松下さんは助けられた時に「今が夏で良かった。冬の海でなくて幸運だった。」と思われたそうです。
確かに冬の海であれば命の危険が伴います。
とっさにそのことに思い至ったとしても、海に落とされて「幸運だった」という思いははなかなか出てくるものではないように思います。
普通(?)であれば「今日は厄日だ…」とか、「あぁ、なんて自分は不運なんだ…」とか、あるいは「このやろーボコボコにして簀巻きにして重りつけて海に沈めてやる!」ということくらいは…実際にはやらないにしても思ってしまいそうなものです。
ごく自然に物事の良い面がみえる、あるいは不利な状況の中にあっても不幸感覚を抱かず、自分にとって良い部分、ためになる部分を見出して心の平安を保っていけるようなメンタリティというのはどうすれば身についてくるのでしょうか?
つづく
人気ブログランキングへ
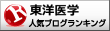
東洋医学 ブログランキングへ
これは、「黄帝内経(こうていだいけい)」という東洋医学の医学書の最初にでてくる言葉です。
少し難しいかもしれませんが、意味としては「心にわだかまりがなくとらわれのない状態であれば、気の流れが心の状態に従って淀みなく流れるので、どうして病気になることがあるだろうか。」ということを言っています。
実は東洋医学では、身体と心はつながっていて一体のものとして捉えます。
ゆえに、病気を発生させる大きな原因として、常日頃の精神状態のあり方を、極めて重要視しています。
人間には様々な感情があり、多用な精神作用があるのは当然のことなのですが、ある特定の感情(例えば憤り、嫉み、自己憐憫、不安等)を過度に、あるいは長期にわたって持ちつづけると、気の流れに不調和をおこして病気を形成する大きな一因になるということなのですね。
そこで今回は、経営の神様・松下幸之助さんの逸話を参考にして、気の流れをよくするための心の持ち方についてのヒントを得ることができればと思います。
松下さんが若かりし頃の話です。
松下さんが船の舳先に腰掛けていた時に、前を通りかかった船員が足をすべらして倒れてしまい、その拍子に松下さんをつかんだため、二人とも海におちてしまったということがあったそうです。
自分で落ちたのではなく、他人に落とされてしまったという状況で、松下さんは助けられた時に「今が夏で良かった。冬の海でなくて幸運だった。」と思われたそうです。
確かに冬の海であれば命の危険が伴います。
とっさにそのことに思い至ったとしても、海に落とされて「幸運だった」という思いははなかなか出てくるものではないように思います。
普通(?)であれば「今日は厄日だ…」とか、「あぁ、なんて自分は不運なんだ…」とか、あるいは「このやろーボコボコにして簀巻きにして重りつけて海に沈めてやる!」ということくらいは…実際にはやらないにしても思ってしまいそうなものです。
ごく自然に物事の良い面がみえる、あるいは不利な状況の中にあっても不幸感覚を抱かず、自分にとって良い部分、ためになる部分を見出して心の平安を保っていけるようなメンタリティというのはどうすれば身についてくるのでしょうか?
つづく
人気ブログランキングへ
東洋医学 ブログランキングへ