みなさんは小柴胡湯(しょうさいことう)という漢方薬をご存知ですか?
以前、その小柴胡湯という漢方薬を肝炎による肝機能障害に使用することで、間質性肺炎という病気をおこしたことから、小柴胡湯には副作用があると言われたことがあります。
今回は漢方薬の副作用についてです。
少しだけ専門的になりますが、できるだけわかりやすく解説してみます。興味のある方は以下おつきあいくださいね。
まずは最初に、一つだけ断っておかなければならないことがあります。
それは、小柴胡湯は「少陽病(しょうようびょう)」の薬であって肝機能障害の薬ではないということです。
少陽病というのは、東洋医学における病名の一つです。
具体的な症状としては、寒気と熱感が繰り返したり、みぞおちや脇の張りが強かったり、口の苦味や吐き気があったり、場合によってはめまい、頭痛等が表れます。
それらの症状と脈や舌、お腹、ツボ等の所見から、東洋医学的に少陽病と診断できた場合にのみ、少柴胡湯は処方されるのです。
それでは、なぜそのような薬が肝機能障害に用いられたりしたのでしょうか。
それはおそらく、東洋医学でいうところの「肝」を「肝臓」とイコールで捉えてしまったためではないかと思われるのです。
東洋医学でいう「肝」というのは、西洋医学の解剖学でいう「肝臓」と同じ物をさしているわけではないのですね。
東洋医学の「肝」は、気血を全身に淀みなく流す働きや、心身の緊張状態を適度に維持する働き、不要なものを解毒し排泄できる形にする働き、血の貯蔵量を調節する働き等の、複数の機能に対してつけられた名称(総称)なのです。
つまり、実質的な臓器そのものを指す名称ではないということですね。
あえて「肝」の働きを西洋医学的に表現すると、肝臓の働きのほかに、自律神経系や内分泌系等の機能を含めたものと言えるかもしれません。
そして、少柴胡湯というのは東洋医学でいう「肝」に関わる病気を治癒するための薬なのですね。
つづく
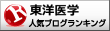
東洋医学 ブログランキングへ
以前、その小柴胡湯という漢方薬を肝炎による肝機能障害に使用することで、間質性肺炎という病気をおこしたことから、小柴胡湯には副作用があると言われたことがあります。
今回は漢方薬の副作用についてです。
少しだけ専門的になりますが、できるだけわかりやすく解説してみます。興味のある方は以下おつきあいくださいね。
まずは最初に、一つだけ断っておかなければならないことがあります。
それは、小柴胡湯は「少陽病(しょうようびょう)」の薬であって肝機能障害の薬ではないということです。
少陽病というのは、東洋医学における病名の一つです。
具体的な症状としては、寒気と熱感が繰り返したり、みぞおちや脇の張りが強かったり、口の苦味や吐き気があったり、場合によってはめまい、頭痛等が表れます。
それらの症状と脈や舌、お腹、ツボ等の所見から、東洋医学的に少陽病と診断できた場合にのみ、少柴胡湯は処方されるのです。
それでは、なぜそのような薬が肝機能障害に用いられたりしたのでしょうか。
それはおそらく、東洋医学でいうところの「肝」を「肝臓」とイコールで捉えてしまったためではないかと思われるのです。
東洋医学でいう「肝」というのは、西洋医学の解剖学でいう「肝臓」と同じ物をさしているわけではないのですね。
東洋医学の「肝」は、気血を全身に淀みなく流す働きや、心身の緊張状態を適度に維持する働き、不要なものを解毒し排泄できる形にする働き、血の貯蔵量を調節する働き等の、複数の機能に対してつけられた名称(総称)なのです。
つまり、実質的な臓器そのものを指す名称ではないということですね。
あえて「肝」の働きを西洋医学的に表現すると、肝臓の働きのほかに、自律神経系や内分泌系等の機能を含めたものと言えるかもしれません。
そして、少柴胡湯というのは東洋医学でいう「肝」に関わる病気を治癒するための薬なのですね。
つづく
東洋医学 ブログランキングへ