前回は、小柴胡湯という漢方薬は東洋医学でいう「少陽病」の薬であって、決して西洋医学でいう肝機能障害のための薬ではないということと、東洋医学の「肝」と西洋医学の肝臓をイコールで捉えてしまうところに問題があるということを解説させていただきました。
今回はその続きです。
もし東洋医学の「肝」を、西洋医学の肝臓とイコールで捉えてしまうと、東洋医学の「肝」に関わる薬を、西洋医学における肝機能の障害に対しても使用できるのではないかという発想がおこってしまうだろうことが容易に想像されます。
確かに、西洋医学的に肝機能障害と診断される人の中にも、東洋医学的には少陽病と診断される人もいるかと思われます。
しかし、中には少陽病と診断されない人もいるのではないかと思われます。
問題は、少陽病と診断されない人達に少柴胡湯が処方された場合です。
その人の体質や漢方薬を飲んだ時の身体の状況にもよりますが、悪ければ持病を悪化させてしまう可能性もあるでしょう。
もし、東洋医学的に少陽病と診断されない人に対して少柴胡湯を処方した結果、間質性肺炎が発症し病気を悪化させてしまったとしたら、それは果たして副作用と呼ぶべきものなのでしょうか。
東洋医学では、これを「誤治(ごち)」といいます。診断を誤ってしまったということですね。
つまり、薬が悪いのではなく、病を診断する医者が悪かったということです。
確かに、西洋医学の病名による処方でも「かぜに葛根湯」のように、効果や安全性がある程度確立されて有効に利用されているものは多数ありますし、それはかまわないと思います。
しかしながら、漢方薬はあくまで西洋医学とは全く違った理論を元に診断し処方されるということを忘れると危険な事もあるということです。
例えば、病院に行って、東洋医学で少陽病と診断されたので少陽病を治すための西洋薬をくださいと言ったとしたら、医師も薬剤師も困るはずです。
西洋医学には、少陽病という病名も概念もないからですね。
東洋医学の診断名で西洋薬が出せないように、本来は逆もまたしかりなのです。
つづく
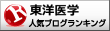
東洋医学 ブログランキングへ
今回はその続きです。
もし東洋医学の「肝」を、西洋医学の肝臓とイコールで捉えてしまうと、東洋医学の「肝」に関わる薬を、西洋医学における肝機能の障害に対しても使用できるのではないかという発想がおこってしまうだろうことが容易に想像されます。
確かに、西洋医学的に肝機能障害と診断される人の中にも、東洋医学的には少陽病と診断される人もいるかと思われます。
しかし、中には少陽病と診断されない人もいるのではないかと思われます。
問題は、少陽病と診断されない人達に少柴胡湯が処方された場合です。
その人の体質や漢方薬を飲んだ時の身体の状況にもよりますが、悪ければ持病を悪化させてしまう可能性もあるでしょう。
もし、東洋医学的に少陽病と診断されない人に対して少柴胡湯を処方した結果、間質性肺炎が発症し病気を悪化させてしまったとしたら、それは果たして副作用と呼ぶべきものなのでしょうか。
東洋医学では、これを「誤治(ごち)」といいます。診断を誤ってしまったということですね。
つまり、薬が悪いのではなく、病を診断する医者が悪かったということです。
確かに、西洋医学の病名による処方でも「かぜに葛根湯」のように、効果や安全性がある程度確立されて有効に利用されているものは多数ありますし、それはかまわないと思います。
しかしながら、漢方薬はあくまで西洋医学とは全く違った理論を元に診断し処方されるということを忘れると危険な事もあるということです。
例えば、病院に行って、東洋医学で少陽病と診断されたので少陽病を治すための西洋薬をくださいと言ったとしたら、医師も薬剤師も困るはずです。
西洋医学には、少陽病という病名も概念もないからですね。
東洋医学の診断名で西洋薬が出せないように、本来は逆もまたしかりなのです。
つづく
東洋医学 ブログランキングへ