二千年以上前の中国の医学書で「黄帝内経(こうていだいけい)」という本があります。
本といっても当時は木簡や竹簡だったと思われますが、その内容はというと、黄帝という偉い方と当時の名医との問答形式で、身体や病気の捉え方やその理、治療法則等を説いた東洋医学の根本経典のような本です。
その中にこんなことが書かれています。
黄帝:「同じ環境にいても、病気になるものとならないものがいるが、これはどういう違いによるものなのか?」
名医:「お答えしましょう。同じ鉞(まさかり)でも切りやすい木と切りにくい木があるのは鉞に問題があるのではなく、それぞれの木の太さや性質等の状態に違いがあるからです。それと同じように、病気になってしまう原因は外部要因ではなく、人それぞれの体内の状態、つまり不摂生による内部要因の影響が大きいのです。」
という内容の記述があります。
例えば、同じ職場にいて、かぜをひく人とひかない人の違いは、自分が作ってきた普段の身体の状態によるのだということですね。
かつて、ドイツの細菌学者のペッテンコーフェルという人は、抵抗力があれば病気にはかからないということを証明するために、コレラ菌の入った水を飲んでみせたことがあるそうです。
結果は軽い下痢にはなったものの、コレラにはならなかったそうです。
細菌やウイルスは、病気を引きおこす重要な要素のひとつであることは間違いありません。例えると、細菌やウイルスは病気の種のようなものですね。
しかし、その種を発芽させ開花させるためには、発芽条件を整えなければなりません。
東洋医学的にいえば、身体が熱に傾いていたり、冷えに傾いていたり、あるいは、生命エネルギーである気が不足していたり、流れが悪かったりするような状態は、自然治癒力が働きにくい状態で、病気の種にとっては発芽条件が整っているということになります。
でも逆から言えば、発芽条件さえ整っていなければ、病気の芽がでることはないということにもなりますね。
細菌やウイルスは病気を引きおこす要因であり、身辺の消毒をしておくことは確かに大切なことです。
しかしながら、ペッテンコ-フェルのように、それらが体内に入れば必ず病気になるかというとそうでもありません。
細菌やウイルスが活動しやすいような体内環境を提供しなければよいのです。
つまり病気の種の発芽条件を整えないということですね。
これを東洋医学的にいうと、体内の寒熱の偏りをなくし、気を充実させ、淀みなく流しておくことで自然治癒力を正しく働かせておくことということになります。
このように、東洋医学は、細菌やウイルス等の外部の要因をコントロールしようとするよりは、むしろ身体の内部環境をコントロールすることの方を非常に重視するのですね。
つづく
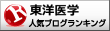
東洋医学 ブログランキングへ
本といっても当時は木簡や竹簡だったと思われますが、その内容はというと、黄帝という偉い方と当時の名医との問答形式で、身体や病気の捉え方やその理、治療法則等を説いた東洋医学の根本経典のような本です。
その中にこんなことが書かれています。
黄帝:「同じ環境にいても、病気になるものとならないものがいるが、これはどういう違いによるものなのか?」
名医:「お答えしましょう。同じ鉞(まさかり)でも切りやすい木と切りにくい木があるのは鉞に問題があるのではなく、それぞれの木の太さや性質等の状態に違いがあるからです。それと同じように、病気になってしまう原因は外部要因ではなく、人それぞれの体内の状態、つまり不摂生による内部要因の影響が大きいのです。」
という内容の記述があります。
例えば、同じ職場にいて、かぜをひく人とひかない人の違いは、自分が作ってきた普段の身体の状態によるのだということですね。
かつて、ドイツの細菌学者のペッテンコーフェルという人は、抵抗力があれば病気にはかからないということを証明するために、コレラ菌の入った水を飲んでみせたことがあるそうです。
結果は軽い下痢にはなったものの、コレラにはならなかったそうです。
細菌やウイルスは、病気を引きおこす重要な要素のひとつであることは間違いありません。例えると、細菌やウイルスは病気の種のようなものですね。
しかし、その種を発芽させ開花させるためには、発芽条件を整えなければなりません。
東洋医学的にいえば、身体が熱に傾いていたり、冷えに傾いていたり、あるいは、生命エネルギーである気が不足していたり、流れが悪かったりするような状態は、自然治癒力が働きにくい状態で、病気の種にとっては発芽条件が整っているということになります。
でも逆から言えば、発芽条件さえ整っていなければ、病気の芽がでることはないということにもなりますね。
細菌やウイルスは病気を引きおこす要因であり、身辺の消毒をしておくことは確かに大切なことです。
しかしながら、ペッテンコ-フェルのように、それらが体内に入れば必ず病気になるかというとそうでもありません。
細菌やウイルスが活動しやすいような体内環境を提供しなければよいのです。
つまり病気の種の発芽条件を整えないということですね。
これを東洋医学的にいうと、体内の寒熱の偏りをなくし、気を充実させ、淀みなく流しておくことで自然治癒力を正しく働かせておくことということになります。
このように、東洋医学は、細菌やウイルス等の外部の要因をコントロールしようとするよりは、むしろ身体の内部環境をコントロールすることの方を非常に重視するのですね。
つづく
東洋医学 ブログランキングへ