中国の古典に「三利あれば、必ず三患あり。」という言葉があります。
三つ利点があれば、それによって受ける不利な点も必ず三つくらいあるぞという意味ですが、発想の転換というか、考えようによっては逆もまた真なりで、三つ悪いことがあっても、それによって三つとはいわずとも一つくらいはいいことがあるのではないかという解釈も成り立つわけです。
例えば、ケガや病気は嫌なものですが、ケガをして初めて五体満足で動けていたことがありがたいことだったのだなぁと思って、足る心を学ぶかもしれません。
大病を患って初めて家族のありがたさがわかり、感謝の心を学ぶかもしれません。
あるいは、それまで理解できなかった他人の苦しみが理解できるようになるかもしれません。
このように、痛い思いをした分、心が豊かになるというか、自分にとっては病気にかからないと絶対に気付けなかったのではないだろうかということも、もしかしたらあるかもしれないのです。
つまり「三患あっても、それによってうける一、ニ利くらいはあるかもよ」ということですね。
そのような自分なりの気付きをみつけることができれば、病気になったことは無駄なことや何かの間違いでおこったことではなく、本当は深い意味があることなのかもしれませんね。
それから病気ではないですが、日々年をとって老いていくというのも一般的には嫌なものでしょう。
しかし、年月を重ねることによってしかわからないことやできないこともまたあるのではないかと思われます。
高度な学問や状況に応じた的確な判断力、職人の技術、家事等の仕事能力は年月をかけて修練しないとなかなか身につきません。
また、人に優しくできるようになったり人のことを理解できるようになったり、人間としての器ができていくのも、人格的に成長していくのも同じですね。
なかなか一朝一夕で完成するものではありません。やはり時間をかけて練られていくものだと思います。
このように、病気や老い等の一見不利なことや自分にとって嫌に思えるようなことの中に、実は本当に自分のためになるものがあるのかもしれません。
できれば年月を重ねていくと同時に、コツコツとたんたんと努力も重ねていくことによって、今よりも成長した人間になっていきたいものですね。
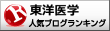
東洋医学 ブログランキングへ
三つ利点があれば、それによって受ける不利な点も必ず三つくらいあるぞという意味ですが、発想の転換というか、考えようによっては逆もまた真なりで、三つ悪いことがあっても、それによって三つとはいわずとも一つくらいはいいことがあるのではないかという解釈も成り立つわけです。
例えば、ケガや病気は嫌なものですが、ケガをして初めて五体満足で動けていたことがありがたいことだったのだなぁと思って、足る心を学ぶかもしれません。
大病を患って初めて家族のありがたさがわかり、感謝の心を学ぶかもしれません。
あるいは、それまで理解できなかった他人の苦しみが理解できるようになるかもしれません。
このように、痛い思いをした分、心が豊かになるというか、自分にとっては病気にかからないと絶対に気付けなかったのではないだろうかということも、もしかしたらあるかもしれないのです。
つまり「三患あっても、それによってうける一、ニ利くらいはあるかもよ」ということですね。
そのような自分なりの気付きをみつけることができれば、病気になったことは無駄なことや何かの間違いでおこったことではなく、本当は深い意味があることなのかもしれませんね。
それから病気ではないですが、日々年をとって老いていくというのも一般的には嫌なものでしょう。
しかし、年月を重ねることによってしかわからないことやできないこともまたあるのではないかと思われます。
高度な学問や状況に応じた的確な判断力、職人の技術、家事等の仕事能力は年月をかけて修練しないとなかなか身につきません。
また、人に優しくできるようになったり人のことを理解できるようになったり、人間としての器ができていくのも、人格的に成長していくのも同じですね。
なかなか一朝一夕で完成するものではありません。やはり時間をかけて練られていくものだと思います。
このように、病気や老い等の一見不利なことや自分にとって嫌に思えるようなことの中に、実は本当に自分のためになるものがあるのかもしれません。
できれば年月を重ねていくと同時に、コツコツとたんたんと努力も重ねていくことによって、今よりも成長した人間になっていきたいものですね。
東洋医学 ブログランキングへ