これまで、東洋医学の基本的なことについていろいろと解説をしてみましたが、今回はこれまでの東洋医学についての解説を、可能な限りさらに要約してまとめてみたいと思います。
そうすることで、一般の方々に東洋医学というものがいったいどういうものなのかを、ざっくりと把握していただければと思います。
それでは、興味のある方は以下おつきあいくださいね。
このブログを読んでくださる方であればもうご存知かもしれませんが、実は東洋医学は、人間の身体と病気を、西洋医学とは全く違った捉え方で理解していきます。
それゆえ、病気に対するアプローチのしかたも病院の治療とは全く違ったものになるのですね。
そのような東洋医学と西洋医学の考え方の違いを、「木を見る西洋人、森を見る東洋人」という言葉で表すことがあります。
個性や部分を重視するか、関係性や調和を重視するかの違いですね。
西洋医学では「世の中は独立した個別なものが多数集まって成り立っている」という、ギリシャ哲学的な考え方が根底にあるため、人間の身体を無数のパーツが集った精密機械のような捉え方をしていきます。
それに対して東洋医学は「世の中はみんなつながっていて個単独ではなにものも存在できない」という、東洋哲学的な考え方が根底にあるため、人間の身体を網の目のようにつながったひとつのものとして捉えていきます。
それぞれにそのような特徴がるため、西洋医学では精密機械としてのパーツ毎の働きにフォーカスしていくのに対して、東洋医学では精密機械よりも、精密機械を動かすエネルギーそのものや、その流れの方にフォーカスしていくのですね。
東洋医学では、精密機械のように精巧な身体を動かすエネルギーのことを「気」という概念で認識し、人間の身体そのものが「気」という生命エネルギーの塊であるというふうに捉えます。
「気」をイメージするならば、それは地球を育む大気のようなものです。
人間の身体を大地、身体を養う血や水分を海や川に例えると、「気」は大気のようなものなのですね。
それは、取り出して見せろと言われても見せることはできませんが、誰もが感じることはできるものなのです。
そして、大気が大地を覆うことで生態系が維持されるように、「気」が全身をくまなく満たすことで健康が維持されます。
もし、「気」の流れが不足したり滞ったりすると、身体の正常な働きが失調して病理状態を引き起こしてしまうのですね。
つづく
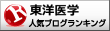
東洋医学 ブログランキングへ
そうすることで、一般の方々に東洋医学というものがいったいどういうものなのかを、ざっくりと把握していただければと思います。
それでは、興味のある方は以下おつきあいくださいね。
このブログを読んでくださる方であればもうご存知かもしれませんが、実は東洋医学は、人間の身体と病気を、西洋医学とは全く違った捉え方で理解していきます。
それゆえ、病気に対するアプローチのしかたも病院の治療とは全く違ったものになるのですね。
そのような東洋医学と西洋医学の考え方の違いを、「木を見る西洋人、森を見る東洋人」という言葉で表すことがあります。
個性や部分を重視するか、関係性や調和を重視するかの違いですね。
西洋医学では「世の中は独立した個別なものが多数集まって成り立っている」という、ギリシャ哲学的な考え方が根底にあるため、人間の身体を無数のパーツが集った精密機械のような捉え方をしていきます。
それに対して東洋医学は「世の中はみんなつながっていて個単独ではなにものも存在できない」という、東洋哲学的な考え方が根底にあるため、人間の身体を網の目のようにつながったひとつのものとして捉えていきます。
それぞれにそのような特徴がるため、西洋医学では精密機械としてのパーツ毎の働きにフォーカスしていくのに対して、東洋医学では精密機械よりも、精密機械を動かすエネルギーそのものや、その流れの方にフォーカスしていくのですね。
東洋医学では、精密機械のように精巧な身体を動かすエネルギーのことを「気」という概念で認識し、人間の身体そのものが「気」という生命エネルギーの塊であるというふうに捉えます。
「気」をイメージするならば、それは地球を育む大気のようなものです。
人間の身体を大地、身体を養う血や水分を海や川に例えると、「気」は大気のようなものなのですね。
それは、取り出して見せろと言われても見せることはできませんが、誰もが感じることはできるものなのです。
そして、大気が大地を覆うことで生態系が維持されるように、「気」が全身をくまなく満たすことで健康が維持されます。
もし、「気」の流れが不足したり滞ったりすると、身体の正常な働きが失調して病理状態を引き起こしてしまうのですね。
つづく
東洋医学 ブログランキングへ