『五臓六腑』とは、「気」の働きや運動のしかたを「肝」「心」「脾」「肺」「腎」の五つの臓という働きと、「胆」「小腸」「胃」「大腸」「膀胱」「三焦」の六つの腑という働きに分割して捉えたものだと考えてください。
前回は、全身の気の働きと運動を「昇降出入」だけで大きくがばっと捉えましたが、その働きと動きをさらに五臓と六腑の11種類に分割して捉えるという感じでしょうか。
例えば、全体の「昇降出入」の降、つまり「気」が下に降りる働きをもう少し細かく分割してみると、上半身の胸のあたりを起点にしてシャワーのように「気」を下半身に向かって降ろすことで、気血を全身に巡らしたり、水分を代謝したりする働きを「肺」と名付けてみたりします。
また、おなかにある「気」が下に降りることで、消化した飲食物を下腹へ送る働きに「胃」と名付けてみるというような具合です。
もし、おなかの気が下に降りなくなると消化不良や腹痛をおこすのですね。
このように、「気」が下に降りるという働きは同じでも、上半身における降と、身体の真ん中における降とでは、また役割が違ってくるのです。
同じように「気」の働きや運動形式を『五臓六腑』として11種類に分割していくのですが、そうすることによって身体の様々な働きや病気のメカニズムを「気」の働きで説明することができるようになるのですね。
例えば、東洋医学で「胃気上逆」という状態は、体内の真ん中あたりの「気」が引き降りる働きが失調して、逆に「気」が上に昇ってしまう異常な状態のことです。
本来、体内の真ん中で引き降りる「気」が上に昇ってしまうのですね。
「気」の運動に異常がおこると、それに伴って胃液が逆流したり、気持ち悪さや吐き気がでたり、実際に吐いてしまったりするような病的な現象が現れます。
このような場合、東洋医学では、おなかの「気」を引き降ろす治療をおこなうのですね。
つまり実質の臓器としての胃袋に処置を加えるわけではありません。
よって、東洋医学でいう「五臓六腑」は、西洋医学でいう「肝臓」や「腎臓」等と同じ物をさしているわけではないのです。
東洋医学の「五臓六腑」は実質的な臓器そのものにつけられた名称ではなく、身体における「気」の働きや運動のしかたそのものに対してつけられた名称なのですね。
つづく
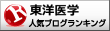
東洋医学 ブログランキングへ
前回は、全身の気の働きと運動を「昇降出入」だけで大きくがばっと捉えましたが、その働きと動きをさらに五臓と六腑の11種類に分割して捉えるという感じでしょうか。
例えば、全体の「昇降出入」の降、つまり「気」が下に降りる働きをもう少し細かく分割してみると、上半身の胸のあたりを起点にしてシャワーのように「気」を下半身に向かって降ろすことで、気血を全身に巡らしたり、水分を代謝したりする働きを「肺」と名付けてみたりします。
また、おなかにある「気」が下に降りることで、消化した飲食物を下腹へ送る働きに「胃」と名付けてみるというような具合です。
もし、おなかの気が下に降りなくなると消化不良や腹痛をおこすのですね。
このように、「気」が下に降りるという働きは同じでも、上半身における降と、身体の真ん中における降とでは、また役割が違ってくるのです。
同じように「気」の働きや運動形式を『五臓六腑』として11種類に分割していくのですが、そうすることによって身体の様々な働きや病気のメカニズムを「気」の働きで説明することができるようになるのですね。
例えば、東洋医学で「胃気上逆」という状態は、体内の真ん中あたりの「気」が引き降りる働きが失調して、逆に「気」が上に昇ってしまう異常な状態のことです。
本来、体内の真ん中で引き降りる「気」が上に昇ってしまうのですね。
「気」の運動に異常がおこると、それに伴って胃液が逆流したり、気持ち悪さや吐き気がでたり、実際に吐いてしまったりするような病的な現象が現れます。
このような場合、東洋医学では、おなかの「気」を引き降ろす治療をおこなうのですね。
つまり実質の臓器としての胃袋に処置を加えるわけではありません。
よって、東洋医学でいう「五臓六腑」は、西洋医学でいう「肝臓」や「腎臓」等と同じ物をさしているわけではないのです。
東洋医学の「五臓六腑」は実質的な臓器そのものにつけられた名称ではなく、身体における「気」の働きや運動のしかたそのものに対してつけられた名称なのですね。
つづく
東洋医学 ブログランキングへ