遊鬱@ripplemirror
高齢を盾に取る石原元知事は論外としても、都民もまたそれをよしとして圧倒的に支持した事を忘れて指弾するのはいかがなものか?これまでの都知事選で争点になっていたにも関わらず「選挙」で追認してきた都民の「自己責任」という視点が不足。或い… https://t.co/wtGq8roDg6
2016年09月22日 08:04
民主主義下の選挙で選んだ以上は、選ばれたものと同様に選んだものも連帯して責任を負うべき―それは投票の秘密という権利を犯すわけだが、衆愚政を防ぐために一顧に値すると思うのだが―。
『民主主義下においては人民は、自分の信頼する指導者を選ぶ。それから選ばれたものは言う「さあ、今度は喋るのはやめて服従せよ。人民も政党ももはや自分に干渉することは許さぬ。」と。その後で人民は審判をすることができる。もし指導者が過ちを犯したならば彼とともに絞首台にのぼることもあるはずです』(マリアンネ・ウェーバー)
8月は不作だったため9月とあわせてメモ。
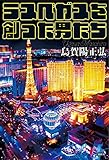 | ラスベガスを創った男たち 1,620円 Amazon |
日本のような賭博大国で新たにカジノ導入の是非を問うことに疑義はあるが、上書は一読の価値あり。ノーブルエクスペリメントと称される禁酒法から今日のラスベガスまでを3人の主要な人物ルチアーノ、ランスキー、シーゲルの物語として一挙に編み上げる。ゴッド・ファーザーの元ネタはここにあったのかと随所でニヤリとさせられる。ほかにもエピソードとして、フーバーダムの水と電力供給がラスベガスを作ったこと、原爆実験がイベントとして観光の目玉になったこと、シチリア上陸におけるマフィアの貢献etc非常に面白かった。
 | 自由主義は戦争を止められるのか: 芦田均・清沢洌・石橋湛山 (歴史文化ライブラリー) 1,836円 Amazon |
著者は自由主義者として名高い三者でも次第に満州を自明のものとした言論を編み出していくことに限界を見て批判的であるのだが、それは当時の状況を知らない「過去の断罪」というべきものだろう。当著は筆者の視座とは別に、彼らが「空気」に抗って紡いだ言論を味わうことにある。「愛国心を算盤玉にのるものにせよ」とは今日でも当然に通用する至言と思われる。
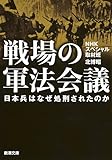 | 戦場の軍法会議: 日本兵はなぜ処刑されたのか (新潮文庫) 594円 Amazon |
NHKスペシャルの再編・文庫版。軍部大臣現役武官制の復活をもってポイント・オブ・ノーリターンとする言説はあるが、法務官の武官制も戦争下でなされたことは露知らず。私にとっての衝撃は、戦場下での処刑の正当化という犯罪に加担した法務官が戦後法曹会で重きを成していたということ。最高裁長官2名、最高裁判事8名、最高検察庁検事総長1名、最高検察庁検事4名を輩出、、、彼らが編み出した「受忍論」の正統性について改めて思いを馳せたくなる一冊(当著では上記該当する具体氏名を上げていないため関係判決時の判事・検事の具体名とリンクした検証はできないが)。
 | 結婚クライシス: 中流転落不安 1,512円 Amazon |
ネーミングの天才、山田教授による「婚活」解説。婚活は独身「市場」の統計的真実を教え、皆が理想を下げて現実的な結婚のススメの筈が、「宝くじ」的理想の相手をいかにおとすかというノウハウ集を示す用語に堕して広まった皮肉。
 | 心という難問 空間・身体・意味 2,592円 Amazon |
これは今年の一冊になるかな…。お得意の今北産業的コメントを附する気にはならない。まさに「世界」に向き合い、信頼する「核」を自分の中に作り上げるための一冊。他我問題、独我論などを超えて公共的なものとして「世界」を整合的に捉える試み。私は腑に落ちました。