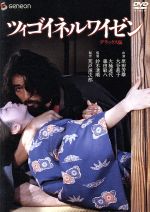前回の記事に関連して内田百閒の「山高帽子」という作品もご紹介します♪
百閒と芥川龍之介が海軍機関学校の教官をしていた時代から芥川が自殺するまでを小説仕立てに描かれています。
語り手となる❝青地❞が内田百閒自身で、青地の友人の❝野口❞が芥川です。
青地は自分の精神状態に不安を覚えながらも、自虐や開き直りも強く、時には敢えて気の違った人のふりをすることもあります。
周囲の人から変人扱いされているので益々神経過敏になっているのか、日常の風景を見ても不穏なものを感じているような描写があったり、広場恐怖症を理解してもらえなかったり、1度だけ幻聴のようなものと不可解な現象まで体験してしまいます。
青地は発狂するのではないかという不安が日を追うごとに募るのでした。
野口はいつも青地のことを❝気違い❞扱いしており、人に紹介する時ですら「この人は僕の友人で先輩で、『瑪瑙』の著者の青地豊二郎と云う気違いです」と言い、自分の書いたものに変な傾向があるとすれば青地の影響なのだと言い切ります。
中でも野口が怖がるのが、青地がいつも被っている❝山高帽子❞でした。
会うたびに「こわい」「あぶない」など言われるので、青地のほうもムキになって山高帽子を被り続けます。
青地を心配したり怖がったりする野口は、実は自分自身が発狂するのではないかという怯えがあるが故なのです。
青地のほうも顔色が悪く睡眠薬漬けになっていく野口のことが心配でなりません。
しかしある日青地は借金のこともあり2ヵ月ほど失踪してしまうのです(内田百閒は現実でも借金魔でした)。
結局戻ってきた青地に、失踪したまま自殺しているのではないかと心配していたことを野口は告げます。
その時の交わされる会話に、青地のある種の強さが見えました。
「君には自殺する勇気もないし」
「勇気もないかもしれないが、どうせ死ぬにきまっているのだから、ほうって置けばよい」
青地は野口と同じように病んでいたかもしれないけれど、野口はその後自殺してしまい青地は生き続けたことに納得のゆくくだりは作中にいくつもありました。
この作品は芥川の自殺から2年後くらいに発表され、その後の「私の『漱石』と『龍之介』」に収録されている随筆集に同じような内容が綴られています。
その中の「亀鳴くや」だけは芥川の死後24年経ってから発表されています。
ただ百閒は、この「山高帽子」はあくまでも小説で、晩年の芥川を綴ったものだとは認めていないのだそうです。
ところで、鈴木清順監督の「ツィゴイネルワイゼン」の原作は内田百閒の「サラサーテの盤」ですが、この「山高帽子」からも同じ場面が映画に取り入れられていました。
青地が幻聴を聞くと同時に、妻と食べていた蕎麦の丼が二つに割れているシーンです。
「ツィゴイネルワイゼン」の主人公の名前も❝靑地❞でしたし、清順監督は百閒の作品から他にもいろいろ織り交ぜているのでしょうね。