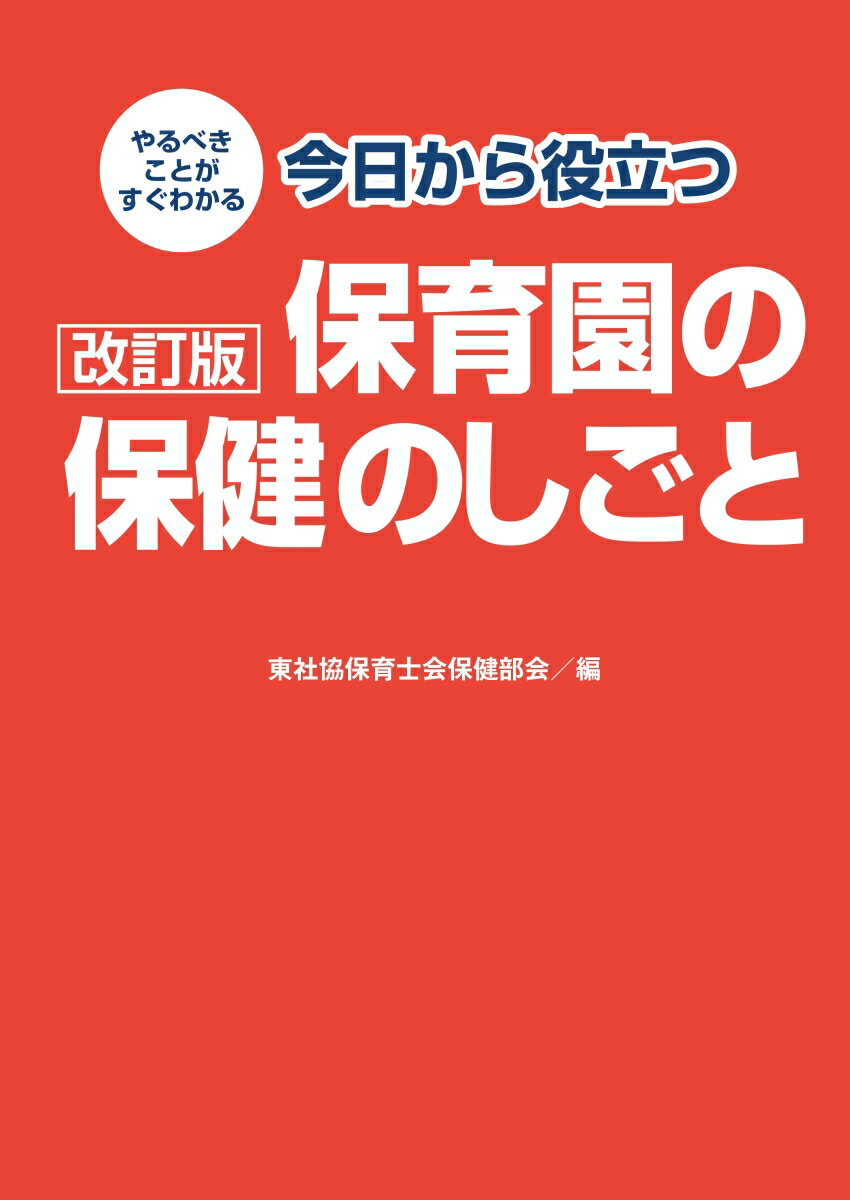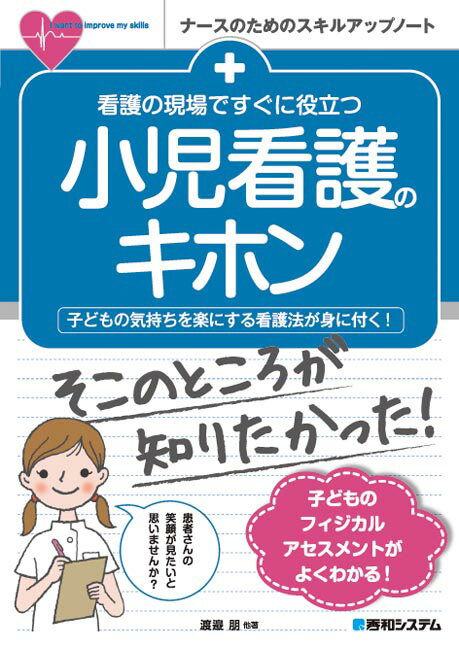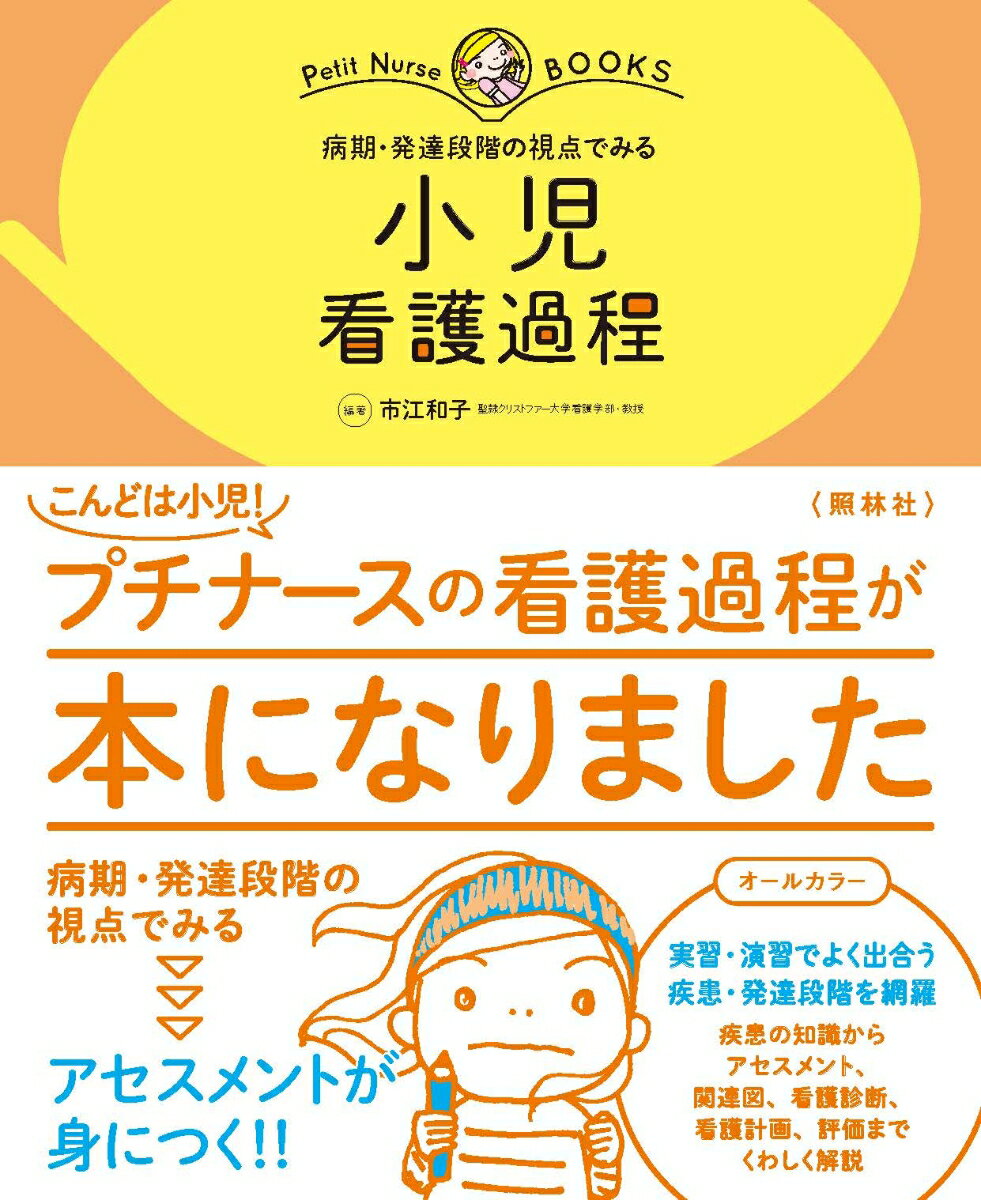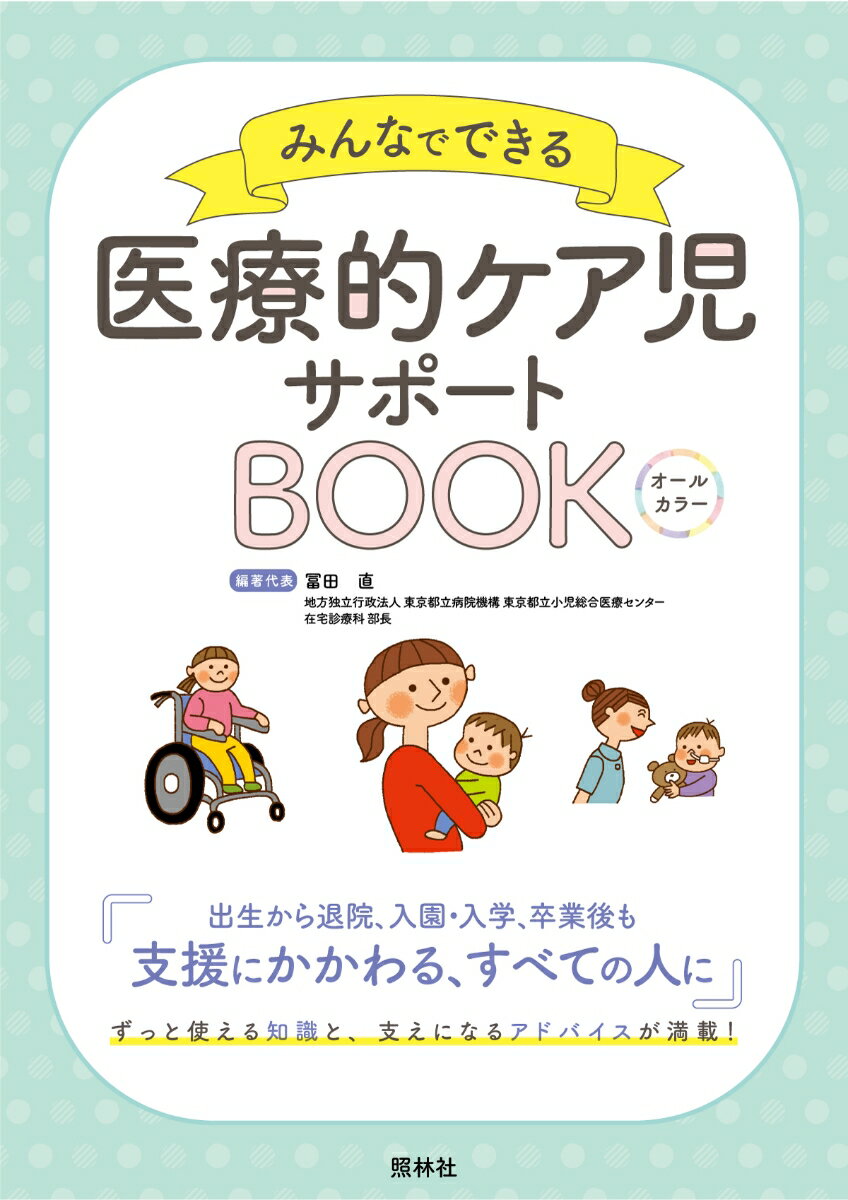保健所と連携しながら対応し、インフルエンザが28名で終息したと思ったら…
その直後から手足口病が流行中。
そろそろ終息できるかなというところで、きょうだいを介して他のクラスへ拡大。
現在、23名の発症です。
終息まではもう少しかかりそう![]()
感染症対応や、お泊まり保育の準備その他諸々に追われていますが、近隣の私大の看護学実習も近づいてきました。
1年って早いなあ…
新型コロナが五類感染症に分類され、今年度から実習もこれまで通りに行えるようになりました。今年も1年生1グループと3年生2グループを担当させていただきます![]()
ただ、問題がひとつ。
外部講師で出張の日は外したのだけど、どうしてもお泊まり保育の引率で実習日不在の日が1日できてしまいました💦
最初は実習とお泊まり保育の日が重ならないように調整していたのですが、お泊まり保育の日程が二転三転してどうにもならず…
副主任と事務で対応してくださるとのことで、昨日引き継いできたところです。
直接指導してあげられなくて、心苦しいけれどありがたい![]()
本格的に臨地実習で小児をまわる前に、子どもたちの生活の場を見てもらうのは、とても重要なことだと考えています。
病気で入院している子どもたちを見る前に、健常な子どもたちを見てもらうことがひとつ(健常という用語は好きではないのですが、便宜上)。
「異常」を知るためには、どうしても「正常」を知っておく必要があります。
そして、もうひとつは退院後の生活をイメージしてもらうこと。
入院している子どもたちのほとんどは、退院して家庭や学校、幼稚園、保育園等の地域に戻っていきます。
慢性疾患のコントロールや、医療的ケアが必要なお子さんが増えている中で、病院ではできていたとしても、家庭や地域の場に戻ったらできないとなると本末転倒です。
退院後の生活を見据えて、継続的に取り組んでいけるようなケアや指導を考えるうえで、子どもたちの生活の場を実際に見てもらうことは非常に意義があることだと思います。
併せて、保育専門職の子ども達への関わり方や、看護職がこのような場でどのような役割を担っているのかも見てもらえたら良いかな![]()
毎年、学生の中から「子どもってできないことだらけだと思っていたけど、実はできることがたくさんあるんですね」といった感想が出てきます。
そう!
子どもってすごいんだよ!✨
疾患や障害の有無に関わらず、どの子も無限の可能性を秘めているんだよ!✨
学生達には楽しく実習してもらって、何かひとつ学びを持ち帰ってもらえたら指導者冥利に尽きるというものですね。
そうなるように、裏方として打ち合わせや事前準備をしっかり行い、実習環境をより良いものに整えていきたいと思います![]()
![]()