2月23日付の新聞に興味深い記事が載っていました。
・自民県連もめすぎて警察ざたに 福岡、執行部方針に不満|朝日新聞

(画像は朝日新聞より)
記事によると、福島県の自民党の政治家達が活動方針などを話し合う年次大会の会議が21日に行われたそうです。その際に、来る県議会選挙の立候補予定者の推薦の決め方をめぐり、県連執行部への不満が一部の政治家から噴出し、会場内でもみ合いが起きたそうです。
驚くべき点はこのつぎで、この会議の紛糾を受けて、なんと執行部側が110番通報をして警察を呼び、警察官がこの会議場に駆けつけたというのです。
ちょっと信じがたい事態です。もちろん政党の政治家達の会議であっても、一部の政治家が激高してナイフを振りかざした等といった異常な事態になれば、警察を呼ぶこともありでしょう。しかし記事によれば、事態はそこまで至っていたとは思えません。
自民党の政治家は、政党の「団体の自治」を何だと思っているのでしょうか。団体の自治の話をおくとしても、言論や議論を命とし、議論を仕事とするはずの政治家のやることとは思えません。
この事件の根底には、政党等の「団体の自治」の問題があります。政党の団体の自治の問題は、憲法においては、裁判所の司法権の限界の問題が大きなテーマです。今回の自民党の事件に直接関係はしないのですが、少しみてみたいと思います。
2.司法権
そもそも司法権に関しては、憲法は第6章に「司法」の項目を置き、裁判所の事柄について定めています。その76条1項は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定しています。
そして、この憲法76条1項に基づき定められた裁判所法の3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定しています。
そこで、憲法のテキストにおいては、司法権とは、「具体的な争訟(=法律上の争訟)について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家の作用」と定義されています。
3.司法権の限界
そのため、裁判所は何でもかんでも判断をして判決を出してよいわけではなく、この司法権の定義にあてはまらない事柄や、憲法等が明文で裁判所が判断してはならないとしている事項、そして憲法の解釈上、裁判所の判断になじまないとされる事柄については、裁判所は判断してはならないとされています。これらが一般的に、「司法権の限界」と呼ばれる問題です。
たとえば一番最初の「司法権の定義にあてはまらない事柄」の例としてよく挙げられる極めて有名な判例は、創価学会が1960年代に建築したお寺に安置した本尊「板まんだら」が偽物であると信者が訴訟を提起したところ、裁判所が宗教上の教義に係る事柄は「法律上の争訟」の範囲外であるとして訴えを却下ものがあります(「板まんだら事件」最高裁昭和56年4月7日判決)
4.部分社会の法理
そして一番最後の、「憲法の解釈上、裁判所の判断になじまないとされる事柄」のカテゴリーに属するひとつが、大学の自治、地方議会、宗教団体、労働組合、そして今回新聞記事になった政党の自治の問題です(「部分社会の法理」)。
つまり、政党、大学等の内部で紛争が発生した場合に、その紛争に裁判所の司法権がおよぶのだろうか?という問題です。
この点、判例は、「一般市民法秩序と直接関係しない純然たる内部紛争は、司法審査の対象とならない」とします。逆に、そうでない内部紛争は、司法審査の対象となります(「部分社会の法理」)。
この判例の表現は少し硬い言い回しですが、要するに、たとえば大学の事例で説明すると、ある学生が大学のある科目で不可となり単位を落としてしまい、単位が落ちていないか否かを裁判で争おうとしても、それは大学のなかの問題にとどまるので、「一般市民法秩序と直接関係しない純然たる内部紛争」であるとして、裁判所はそれを司法審査しません。
しかし、その学生が単位ではなく自分が卒業できるか否かを裁判で争うのであれば、卒業できるか否かは学生が大学の外部に出れるか否かの問題であるので、“一般市民法秩序と直接関係する”ものであり、“純然たる内部紛争”ではないので、裁判で争うことができます(富山大学事件・最高裁平成52年3月15日判決等)。
5.政党の自治‐共産党袴田事件(最高裁昭和63年12月20日判決)
この点、政党の自治と内部紛争、それに対する司法審査の可否が争われた著名な判例として、共産党袴田事件(最高裁昭和63年12月20日判決)があります。
(1)事実の概要
日本共産党(Ⅹ)の副委員長などを務めたY(袴田里見氏)は、党幹部らとの対立により、Ⅹから“党を批判する言論を行った”等の理由でXから除名処分を受けた。そして、YはX所有の家屋に居住していたため、ⅩがYに対して当該家屋の明け渡しを求めて訴訟を提起した。
(2)判旨
「政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって内部的には、通常、自律的規範を有し、(略)一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在である」
(そのため、)「政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」
「したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。」
「Ⅹは、自律的規範として党規約を有し、本件除名処分は右規約に則ってされたものということができ、右規約が公序良俗に反するなどの特段の事情のあることについて主張立証もない本件においては、その手続には何らの違法もないというべきであるから、右除名処分は有効である」
(4)検討
このように最高裁は、まず、政党が議会制民主主義を支えるうえにおいて極めて重要な存在であることから、政党に対しては高度の自主性と自律性を与え、政党の自治を認めなければならないとしました。
そのうえで、除名処分は一般市民秩序につながる問題であるので司法審査の対象となるとしつつも、裁判所の除名処分の当否の司法審査は、その政党内の規約にもとづき適正な手続きにのっとってなされたか否かの点に限って行われると判示しました。
そして結論として、最高裁はX側の主張を認めました。
6.共産党袴田事件から今回の福岡県の自民党県連の事件を考える
この共産党袴田事件の最高裁判決を振り返ってみると、最高裁は、政党による党員の除名処分の可否を述べる前提として、現代の議会制民主主義における政党の重要性の観点から、政党に対しては高度の自主性と自律性を与えるべきであること、政党の自治を保障すべきであることを述べています。
自民党の政治家たちも、自分たちの属している政党とは、国民の政治的意思を国政や地方政治に反映させる媒介として極めて重要な意味を持つのであって、そのような意味で議会制民主主義の重要な構成要素であることを、今一度確認すべきです。
そのような政党が国民の負託にこたえるために、高度な自主性と自律性、政党の自治が保障されるべきです。
今回の福岡の事件のように、政党の政治家の執行部側が、会議中に反対派から反対を受け、もみあいになったからといって、安易に自ら警察を呼ぶような行為は、本来、高度な自律性・自主性を保つべき政党内部に行政の一部問たる警察を自ら招き入れることであり、国民の代表である政党の自治、自主性、自立性を自ら損ねるものです。自民党は与党であるとはいえ、行政に対してもう少し緊張感を持つべきです。
■参考文献
・芦部信喜『憲法[第3版]』307頁以下
・片山智彦「政党の内部自治と司法審査」『憲法判例百選Ⅱ[第6版]』404頁 など
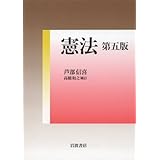 |
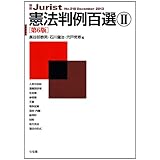 |
法律・法学 ブログランキングへ
にほんブログ村