犬のツボ初心者は、とりあえずここを揉もう。内臓系のツボが集まる場所の解説。
こんにちは。Office Guriの諸橋直子です。
さて、今日は予告通り
「ここをとりあえず押さえておけば外れがない、内臓系のツボが集まっている場所」
の解説。
——————————————
●足の太陽膀胱経には「内臓系」のツボがいっぱい!
——————————————
犬も人も、体に経絡が12本走っているよ、という話は前回のメールでしました。
その12本の経絡のうちの一つ「足の太陽膀胱経」というのがあります。
腎臓、膀胱周りを取り囲む経絡ですが、その一部が「背中」を通るんですね。
そして、その背中を通るルート上に「内臓系」のツボがたくさんある、というわけです。
以下、代表的なものの紹介。
↓
————————————————————-
●肺兪(はいゆ):肺の機能を高める。風邪や喘息で咳き込む時に。
●心兪(しんゆ):心臓の働きを高める。緊張感、ストレスの緩和に。
●肝兪(かんゆ):肝臓の働きを良くする。体がだるい、元気がない時に。
●脾兪(ひゆ)・胃兪(いゆ):共に胃腸の働きを良くするツボ。食欲不振、体力減退に。
●腎兪(じんゆ):腎は中医学で老化防止のために重要な場所と考えられています。老化防止、病気の予防に。
●大腸兪(だいちょうゆ)・小腸兪(しょうちょうゆ):便秘気味、お腹の調子が悪い時に。
●膀胱兪(ぼうこうゆ):尿もれ、排尿障害がある時に。
————————————————————-
内臓系のツボは、その名前がついている臓器と直接つながっていると考えられるツボです。
肝兪であれば肝臓、腎兪であれば腎臓、という風ですね。
その臓器が調子悪い時に、そことつながっているツボを押したり、鍼を刺したり、お灸で温めることで、調子を取り戻せる、というのが鍼灸の基本の考え方。
*
ツボの良いところは
「病気の時に限らず、普段から健康増進の目的で暖めたり指圧したりしていいですよ」
という点。
中医学の特徴でもあります。
西洋医学的「治療」だと、病気じゃないのに治療はしないですよね。
風邪をひいたら風邪薬を飲みますが、風邪の予防に風邪薬は飲まないですよね?という話。
中医学の場合、病気の治療に使う「ツボ」を病気の予防目的や、健康増進に使ってもいいですよ、という風に考えます。
つまり、ツボは一度マスターすると、普段の犬のヘルスケアに使える上、病気の際の回復を助けるためのホームケアとしても活用できる。
まさに一石二鳥の家庭の手当て。それが「ツボ」になります。
では、肝心の「その内臓系のツボってどこに集まっているんですか?」ですが…。
↓
↓
———————————–
●犬の背骨に沿って、左右両側に並んでいる
———————————–
ツボ初心者の方はこんな風にまず、大雑把に理解してください。
その上で、犬の背中の背骨、首から尻尾にかけて、背中の「皮」を引っ張ったりマッサージする。
犬の背中の皮引っ張りは、なんか冗談みたいですが、犬のツボをやる上で必ず学ぶ、初心者向けのテクニック。基本中の基本。
これでも十分、ツボの刺激になります。
そしてもし、もっと強めの刺激を与えて本格的にツボをやってみたい、という場合は
●鍼
●灸
という選択肢があります。
鍼は動物病院で打ってもらってください。
最近は鍼灸治療を施してくれる動物病院もたくさんあります。
Googleで自宅の近所に鍼灸治療を行なっている動物病院がないか?を探してみるのも手です。
でももし、あなた自身が
「自宅で、自分の手で犬にツボ刺激をやってあげたい」
と希望する場合。
私のおすすめは「お灸」です。
健康な犬の健康管理に、病気の犬の回復サポートに、シニア犬の体のケアに。
ツボをやるなら「お灸」。特に初心者の方ほどお灸が実はおすすめです。
「えー、お灸ってハードル高い感じがするんですが、なぜ初心者ほどお灸がおすすめなんですか?」
はい、その理由を次号のメールで詳しくお話ししますね。
興味のある方は是非、お楽しみに!
Office Guri
諸橋直子
(終)
この記事は「メルマガ:ぐり通信」のバックナンバーです。 このメルマガの最新号を購読しませんか? 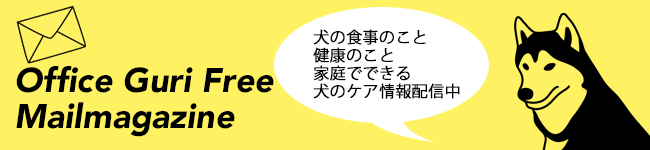
犬の手作り食やマッサージなど、犬の健康をサポートするための情報をメールマガジンで配信しています。 自宅でできる愛犬のマッサージやアロマテラピー、食事について知りたい方はご購読ください*
■無料購読ご登録はこちらから⇒クリックして購読する!
犬のお灸の基礎知識:ツボってなんだろう?ツボの解説
こんにちは。Office Guriの諸橋直子です。
さて、前回のメールで「犬に安全なお灸」を紹介したところ、すごくたくさんの方がリンク先をチェックしてくれたようです。
確かに気になりますよね、犬に安全なお灸。
私も初めて知った時は「ほええええ」と思いましたもの。
さて、今日はその「お灸」を当てる「ツボ」の話をします。
中医学の込み入った話が絡んできますので今日はちょっと長くなります。
つぼとは何か?をはじめの段階できっちり理解した上で次のステップで
「体の悩み別つぼをどう選ぶか?」
という話に進んだ方が、犬の健康管理につぼを生かしたい方には良いとい思うので、その順番で解説してきますね。
————————————–
●ツボ(経穴:けいけつ)ってなんだろう?
————————————–
よく肩こりに効くツボはここ、とか、月経痛にはこういうつぼがいいよ、とか聞いたことはないでしょうか?
私たちは普段、結構こういう話を何気なく会話で聞くことがあり「ツボ」というもの自体は
「なんだか押したり、あっためたりすると体に良かったり気持ち良いポイント」
的な理解を、大雑把にしています。
この「ツボ」というものは、実際何なのか?
そういう話ですね。
————————————–
●基本その1:ツボは経絡(けいらく)上に存在する、内臓とつながったポイントのようなもの
————————————–
中医学には「経絡」という概念があります。
私たちの体の中には「気(エネルギーの巡り)」、「血(血液や栄養を運ぶ流れ)」「水(体液の流れ)」の3つが流れている、という風に中医学では考えています。
この3つのうち、「気(き)」と「血(けつ)」が流れているのが
●経絡(けいらく)
という体の中の通り道だ、という解釈。
ちなみに経絡は、解剖学上存在する器官ではなく、目に見えないエネルギーの運行ルート的に考えられています。
そのルート上に、地下鉄駅のように点在するポイントが「ツボ(経穴)」というわけです。
ここまではOKでしょうか?
さて、経絡は全身に12本巡っていると考えられています。
地下鉄でいうと東西線とか、南北線とか東豊線とかそういう感じですね。(札幌市営地下鉄で例えてみた。札幌市民なので)
どういうルートを巡るか?によって色々名前がついています。
例えば「足の陽明胃経」という経絡があります。
これはものすごく簡単に説明すると「胃腸周りを回り経絡」です。
なので、このルート上にあるツボは「胃腸」の不調に効くとされるツボが多い。
他には「足の厥陰(けついん)肝経」とか「足の少陰腎経」とか経絡の名前に
「肝」
とか
「腎」
という文字が入っている経絡もあります。
これも「肝臓に関係あるんだな」「腎臓とつながりがあるのかな」という風に何となくですが「臓器」とのつながりをイメージさせるのがわかりますよね。
さて、この内臓と繋がるのある、体を走るルートがあり、その上にいくつかの駅が点在する。
その「駅」に相当するポイントを温めたり、指圧したり、鍼を浅く刺して刺激することでそれを内臓に伝え、活性化させたり、調子を整える。
これが「ツボ」を刺激して、体の自然治癒力を高めようという「鍼灸(しんきゅう)」の基本となります。
—————————————————–
●ポイント1のまとめ:
体の中を走行する「経絡」というルートは内臓とつながっている。
その内臓上に点在する「ツボ」を刺激することで内臓の調子を整えたり、働きを正常化するよう働きかける。
これが「鍼灸」である。
—————————————————–
ツボは体上に361個あるとされています。(数は世界保健機関:WHO基準。ただし、それ以上あるとする考え方もあります)
人と犬のツボの位置はほぼ同じです。
ただ、いくつかのツボについては人と犬とでは位置が全然違う、ということも出てきます。
なので、犬のツボを正確に捉えてお灸を据えて温めたい、という場合、犬のツボの取り方について、ある程度基本を学ぶ必要がありますね。
「…う~ん、ということはなんか難しいんでしょうか?」
そう心配になった方、大丈夫です。
ツボの正確な取り方は確かにちょっとした練習と学習が必要です。
でもそういうのをすっ飛ばして、とりあえず初心者の方でもほぼ正確に外すことなく刺激できる、しかも体にとってメリットの大きいツボががっちり集中している箇所、というのが実はあります。
そこには内臓と繋がるツボがゴロゴロしており、とりあえずそこを丁寧に刺激しておくだけでも犬の体のメンテナンスになる、というありがたい場所。
「えええ、そんな場所があるなら知りたいです!」
はい、それではその場所について次号のメールで引き続きお話ししていくので、是非楽しみにしていてください。
本日は以上です。
Office Guri
諸橋直子
(終)
この記事は「メルマガ:ぐり通信」のバックナンバーです。 このメルマガの最新号を購読しませんか? 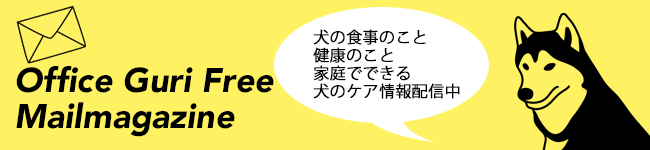
犬の手作り食やマッサージなど、犬の健康をサポートするための情報をメールマガジンで配信しています。 自宅でできる愛犬のマッサージやアロマテラピー、食事について知りたい方はご購読ください*
■無料購読ご登録はこちらから⇒クリックして購読する!
犬にも安全!オススメのお灸は「コレ」だ!お灸の紹介。
こんにちは。Office Guriの諸橋直子です。
今朝の札幌は氷点下4度。寒いです。
今日はそんな寒い日に、体を温めるお灸の話。
予告通り「犬に安全に使えるお灸」をご紹介します。
————————————–
●犬には安全・安心な「棒温灸」
————————————–
お灸には色々な種類がありますが犬に使う場合はとにかく安全度優先!
熱くなく、火傷の心配がないことが大前提です。
「えー、でもそんなお灸なんて存在するのかね?」
はい、そう思いますよね。
でもちゃんとあります。犬にも安全に使えるお灸。
それが棒温灸ですね。
↓
●棒温灸:
https://www.sennenq.co.jp/shop/products/detail/60
これは普通の人間用として売られていますが犬にも問題なく使えます。
世の中にはペット用の棒温灸として売られている製品もありますがお値段が、今回ご紹介した製品の倍くらいするものもあるんですよね。
でも「犬の体のツボを温める」という目的のためには棒温灸であればOK。
だったら今回ご紹介した棒温灸で問題ありません。
というかむしろ、リンク先のページはお灸で最も有名な最大手さんの製品です。
私自身も持っていて、犬たちと兼用で使っているので自信を持ってお勧めできる棒温灸ですね。
というわけで、一つ目の結論。
————————————–
●犬には安全・安心な「棒温灸」がお勧め。
→ https://www.sennenq.co.jp/shop/products/detail/60
————————————–
そしてここからは「中医学」で考える「お灸の効果」について解説していきます。
基本の大前提としてまずは、お灸について以下の予備知識を知っておいてください。
●お灸は中国古典医学「中医学」で用いられる治療法、健康増進法の一種
●お灸は体にある「ツボ(経穴:けいけつ)」を温めるもの
●ツボには様々な種類があり、体の悩み別、ケアしたいポイント別に選べる
ざっと基礎はこんな感じ。
この基礎を踏まえて今回は「お灸にはどんな効果があるの?」という話をします。
↓
↓
↓
「お灸は温熱でツボを温めて、血行を促進し、体の自然治癒力が働きやすいようサポートするセルフケア」
はい、ポイントは「血行促進」ですね。
実は私も今朝、このメルマガを書きながら手がどうしても冷えて困ったので、サクサク棒温灸に火をつけて手のツボを中心に温めるようにお灸をしました。
3分ほど当てるだけで手はポカポカ温まりますね。一度温まると、あとは冷たさによる不快感は無くなります。
で、せっかくお灸に点火したのでついでに、と我が家の14歳の黒ラブ:ぐりの背中も
背骨に沿ってお灸で温めました。
(背骨に沿って温めるのには意味があります。コレは次号のメルマガあたりでお話しできる予定)
程よい温熱なので、ぐりもすうすう寝たままお灸をされていましたね。
残念ながら犬とは言葉で会話することはできません。
でも、今日みたいな寒い日はじんわりお灸の熱を体に当てると気持ちがいいです。
我が家のぐりも、同じようにじんわり心地よさを、おそらく感じているはず。
ということで、2つ目の結論。
————————————–
●お灸は体を温め、血行を促進する
————————————–
冒頭にも書きましたが、今朝の札幌は氷点下4度です。
犬だって体を温めたい。そんな時には我が家の場合、お灸です。
先ほどお灸をした様子を写真に撮りましたのでよろしければどうぞ。
↓
↓
●14歳ぐり、お灸でポカポカ温まる。
特にシニア期の犬には心からオススメです。
お灸の良さはご理解いただけましたか?
次号のメールではお灸を当てる際に欠かせない
———————-
●ツボ(経穴:けいけつ)
———————-
の解説をしますね。
興味のある方は是非、お楽しみに。
Office Guri
諸橋直子
(終)
この記事は「メルマガ:ぐり通信」のバックナンバーです。 このメルマガの最新号を購読しませんか? 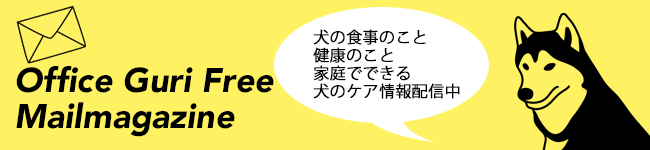
犬の手作り食やマッサージなど、犬の健康をサポートするための情報をメールマガジンで配信しています。 自宅でできる愛犬のマッサージやアロマテラピー、食事について知りたい方はご購読ください*
■無料購読ご登録はこちらから⇒クリックして購読する!