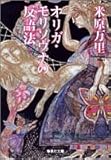万城目学『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』(角川文庫)
初のマキメマナブです、いやータイトルがいつも面白そうで興味はあったんだけど、なんというか、きっかけがなかなか。『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』は入試問題にもちらほら使われていたので、このたび読めてよかったです。
かのこちゃんは、小学1年生。両親と老犬の玄三郎、猫のマドレーヌとともに、小さな庭のあるおうちに住む女の子です。好奇心旺盛なかのこちゃん、小学校で出会った「刎頚の友」すずちゃん、プール、夏休みの自由研究。だいぶ懐かしいシチュエーションをたどりながら、物語は《かのこちゃん視点》と《マドレーヌ視点》で交互に語られていきます。
特筆すべきは《マドレーヌ視点》の第2章、第4章。猫たちの間で「マドレーヌ夫人」と呼ばれ、敬愛されているマドレーヌは、あろうことか犬の玄三郎と夫婦関係にあるんだけれども(あ、精神面で。ひどく珍しいことに言語が通じ、心が通じている犬と猫のカップルなのです)、この夫婦のいたわりあいがなんとも温かく、切ない。身体の衰えが目立つ玄三郎をハラハラと見守るしかないマドレーヌ、このあたりになるともう「猫と犬」というよりは……おだやかな年月を共に重ねてきた老夫婦の趣き。
玄三郎とマドレーヌみたいな夫婦になりたいよ!?
それから、マドレーヌの視点から描写されるかのこちゃんの可愛いことといったら。就学直前まで指しゃぶりの癖が抜けなかった小さなかのこちゃん、その子が小学校にあがって毎日いきいきと遊び、賢くなっていくさま。なんだか親戚のおねえさん感覚で(おばさん、ではない!)愛しく読みすすめてしまいました。
ああ、面白かった。万城目学もっと読みたいな。そういえば、かのこちゃんが宿題で自分の名前の由来について調べることになったとき、お父さんが「そう名付けるよう、鹿に言われたから」と語るトンデモな場面がありますが、これってタイトルだけ見て知っている『鹿男あをによし』に何か関係が……? 次はこれかな?
- かのこちゃんとマドレーヌ夫人 (角川文庫)/万城目 学
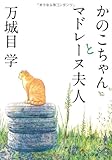
- ¥500
- Amazon.co.jp