金の瞳のリゼ 第2章 その1
第2章です。
ACT 2 サリーとローレンス卿
ぼくはしばらく台所に残り、モリス夫人がハーブティーを用意してくれるのを待つことにした。
「もうすぐですよ。茶器はミスター・アーノルドのお気に入りの、ボーンチャイナにしましょうね」
やがて、ハーブの淡く甘いかおりが漂い始めた時。
「おはようございます、ミセス・ハリエット! お仕立てものを届けに来ましたぁ!」
明るい声がして、台所の勝手口が開いた。
涼しい風とともに、茶色の髪の若い娘が顔を出す。
「あら、おはよう、サリー。早いねえ」
ハウスメイドのメグより二、三才くらい年上だろうか。サリーと呼ばれた娘は、何枚ものシーツやテーブルクロスをきちんと畳んで積み重ねた大きなかごを抱えていた。
質素なブルーグレーのドレスに洗いざらしのエプロン、化粧っ気もなく、髪はシンプルなシニョンにまとめただけのその娘に、ぼくはどこか見覚えがあるような気がした。子鹿のような茶色の眼と、鼻のあたまに薄く散ったそばかすが愛らしい。
モリス夫人はぽよぽよと弾むような足取りでサリーの前へ行き、かごを受け取った。
「おやまあ、あんた、これ全部仕上げちまったのかい?」
「もちろん! だって、金曜までに終わらせたら手間賃はずんでくれるって、ヘッティおばさん、言ったじゃない!」
「そりゃ言ったけど、サリー、今日はまだ水曜だよ」
かぎ裂きやほころびがきちんと繕われているか、ひとつひとつチェックしながら、モリス夫人は苦笑した。
「うちみたいに若い殿方を何人もお世話する下宿屋じゃあ、毎日山のように繕い物が出るから、仕事が速いのは大助かりだけどねえ」
こういう働く女性たちのおしゃべりの場に、男がいるのはよろしくない。ぼくはふたりに軽く挨拶をして、手ぶりでモリス夫人に「お茶が用意できたら上へ届けて」と合図すると、そのまま台所を立ち去ることにした。
――でも、誰だっけ、あの娘(こ)。たしかにどこかで見た気がするんだが。
「あんまり根を詰めすぎるんじゃないよ、サリー。体をこわしちまったら、元も子もないじゃないか」
モリス夫人が声をひそめるようにして、娘に忠告している。
「だいたいあんた、もうこんなに働かなくたっていいはずだろ? それともローレンス卿は、あんたにろくすっぽお手当をくれないのかい?」
「ううん、そんなことないよ。あたしひとりが食べてくには、充分すぎるくらいもらってる。家だって、ピカデリー広場のそばにすてきなコテージを借りてくれたし」
――ああ、そうか。
あのサリーという娘をどこで見たか、思い出した。数ヶ月前まで『王冠とアヒル』亭にいた、娼婦たちのひとりだ。
その時は派手に化粧をして、たいがいの娼婦がそうするように、カミーユ・マリとフランス風の源氏名を名乗っていた。そうか、あの娘の本名はサリーというのか。
会話から察するに、彼女はローレンス卿という紳士の囲われ者になったようだ。
娼婦たちにとって、金持ちの紳士の愛人になることは、たいそうな出世だ。衣食住の面倒をすべてみてもらえるし、なにより夜ごとに街へ出て、不特定多数の男の相手をしなくていい。
だが、紳士の囲われ者になっているのにまだ繕い物の賃仕事をしているなんて、それも妙な話だ。
「でもね、あたし、あの人からもらうお金は少しでも多く貯金しておきたいの」
思いがけない一言を聞いて、ぼくは思わず足を止めた。
貯金だって? 紳士の愛人ってのは、パトロンの金を湯水のように使い、ひとりでも多くの男を破産させるのを至上命題としているんじゃないのか?
「だってあの人、ほんとは自分の自由になるお金なんか、1ペニーもないのよ。卿(サー)だの男爵閣下だのって呼ばれてても、財産はみんな、奥さんの持参金と実家からの援助なんだもの。だからね、あたしも少しでも働いてお金貯めて、あの人の手助けがしたいんだ」
静かな言葉には、彼女の真心があふれていた。
――ぼくにはわかる。嘘が商売のぺてん師だからね。
貴顕の紳士が貧しい若い娘にささやく睦言には、一〇にひとつも真実なんかありはしない。生き馬の目を抜くロンドンで娼婦として生きてきたサリーにだって、それは充分にわかっているだろう。
それでも彼女は、ローレンス卿なる男の言葉を本気で信じているようだ。
「なのに彼、無理してあたしのためにコテージを借りて、ジムの薬代まで出してくれてるの」
「ジムのって……、じゃあ、まさか――」
「そうよ。ジムもいっしょに住まわせてもらってる」
「そうかい……。そりゃ良かったねえ。姉さんと弟がいっしょに住めるなら、安心だ。ローレンス卿は本当にあんたのことを大事にしてくれてるんだねえ」
ため息をつくように、モリス夫人が言った。彼女もローレンス卿の親切心を信頼したのか、それとも恋は盲目と、忠告するのを諦めたのか。
「だったらなおさら、あんたも体を大切にしなきゃ。繕い物に精出しすぎて、眼がしょぼしょぼの婆さんみたいになっちまったら、優しくてハンサムなローレンス卿に嫌われちまうよ?」
「それも大丈夫。あの人ね、あたしのどこに惚れたのって訊いたら、一番はあたしが作るミンスパイだって言ったのよ! あたしの作るパイはロンドン一だって!」
「おやまあ! たしかにそれなら大丈夫だ!」
モリス夫人もなかば呆れたように笑った。
「何が安心って、男は胃袋で惚れさせるのが一番だよ。年食って髪が真っ白になって、おっぱいが萎びちまっても、パイの味は変わらないからねえ」
「あら、彼、ほかにもいっぱい誉めてくれたわよ。いつも楽しそうに笑ってるとこがいいとか、あたしの歌を聴くだけで一〇才も若返った気分になるとか!」
「はいはい、ごちそうさま。おのろけ話はもうたくさんだよ。ほら、今週の手間賃。約束どおり上乗せしておいたからね。次は月曜日に来ておくれ」
ちゃり、ちゃりん、とわずかな硬貨の音がする。
「それと、これはジミー坊やにね」
「キドニーパイじゃない! いいの!?」
「ああ。あんたのミンスパイはロンドン一だろうけど、あたしのキドニーパイは英国一さ。これを食べれば、ジムもきっと元気になるよ」
「ありがとう、ヘッティおばさん! ありがと、ほんとに大好きよ!」
そしてサリーは、入ってきた時と同じく、風のように身軽に台所を飛び出していった。
台所は急に静まりかえり、モリス夫人のかすかなため息だけが聞こえる。
――ちょっと興味深い話だったな。
サリーが言っていたことがすべて本当なら、ロンドンじゃ滅多にない純愛だ。
彼女が騙されているのでなければいいが。他人事ながら、そう思ってしまう。
すると。
「今どき、珍しいくらい良い話じゃないか。あのサリーって娘が騙されてんじゃなきゃ、いいけどな」
ぼくの背後で、いきなり声がした。
「うわっ!?」
「男爵閣下のローレンス卿……て言うと、ミドルトン男爵かな? ローレンス・パウエル・ウェイクスリー・オブ・ミドルトン。ほかに誰かいたっけ」
「ね、ねぇ――いや、兄さん!?」
いったいいつの間に二階から降りてきたのか、姉さんがぼくのすぐ後ろに立っていた。
……驚いた。足音ひとつ聞こえなかった。
姉さんはすでにきちんと身支度を整え、髪もいつものように黒いサテンのリボンでひとつに括っている。クラヴァットは結んでいないが、昨夜、ぼくがつけてしまった愛撫の跡はハイカラーのワイシャツで上手に隠していた。
「おまえが台所に降りていったきり、戻ってこねえからさ。きっとミセス・ハリエットにりんごの甘煮でも頼んでるんだろうと思って。そろそろできるころだろ?」
ああ、まったく。ぼくの浅知恵なんか、姉さんにはとっくの昔にお見通しってわけだ。
「ミドルトン男爵はかなりいい年齢(とし)で、ロンドンの社交界より田舎暮らしが好きな典型的な地方領主だったと思うけど。だから、社交シーズンになってもロンドンに来るのはレディ・ミドルトンと息子のヴィンセントだけで、本人は田舎の領地に引っ込んだままだったはずだけどな」
「よく覚えてるね、兄さん」
「おまえもこのくらいは覚えとけ。なにがメシのタネになるか、わかんねえんだぞ」
「だからと言って、れっきとした紳士が台所で女中の話を盗み聞きなんて、誉められたことじゃございませんよ。ミスター・グレンフィールド」
しかめっ面のモリス夫人が廊下に顔を出した。
「ご兄弟揃って、なんてお行儀が悪いまねをなさるんです。お茶がご入り用でしたら、卓上鈴を鳴らしてメグをお呼びになってくださいまし」
「すまないね、ミセス・ハリエット。つい、待ちきれなくなっちゃって。あなたの作るアップルパイは世界一だから」
「ほんとにもう、お口がお上手でらっしゃいますこと。しかたありませんね、少しお待ちくださいな」
礼儀作法にやかましいベテラン家政婦も、アーノルド・グレンフィールド氏の人懐っこい無邪気な笑顔にはかなわない。モリス夫人はため息をつきながらいったん台所へ引っ込み、すぐにお茶とりんごの甘煮、おまけにスコーンまでワゴンに載せて戻ってきた。
「ねえ、ミセス・ヘッティ。あのサリーって娘、そんなに縫い物が上手なのかい? ならオレも、少し頼みたいものがあるんだけど」
「立ったままお菓子をつまみ食いなさってはいけません、ミスター・アーノルド」
ぼくたちを部屋に連れ戻すにはこれしか方法がないと思ったのか、モリス夫人は自分でワゴンを押して歩き出した。
そうやって二階のぼくたちの部屋に戻るまでの短いあいだに、姉さんはサリーのことをいろいろと聞き出してしまった。
もちろん、ぼくも協力したよ。姉さんが話を引き出す時間を稼ぐために、ワゴンを抱えて階段をあがる時、わざともたついたりしてさ。
ふつう、こういう時には男の従僕が呼ばれるものなんだが、
「いいよ、ミセス・モリス。ぼくが運ぶよ。スミザスも忙しいだろ? こんなことくらいでいちいち彼を呼んだら気の毒だ」
で、結局、従僕に運ばせるより二倍近い時間をかけて階段を登ってみたりして。
「ふうん、そうなんだ……。サリーは弟とふたり暮らしなんだね」
「ええ、弟のジムもそれはいい子で――。頭の良い子なんですよ。教会の慈善学校じゃあ、計算でも作文でもいつも一番で、先生に誉めていただいてるとか。ただ可哀想なことに、先月、馬車に轢かれて……」
「怪我したのかい?」
モリス夫人は涙をそっと抑えながら、小さくうなずいた。
「命はなんとか助かったんですけどね。足が……。可哀想に、あの子はまだ一〇になったばっかりだっていうのに……」
近年、人口が爆発的に増えているロンドンでは、それに比例して道の混雑もかなりひどくなっている。
貴族が乗る二頭立て、四頭立ての箱馬車に、二人乗りで車高が高く、安定感のないフェートン馬車。近郊から運ばれる野菜やビール樽を満載した荷馬車ものろのろ通る。速度も大きさもばらばらの車が道幅一杯に広がって、車体を擦りあわせんばかりにすり抜けようとするものだから、歩行者はおちおち道を横断することもできない。
馬車どうしの衝突事故や、歩行者が馬車の車輪に巻き込まれる交通事故は、日常茶飯事だった。
「お医者さまは、栄養をつけさせて、空気の良いところでゆっくり静養すれば、また歩けるようになるっておっしゃったんですけどね……」
そんな金、イーストエンドの娼婦に工面できるはずもない。
「サリーは今まで、ずっと苦労してきたんですよ。そりゃあ、イーストエンド育ちで苦労してない娘なんかいやしませんけれどね。でも、サリーはほんとに家族思いのいい娘なんです。小さい頃から働きづめで、親が死んでからは、自分の体を売って弟の面倒を見てきた。あの娘がやっと掴んだ幸せを、神さまにも、他の誰にも、そっとしておいてもらいたいんですよ……」
一〇才にもならない我が子を女衒に売り飛ばし、その金で飲んだくれる人でなしの親も多いなか、サリーはずっと幼い弟を守り続けてきたのか。かつてのリゼ姉さんのように。
だからだろうか。体を売り、教会の教えに背いて妻子ある男の囲われ者になり、世間から後ろ指をさされる女になっても、それでもサリーがあんなに明るく笑っていたのは。
愛する誰かを守ろうとする時、人はもっとも強くなる。どんな困難にも立ち向かう勇気を持てる。
「相手がローレンス・パウエル卿だっていうのは、たしかなのかい? まさか誰かが名前を騙ってるとか――」
「いいえ、それはございません」
姉さんの問いかけに、モリス夫人はきっぱりと断言した。
「私も心配になって、一度こっそり顔を確かめに行ったんですよ。間違いなく、ミドルトン男爵閣下ご本人でした。私もミセス・オルソンも、男爵閣下のことは若いころからよく存じ上げておりますから。閣下がご結婚なさってから十数年はお会いしておりませんでしたが、間違いございません」
モリス夫人やオルソン夫人が若き日に男爵閣下とどこで知り合いになったのかは、ぼくも姉さんも追求しなかった。
「それでは、お茶とお菓子のおかわりが欲しい時には、もうご自分で台所まで催促にいらしたりせずに、卓上鈴でメイドをお呼びくださいましね」
もう一度しっかり釘を刺してモリス夫人が居間を出ていくと、姉さんは待ちきれないようにさっそくテーブルについた。
ぼくはその左に立ち、いつもどおり給仕役を勤めながら、姉さんに尋ねた。
「なに考えてるの? 姉さん」
「別に、なにも。――あ、クロテッドクリーム取って」
「はい。ジャムは黒すぐりか。ぼくもスコーン一個もらおうかな。……だから、あのサリーって娘のこと。さっきから、やけに気にしてたじゃないか」
姉さんがこんなふうに誰かの話に興味を示す時は、たいがい面白い“仕事”のアイディアを思いついた時だ。
だが、ぼくの予想に反して、姉さんはひどく退屈そうな表情で言った。
「サリーが言ってたろ。ローレンス卿、ミドルトン男爵は、肩書きは持ってるけど、財布の中身は素寒貧だって。おおかた、夫人は土地成金か新興商人の出だろ。破産寸前の独身貴族を多額の持参金で釣って結婚して、レディの称号を手に入れたってわけさ。ま、よくある話だよな」
「うん、そうだね――」
男爵家の家計はすべて夫人の実家の援助によってまかなわれ、男爵は夫人に頭があがらない。その憂さを、外に若い女を囲うことによって晴らしている、か。たしかに、そんな話は英国中にごろごろしている。
「そんな貧乏貴族、どこを突っついたって金になんかなるもんか。あほらしい。興味持つだけ、時間の無駄。――あ、こら! このスコーンはミセス・モリスがオレのために焼いてくれたの! おまえにはあげない!」
「えー、いいじゃないか。一個くらい食べさせてよ」
「だめ! おまえみたいな節操なしの助平には、一個もやらない!!」
続きはまた今度。
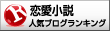
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
ACT 2 サリーとローレンス卿
ぼくはしばらく台所に残り、モリス夫人がハーブティーを用意してくれるのを待つことにした。
「もうすぐですよ。茶器はミスター・アーノルドのお気に入りの、ボーンチャイナにしましょうね」
やがて、ハーブの淡く甘いかおりが漂い始めた時。
「おはようございます、ミセス・ハリエット! お仕立てものを届けに来ましたぁ!」
明るい声がして、台所の勝手口が開いた。
涼しい風とともに、茶色の髪の若い娘が顔を出す。
「あら、おはよう、サリー。早いねえ」
ハウスメイドのメグより二、三才くらい年上だろうか。サリーと呼ばれた娘は、何枚ものシーツやテーブルクロスをきちんと畳んで積み重ねた大きなかごを抱えていた。
質素なブルーグレーのドレスに洗いざらしのエプロン、化粧っ気もなく、髪はシンプルなシニョンにまとめただけのその娘に、ぼくはどこか見覚えがあるような気がした。子鹿のような茶色の眼と、鼻のあたまに薄く散ったそばかすが愛らしい。
モリス夫人はぽよぽよと弾むような足取りでサリーの前へ行き、かごを受け取った。
「おやまあ、あんた、これ全部仕上げちまったのかい?」
「もちろん! だって、金曜までに終わらせたら手間賃はずんでくれるって、ヘッティおばさん、言ったじゃない!」
「そりゃ言ったけど、サリー、今日はまだ水曜だよ」
かぎ裂きやほころびがきちんと繕われているか、ひとつひとつチェックしながら、モリス夫人は苦笑した。
「うちみたいに若い殿方を何人もお世話する下宿屋じゃあ、毎日山のように繕い物が出るから、仕事が速いのは大助かりだけどねえ」
こういう働く女性たちのおしゃべりの場に、男がいるのはよろしくない。ぼくはふたりに軽く挨拶をして、手ぶりでモリス夫人に「お茶が用意できたら上へ届けて」と合図すると、そのまま台所を立ち去ることにした。
――でも、誰だっけ、あの娘(こ)。たしかにどこかで見た気がするんだが。
「あんまり根を詰めすぎるんじゃないよ、サリー。体をこわしちまったら、元も子もないじゃないか」
モリス夫人が声をひそめるようにして、娘に忠告している。
「だいたいあんた、もうこんなに働かなくたっていいはずだろ? それともローレンス卿は、あんたにろくすっぽお手当をくれないのかい?」
「ううん、そんなことないよ。あたしひとりが食べてくには、充分すぎるくらいもらってる。家だって、ピカデリー広場のそばにすてきなコテージを借りてくれたし」
――ああ、そうか。
あのサリーという娘をどこで見たか、思い出した。数ヶ月前まで『王冠とアヒル』亭にいた、娼婦たちのひとりだ。
その時は派手に化粧をして、たいがいの娼婦がそうするように、カミーユ・マリとフランス風の源氏名を名乗っていた。そうか、あの娘の本名はサリーというのか。
会話から察するに、彼女はローレンス卿という紳士の囲われ者になったようだ。
娼婦たちにとって、金持ちの紳士の愛人になることは、たいそうな出世だ。衣食住の面倒をすべてみてもらえるし、なにより夜ごとに街へ出て、不特定多数の男の相手をしなくていい。
だが、紳士の囲われ者になっているのにまだ繕い物の賃仕事をしているなんて、それも妙な話だ。
「でもね、あたし、あの人からもらうお金は少しでも多く貯金しておきたいの」
思いがけない一言を聞いて、ぼくは思わず足を止めた。
貯金だって? 紳士の愛人ってのは、パトロンの金を湯水のように使い、ひとりでも多くの男を破産させるのを至上命題としているんじゃないのか?
「だってあの人、ほんとは自分の自由になるお金なんか、1ペニーもないのよ。卿(サー)だの男爵閣下だのって呼ばれてても、財産はみんな、奥さんの持参金と実家からの援助なんだもの。だからね、あたしも少しでも働いてお金貯めて、あの人の手助けがしたいんだ」
静かな言葉には、彼女の真心があふれていた。
――ぼくにはわかる。嘘が商売のぺてん師だからね。
貴顕の紳士が貧しい若い娘にささやく睦言には、一〇にひとつも真実なんかありはしない。生き馬の目を抜くロンドンで娼婦として生きてきたサリーにだって、それは充分にわかっているだろう。
それでも彼女は、ローレンス卿なる男の言葉を本気で信じているようだ。
「なのに彼、無理してあたしのためにコテージを借りて、ジムの薬代まで出してくれてるの」
「ジムのって……、じゃあ、まさか――」
「そうよ。ジムもいっしょに住まわせてもらってる」
「そうかい……。そりゃ良かったねえ。姉さんと弟がいっしょに住めるなら、安心だ。ローレンス卿は本当にあんたのことを大事にしてくれてるんだねえ」
ため息をつくように、モリス夫人が言った。彼女もローレンス卿の親切心を信頼したのか、それとも恋は盲目と、忠告するのを諦めたのか。
「だったらなおさら、あんたも体を大切にしなきゃ。繕い物に精出しすぎて、眼がしょぼしょぼの婆さんみたいになっちまったら、優しくてハンサムなローレンス卿に嫌われちまうよ?」
「それも大丈夫。あの人ね、あたしのどこに惚れたのって訊いたら、一番はあたしが作るミンスパイだって言ったのよ! あたしの作るパイはロンドン一だって!」
「おやまあ! たしかにそれなら大丈夫だ!」
モリス夫人もなかば呆れたように笑った。
「何が安心って、男は胃袋で惚れさせるのが一番だよ。年食って髪が真っ白になって、おっぱいが萎びちまっても、パイの味は変わらないからねえ」
「あら、彼、ほかにもいっぱい誉めてくれたわよ。いつも楽しそうに笑ってるとこがいいとか、あたしの歌を聴くだけで一〇才も若返った気分になるとか!」
「はいはい、ごちそうさま。おのろけ話はもうたくさんだよ。ほら、今週の手間賃。約束どおり上乗せしておいたからね。次は月曜日に来ておくれ」
ちゃり、ちゃりん、とわずかな硬貨の音がする。
「それと、これはジミー坊やにね」
「キドニーパイじゃない! いいの!?」
「ああ。あんたのミンスパイはロンドン一だろうけど、あたしのキドニーパイは英国一さ。これを食べれば、ジムもきっと元気になるよ」
「ありがとう、ヘッティおばさん! ありがと、ほんとに大好きよ!」
そしてサリーは、入ってきた時と同じく、風のように身軽に台所を飛び出していった。
台所は急に静まりかえり、モリス夫人のかすかなため息だけが聞こえる。
――ちょっと興味深い話だったな。
サリーが言っていたことがすべて本当なら、ロンドンじゃ滅多にない純愛だ。
彼女が騙されているのでなければいいが。他人事ながら、そう思ってしまう。
すると。
「今どき、珍しいくらい良い話じゃないか。あのサリーって娘が騙されてんじゃなきゃ、いいけどな」
ぼくの背後で、いきなり声がした。
「うわっ!?」
「男爵閣下のローレンス卿……て言うと、ミドルトン男爵かな? ローレンス・パウエル・ウェイクスリー・オブ・ミドルトン。ほかに誰かいたっけ」
「ね、ねぇ――いや、兄さん!?」
いったいいつの間に二階から降りてきたのか、姉さんがぼくのすぐ後ろに立っていた。
……驚いた。足音ひとつ聞こえなかった。
姉さんはすでにきちんと身支度を整え、髪もいつものように黒いサテンのリボンでひとつに括っている。クラヴァットは結んでいないが、昨夜、ぼくがつけてしまった愛撫の跡はハイカラーのワイシャツで上手に隠していた。
「おまえが台所に降りていったきり、戻ってこねえからさ。きっとミセス・ハリエットにりんごの甘煮でも頼んでるんだろうと思って。そろそろできるころだろ?」
ああ、まったく。ぼくの浅知恵なんか、姉さんにはとっくの昔にお見通しってわけだ。
「ミドルトン男爵はかなりいい年齢(とし)で、ロンドンの社交界より田舎暮らしが好きな典型的な地方領主だったと思うけど。だから、社交シーズンになってもロンドンに来るのはレディ・ミドルトンと息子のヴィンセントだけで、本人は田舎の領地に引っ込んだままだったはずだけどな」
「よく覚えてるね、兄さん」
「おまえもこのくらいは覚えとけ。なにがメシのタネになるか、わかんねえんだぞ」
「だからと言って、れっきとした紳士が台所で女中の話を盗み聞きなんて、誉められたことじゃございませんよ。ミスター・グレンフィールド」
しかめっ面のモリス夫人が廊下に顔を出した。
「ご兄弟揃って、なんてお行儀が悪いまねをなさるんです。お茶がご入り用でしたら、卓上鈴を鳴らしてメグをお呼びになってくださいまし」
「すまないね、ミセス・ハリエット。つい、待ちきれなくなっちゃって。あなたの作るアップルパイは世界一だから」
「ほんとにもう、お口がお上手でらっしゃいますこと。しかたありませんね、少しお待ちくださいな」
礼儀作法にやかましいベテラン家政婦も、アーノルド・グレンフィールド氏の人懐っこい無邪気な笑顔にはかなわない。モリス夫人はため息をつきながらいったん台所へ引っ込み、すぐにお茶とりんごの甘煮、おまけにスコーンまでワゴンに載せて戻ってきた。
「ねえ、ミセス・ヘッティ。あのサリーって娘、そんなに縫い物が上手なのかい? ならオレも、少し頼みたいものがあるんだけど」
「立ったままお菓子をつまみ食いなさってはいけません、ミスター・アーノルド」
ぼくたちを部屋に連れ戻すにはこれしか方法がないと思ったのか、モリス夫人は自分でワゴンを押して歩き出した。
そうやって二階のぼくたちの部屋に戻るまでの短いあいだに、姉さんはサリーのことをいろいろと聞き出してしまった。
もちろん、ぼくも協力したよ。姉さんが話を引き出す時間を稼ぐために、ワゴンを抱えて階段をあがる時、わざともたついたりしてさ。
ふつう、こういう時には男の従僕が呼ばれるものなんだが、
「いいよ、ミセス・モリス。ぼくが運ぶよ。スミザスも忙しいだろ? こんなことくらいでいちいち彼を呼んだら気の毒だ」
で、結局、従僕に運ばせるより二倍近い時間をかけて階段を登ってみたりして。
「ふうん、そうなんだ……。サリーは弟とふたり暮らしなんだね」
「ええ、弟のジムもそれはいい子で――。頭の良い子なんですよ。教会の慈善学校じゃあ、計算でも作文でもいつも一番で、先生に誉めていただいてるとか。ただ可哀想なことに、先月、馬車に轢かれて……」
「怪我したのかい?」
モリス夫人は涙をそっと抑えながら、小さくうなずいた。
「命はなんとか助かったんですけどね。足が……。可哀想に、あの子はまだ一〇になったばっかりだっていうのに……」
近年、人口が爆発的に増えているロンドンでは、それに比例して道の混雑もかなりひどくなっている。
貴族が乗る二頭立て、四頭立ての箱馬車に、二人乗りで車高が高く、安定感のないフェートン馬車。近郊から運ばれる野菜やビール樽を満載した荷馬車ものろのろ通る。速度も大きさもばらばらの車が道幅一杯に広がって、車体を擦りあわせんばかりにすり抜けようとするものだから、歩行者はおちおち道を横断することもできない。
馬車どうしの衝突事故や、歩行者が馬車の車輪に巻き込まれる交通事故は、日常茶飯事だった。
「お医者さまは、栄養をつけさせて、空気の良いところでゆっくり静養すれば、また歩けるようになるっておっしゃったんですけどね……」
そんな金、イーストエンドの娼婦に工面できるはずもない。
「サリーは今まで、ずっと苦労してきたんですよ。そりゃあ、イーストエンド育ちで苦労してない娘なんかいやしませんけれどね。でも、サリーはほんとに家族思いのいい娘なんです。小さい頃から働きづめで、親が死んでからは、自分の体を売って弟の面倒を見てきた。あの娘がやっと掴んだ幸せを、神さまにも、他の誰にも、そっとしておいてもらいたいんですよ……」
一〇才にもならない我が子を女衒に売り飛ばし、その金で飲んだくれる人でなしの親も多いなか、サリーはずっと幼い弟を守り続けてきたのか。かつてのリゼ姉さんのように。
だからだろうか。体を売り、教会の教えに背いて妻子ある男の囲われ者になり、世間から後ろ指をさされる女になっても、それでもサリーがあんなに明るく笑っていたのは。
愛する誰かを守ろうとする時、人はもっとも強くなる。どんな困難にも立ち向かう勇気を持てる。
「相手がローレンス・パウエル卿だっていうのは、たしかなのかい? まさか誰かが名前を騙ってるとか――」
「いいえ、それはございません」
姉さんの問いかけに、モリス夫人はきっぱりと断言した。
「私も心配になって、一度こっそり顔を確かめに行ったんですよ。間違いなく、ミドルトン男爵閣下ご本人でした。私もミセス・オルソンも、男爵閣下のことは若いころからよく存じ上げておりますから。閣下がご結婚なさってから十数年はお会いしておりませんでしたが、間違いございません」
モリス夫人やオルソン夫人が若き日に男爵閣下とどこで知り合いになったのかは、ぼくも姉さんも追求しなかった。
「それでは、お茶とお菓子のおかわりが欲しい時には、もうご自分で台所まで催促にいらしたりせずに、卓上鈴でメイドをお呼びくださいましね」
もう一度しっかり釘を刺してモリス夫人が居間を出ていくと、姉さんは待ちきれないようにさっそくテーブルについた。
ぼくはその左に立ち、いつもどおり給仕役を勤めながら、姉さんに尋ねた。
「なに考えてるの? 姉さん」
「別に、なにも。――あ、クロテッドクリーム取って」
「はい。ジャムは黒すぐりか。ぼくもスコーン一個もらおうかな。……だから、あのサリーって娘のこと。さっきから、やけに気にしてたじゃないか」
姉さんがこんなふうに誰かの話に興味を示す時は、たいがい面白い“仕事”のアイディアを思いついた時だ。
だが、ぼくの予想に反して、姉さんはひどく退屈そうな表情で言った。
「サリーが言ってたろ。ローレンス卿、ミドルトン男爵は、肩書きは持ってるけど、財布の中身は素寒貧だって。おおかた、夫人は土地成金か新興商人の出だろ。破産寸前の独身貴族を多額の持参金で釣って結婚して、レディの称号を手に入れたってわけさ。ま、よくある話だよな」
「うん、そうだね――」
男爵家の家計はすべて夫人の実家の援助によってまかなわれ、男爵は夫人に頭があがらない。その憂さを、外に若い女を囲うことによって晴らしている、か。たしかに、そんな話は英国中にごろごろしている。
「そんな貧乏貴族、どこを突っついたって金になんかなるもんか。あほらしい。興味持つだけ、時間の無駄。――あ、こら! このスコーンはミセス・モリスがオレのために焼いてくれたの! おまえにはあげない!」
「えー、いいじゃないか。一個くらい食べさせてよ」
「だめ! おまえみたいな節操なしの助平には、一個もやらない!!」
続きはまた今度。
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
金の瞳のリゼ・ACT1 アーニーとセディ Part2
限定公開版をお読みの方も、続きはこちらから。
金の瞳のリゼ ACT1 アーニーとセディ Part2
翌朝。
いつもの時間にハウスメイドが朝食を届けに来ても、姉さんは自分の寝室から出てこなかった。
「おはようございます、ミスター・グレンフィールド。朝食のお飲物は、珈琲と紅茶のどちらになさいますか?」
つやつやのりんごのような頬をしたハウスメイドが運んできた真鍮のワゴンには、熱々のポリッジにポーチドエッグ、かりかりのベーコン、ソーセージ、かぶのポタージュスープ、ほうれん草のキッシュと、量も味もとても充実した朝食が載っている。焼きたてのパンにはバターとはちみつが添えてある。
この下宿の良いところは、第一に間借り人に対してよけいな詮索を一切しないこと、そして第二がこの食事だ。
「おはよう、メグ。そうだな、ぼくは珈琲をもらうよ」
「かしこまりました。それで、あのぅ……、もうお一方のミスター・グレンフィールドはまだおやすみでしょうか?」
「ああ、兄さんは……まだ寝てるんだ。その、ちょっと二日酔いでね」
――昨夜は、さすがにちょっと、やりすぎたかな。
だって姉さんがあんまり可愛く泣くから。
ぼくもつい抑えが効かなくなってしまって。はっと我に返った時には、姉さんは泣き濡れた頬を青ざめさせて、完全に意識を失っていた。
「まあ、珍しい。ミスター・アーノルドが二日酔いになるほどお酒を過ごされるなんて」
メグから見れば、ミスター・アーノルド・グレンフィールドは、酔っぱらって階段の下で寝こけていたり、若いメイドを卑猥なジョークでからかったり、すれ違いざまに彼女のお尻を撫でたりしない、まさに紳士の鑑だ。信じられないと思うのも無理はないだろう。
――言っておくが、ぼくだってメイドのお尻を触ったことなんかないよ! 深酒して階段を転げ落ちたことなら、二、三度あるけど。
「ここはもういいよ、メグ。兄さんの朝食は、ぼくが運ぶから」
「かしこまりました。では、失礼いたします」
軽く膝を曲げて可愛らしく一礼すると、メグはそそくさと部屋を出ていった。
貴婦人付きの小間使い(レディズ・メイド)と違って、彼女のような、中流家庭に雇われる雑働き女中(メイド・オブ・オールワークス)は、その名のとおり家の中のことを何でもかんでも引き受けなくてはならない。一分一秒だって手と足を休めているヒマはないのだ。
「さて、と。じゃあ、姉さんのご機嫌をうかがいに行こうかな」
こんがり焼けたキッシュを持って、ぼくは姉さんの寝室のドアをノックした。
「姉さん。――リゼ姉さん。もう起きてる?」
返事はない。
「姉さん、朝食だよ。ほら、姉さんの好きなほうれん草のキッシュもあるよ」
もう一度声をかけてから、ぼくはそうっとドアを開けた。
木目と落ち着いたローズグレーを基調にした寝室は、まだ窓に厚いカーテンが引かれ、かなり暗かった。
備え付けのベッドには、シーツに埋もれるようにして、くしゃくしゃに寝乱れたハニーブロンドが見える。
「まだ寝てるの? 姉さん」
近づいて優しく呼びかけると、姉さんは応えるようにゆっくりと寝返りをうった。
「おはよう、朝だよ。起きられる?」
「……セディ――」
シーツの波の合間から掠れた声がぼくを呼んだ。そして金色の瞳が、いささか焦点の合わないまま、ぼくを見上げる。
昨夜は、居間のソファーで意識を失った姉さんを、ぼくがこのベッドまで運んだ。本当ならそのまま同じベッドで眠って、もう一度愛し合いたかったんだけど。
「セディのばか」
枕から顔をあげようともせず、姉さんはひどく恨めしそうに言った。
「やだって、言ったのに……。もうやだ、やめろって、あんなに――」
うん。まあ……。それはぼくもちゃんと聞いたよ。
ぼくを睨む目が、うっすら涙ぐんでいる。
昨夜ぼくが着せた寝間着の襟元から覗く、姉さんの白い肌。そこには濃く薄く、いくつもの愛撫の痕が刻みつけられていた。ハイカラーのワイシャツとクラヴァットで隠れる位置ではあるものの、どんな行為の痕跡であるか、一目でわかる。
ああ、まったく。ぼくは最低の男だ。涙をこらえて薄紅く染まるその目元に、欲情してる。
「ごめん、姉さん。反省してる。今度はもっと優しくするから――」
泣き顔まで可愛い大切な恋人に、なだめるようにキスしようとすると。
「ばかやろッ! もう二度とするかッ!!」
身をかがめたぼくの顔面に、力いっぱい枕が叩きつけられた。
「おまえとはもう二度とキスもなんもしない! 出てけ、ばかっ!!」
枕やクッションが続けざまに飛んでくる。
「ご、ごめん、姉さん! ごめんってば!」
「うるさい! セディのばか、阿呆っ! 変態! ど助平!!」
姉さんは、ベッド回りにあるものを手当たり次第に投げつけてきた。
枕や室内スリッパよりずっと硬い、ヘアブラシや手鏡、革装幀の祈祷書なんかが飛んでくる前に、僕は這々の体で寝室を逃げ出した。
――やれやれ。姉さんのご機嫌はそうとう悪いらしい。
機嫌を直してもらうには、ほうれん草のキッシュ以上の贈り物が必要なようだ。
ぼくはひとり淋しく朝食を終えると、自分でワゴンを押して台所へ向かった。
「まあ、ミスター・セオドア。そんなことをなさらなくても、いつもどおり廊下に出しておいてくだされば、メグが片づけにまいりましたのに」
この下宿のキッチンを預かる家政婦兼料理人のハリエット・モリス夫人は、えくぼが魅力的な、たっぷりしたティーポットみたいに丸々としたご婦人だ。家主のオルソン夫人とは旧知の間柄だそうだ。
「いいんだよ、ミセス・モリス。実はあなたにお願いがあるんだ。また、りんごの甘煮を作ってくれないかな」
アップルパイの、パイ生地に詰める前のりんごの甘煮。特にモリス夫人が作るりんごの甘煮は、姉さんの一番の好物だ。
「メグから聞いてますよ。お兄さまが少しお加減を悪くされたようだとか。ええ、お待ちください。ちょうど昨日、パイを焼こうと思って買い込んでおいたんです」
モリス夫人は下宿人ひとりひとりの好みを正確に把握している。アーノルド・グレンフィールド氏が若い男性にしては珍しく、フルーツや甘いものが好きだということも。
「じゃあ、よろしく」
「あ、少しお待ちください、ミスター・セオドア」
台所を出ようとするぼくを、モリス夫人が呼び止めた。
「今、カモミールとローズマリーのお茶を用意します。このお茶で、お兄さまのお加減も良くなりますよ」
「……ありがとう」
カモミールとローズマリーってのはたしか、女性の冷え性や生理不順に効果があるハーブじゃなかったろうか。
やはり、若いハウスメイドはともかく、この下宿を切り盛りしているふたりの女性は、ぼくの兄アーノルド・グレンフィールドの正体に気づいているのかもしれない。
「ありがとう、ミセス・モリス。――世話をかけるね」
「どういたしまして。ですがそういう優しいお言葉は、私よりもどうぞ大切なお兄さまにおっしゃってあげてくださいまし」
モリス夫人は両手を腰に当て、ひどく怖い顔をしてぼくをじろりと睨み据えた。
「とかく殿方というものは、ご自分のパートナーの価値を軽んじがちです。一度、胸に手をあててよぉーくお考えになってごらんなさいまし。もし今、パートナーの方が忽然と消えてしまったら、自分ひとりだけで今までと同じ暮らしができるものかどうか。それをきちんとわきまえていたら、けして無体な真似はできないはずですよ」
「はい。……肝に銘じます」
世間の荒波を泳ぎ切ってきた女性の鋭い警告に、ぼくは唯々諾々とうなずくしかなかった。
第一章が終わったとこなので、ちょっと短いけど今回はここまで。続きはまた今度。
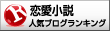
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
金の瞳のリゼ ACT1 アーニーとセディ Part2
翌朝。
いつもの時間にハウスメイドが朝食を届けに来ても、姉さんは自分の寝室から出てこなかった。
「おはようございます、ミスター・グレンフィールド。朝食のお飲物は、珈琲と紅茶のどちらになさいますか?」
つやつやのりんごのような頬をしたハウスメイドが運んできた真鍮のワゴンには、熱々のポリッジにポーチドエッグ、かりかりのベーコン、ソーセージ、かぶのポタージュスープ、ほうれん草のキッシュと、量も味もとても充実した朝食が載っている。焼きたてのパンにはバターとはちみつが添えてある。
この下宿の良いところは、第一に間借り人に対してよけいな詮索を一切しないこと、そして第二がこの食事だ。
「おはよう、メグ。そうだな、ぼくは珈琲をもらうよ」
「かしこまりました。それで、あのぅ……、もうお一方のミスター・グレンフィールドはまだおやすみでしょうか?」
「ああ、兄さんは……まだ寝てるんだ。その、ちょっと二日酔いでね」
――昨夜は、さすがにちょっと、やりすぎたかな。
だって姉さんがあんまり可愛く泣くから。
ぼくもつい抑えが効かなくなってしまって。はっと我に返った時には、姉さんは泣き濡れた頬を青ざめさせて、完全に意識を失っていた。
「まあ、珍しい。ミスター・アーノルドが二日酔いになるほどお酒を過ごされるなんて」
メグから見れば、ミスター・アーノルド・グレンフィールドは、酔っぱらって階段の下で寝こけていたり、若いメイドを卑猥なジョークでからかったり、すれ違いざまに彼女のお尻を撫でたりしない、まさに紳士の鑑だ。信じられないと思うのも無理はないだろう。
――言っておくが、ぼくだってメイドのお尻を触ったことなんかないよ! 深酒して階段を転げ落ちたことなら、二、三度あるけど。
「ここはもういいよ、メグ。兄さんの朝食は、ぼくが運ぶから」
「かしこまりました。では、失礼いたします」
軽く膝を曲げて可愛らしく一礼すると、メグはそそくさと部屋を出ていった。
貴婦人付きの小間使い(レディズ・メイド)と違って、彼女のような、中流家庭に雇われる雑働き女中(メイド・オブ・オールワークス)は、その名のとおり家の中のことを何でもかんでも引き受けなくてはならない。一分一秒だって手と足を休めているヒマはないのだ。
「さて、と。じゃあ、姉さんのご機嫌をうかがいに行こうかな」
こんがり焼けたキッシュを持って、ぼくは姉さんの寝室のドアをノックした。
「姉さん。――リゼ姉さん。もう起きてる?」
返事はない。
「姉さん、朝食だよ。ほら、姉さんの好きなほうれん草のキッシュもあるよ」
もう一度声をかけてから、ぼくはそうっとドアを開けた。
木目と落ち着いたローズグレーを基調にした寝室は、まだ窓に厚いカーテンが引かれ、かなり暗かった。
備え付けのベッドには、シーツに埋もれるようにして、くしゃくしゃに寝乱れたハニーブロンドが見える。
「まだ寝てるの? 姉さん」
近づいて優しく呼びかけると、姉さんは応えるようにゆっくりと寝返りをうった。
「おはよう、朝だよ。起きられる?」
「……セディ――」
シーツの波の合間から掠れた声がぼくを呼んだ。そして金色の瞳が、いささか焦点の合わないまま、ぼくを見上げる。
昨夜は、居間のソファーで意識を失った姉さんを、ぼくがこのベッドまで運んだ。本当ならそのまま同じベッドで眠って、もう一度愛し合いたかったんだけど。
「セディのばか」
枕から顔をあげようともせず、姉さんはひどく恨めしそうに言った。
「やだって、言ったのに……。もうやだ、やめろって、あんなに――」
うん。まあ……。それはぼくもちゃんと聞いたよ。
ぼくを睨む目が、うっすら涙ぐんでいる。
昨夜ぼくが着せた寝間着の襟元から覗く、姉さんの白い肌。そこには濃く薄く、いくつもの愛撫の痕が刻みつけられていた。ハイカラーのワイシャツとクラヴァットで隠れる位置ではあるものの、どんな行為の痕跡であるか、一目でわかる。
ああ、まったく。ぼくは最低の男だ。涙をこらえて薄紅く染まるその目元に、欲情してる。
「ごめん、姉さん。反省してる。今度はもっと優しくするから――」
泣き顔まで可愛い大切な恋人に、なだめるようにキスしようとすると。
「ばかやろッ! もう二度とするかッ!!」
身をかがめたぼくの顔面に、力いっぱい枕が叩きつけられた。
「おまえとはもう二度とキスもなんもしない! 出てけ、ばかっ!!」
枕やクッションが続けざまに飛んでくる。
「ご、ごめん、姉さん! ごめんってば!」
「うるさい! セディのばか、阿呆っ! 変態! ど助平!!」
姉さんは、ベッド回りにあるものを手当たり次第に投げつけてきた。
枕や室内スリッパよりずっと硬い、ヘアブラシや手鏡、革装幀の祈祷書なんかが飛んでくる前に、僕は這々の体で寝室を逃げ出した。
――やれやれ。姉さんのご機嫌はそうとう悪いらしい。
機嫌を直してもらうには、ほうれん草のキッシュ以上の贈り物が必要なようだ。
ぼくはひとり淋しく朝食を終えると、自分でワゴンを押して台所へ向かった。
「まあ、ミスター・セオドア。そんなことをなさらなくても、いつもどおり廊下に出しておいてくだされば、メグが片づけにまいりましたのに」
この下宿のキッチンを預かる家政婦兼料理人のハリエット・モリス夫人は、えくぼが魅力的な、たっぷりしたティーポットみたいに丸々としたご婦人だ。家主のオルソン夫人とは旧知の間柄だそうだ。
「いいんだよ、ミセス・モリス。実はあなたにお願いがあるんだ。また、りんごの甘煮を作ってくれないかな」
アップルパイの、パイ生地に詰める前のりんごの甘煮。特にモリス夫人が作るりんごの甘煮は、姉さんの一番の好物だ。
「メグから聞いてますよ。お兄さまが少しお加減を悪くされたようだとか。ええ、お待ちください。ちょうど昨日、パイを焼こうと思って買い込んでおいたんです」
モリス夫人は下宿人ひとりひとりの好みを正確に把握している。アーノルド・グレンフィールド氏が若い男性にしては珍しく、フルーツや甘いものが好きだということも。
「じゃあ、よろしく」
「あ、少しお待ちください、ミスター・セオドア」
台所を出ようとするぼくを、モリス夫人が呼び止めた。
「今、カモミールとローズマリーのお茶を用意します。このお茶で、お兄さまのお加減も良くなりますよ」
「……ありがとう」
カモミールとローズマリーってのはたしか、女性の冷え性や生理不順に効果があるハーブじゃなかったろうか。
やはり、若いハウスメイドはともかく、この下宿を切り盛りしているふたりの女性は、ぼくの兄アーノルド・グレンフィールドの正体に気づいているのかもしれない。
「ありがとう、ミセス・モリス。――世話をかけるね」
「どういたしまして。ですがそういう優しいお言葉は、私よりもどうぞ大切なお兄さまにおっしゃってあげてくださいまし」
モリス夫人は両手を腰に当て、ひどく怖い顔をしてぼくをじろりと睨み据えた。
「とかく殿方というものは、ご自分のパートナーの価値を軽んじがちです。一度、胸に手をあててよぉーくお考えになってごらんなさいまし。もし今、パートナーの方が忽然と消えてしまったら、自分ひとりだけで今までと同じ暮らしができるものかどうか。それをきちんとわきまえていたら、けして無体な真似はできないはずですよ」
「はい。……肝に銘じます」
世間の荒波を泳ぎ切ってきた女性の鋭い警告に、ぼくは唯々諾々とうなずくしかなかった。
第一章が終わったとこなので、ちょっと短いけど今回はここまで。続きはまた今度。
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
金の瞳のリゼ・続き ACT1 アーニーとセディ
「金の瞳のリゼ」 続き。やばそなところを切り落とした、短縮版です。ストーリー展開には影響ないので、ご安心を。
ACT 1 アーニーとセディ
「ああ、ちくしょう、また負けたぁっ!」
派手にカードをまき散らし、姉さんはばったりとテーブルに突っ伏した。
「だから言ったじゃないか。兄さんはカード賭博には向いてないって」
ぼくは笑いながらカードをまとめ、軽くシャッフルする。
「おまえ、いかさましてねーだろうな」
「兄さん相手にいかさまして、どうするの。兄さんの財布とぼくの財布は一緒だろ」
この人を「兄さん」「姉さん」と呼び分けるのも、もう慣れた。
今みたいに長めのシヴィルコートにクラヴァットで男装している時は「兄さん」、ドレス姿の時は「姉さん」だ。
……ぼくとしては、奇麗なドレス姿のほうがより嬉しいのだが。
ひげ面の無愛想な親爺さんが経営する居酒屋(タヴァーン)『王冠とアヒル』亭は、イーストエンドを含むテムズ河添いのロンドン・ドッグ地帯では、かなりランクが上のほうだ。オランダ産のジンやビールのほかに、金さえ払えば上物のブランデーも出してくれる。もちろん、真夜中にドーヴァーを越えてくる密輸品だが。料理もなかなか美味しく、ぼくたちのお気に入りだ。
煙草の煙が白く立ちこめ、キッチンの奥でスモークされる鴨の匂いがあふれる店内は、今夜もかなりの盛況だった。
あちこちのテーブルでカード賭博の小銭がやりとりされ、運良く儲けた男をカモろうとカウンターでは精一杯めかし込んだ娼婦たちが待ちかまえている。もうしばらくすれば、二階に設けられた休憩用の小部屋はどこもいっぱいになるだろう。
「親爺さん、おかわり。同じものね」
ぼくはブルゴーニュ産のブランデー、姉さんは甘いマデイラワインが好みだ。
「もう一度だ、セディ! もう一回!」
負けず嫌いの姉さんがしつこく食い下がる。
「いいよ、何度でも。ピケ? それともホイスト?」
――何度やっても結果は同じだと思うけどね。思ったことが全部顔に出る姉さんは、カード賭博には向いてないよ。
いつもはぼくよりずっと頭の回転が速くて、並の男など足下にも近寄れないほど度胸も思い切りも良い姉さんが、こうしてぼくとふたりで遊んでいる時だけは、まるで子どもみたいだ。
客を待つ娼婦たちが、ちゅっちゅっと唇を鳴らしてぼくたちの気を引こうとする。
ぼくは、今夜は用はないよ、と彼女らの胸元に銀貨を放ってやった。
「そいつで一杯やってなよ」
娼婦たちははしゃいできゃあっと歓声を上げた。一杯どころか、安物のジンならボトル五、六本は買える金額だ。
姉さん――ぼくの兄、アーノルド・グレンフィールドは物理的に彼女らの客になることはできないが、ぼくは何度かお世話になったことがある。上流階級の紳士どもの醜聞を手に入れるには彼女たちに聞くのが一番だし、ご婦人方をたらし込むためのベッドテクニックを教わるのにも、ね。
そう。
初めて出逢った時、無惨に刈られてしまった髪を汚いスカーフで隠し、つぎあてだらけのエプロンとスカートを着ていた貧民街の少女は、今は仕立ての良いシヴィルコートに磨き上げられたヘシアンブーツ、ジェットストーンのタイピンと、地味だが趣味の良い身なりをして、どこから見ても金に不自由しない都会の紳士だ。
もっともその衣服にも靴にも詰め物がしてあって、本当はほっそりとして華奢な姉さんのプロポーションを少しでも大柄に見せられるよう、工夫してあるのだが。
「女将、オレはもうワインはいいや。ホットトディ、作ってくれ」
低く抑えた作り声も、見事に男の声に聞こえる。
イーストエンド中の娼婦が羨むはちみつ色の髪だけは、ひと昔前に流行ったように、長く伸ばして黒のリボンでひとつに括っている。
これは、髪だけはもったいないから切らないでくれと、ぼくが必死に頼み込んだからだ。姉さんはいつも、背まで届く長い髪のブラッシングを面倒くさがっている。
「おまえみたいに短く切っちまったほうが、ずーっと便利だって。よけいな印象を残さずにすむし。女に戻ってドレスを着る時は、カツラかぶりゃいいんだから」
と、姉さんは言うけれど。
そんなの、ぼくは絶対に認められない。
この、天使の花冠みたいなハニーブロンドを短く刈り込んでしまうなんて、もったいなさすぎてバチが当たるよ。
こうして男のふりをするのは、姉さんが自分で言い出したことだ。
――一〇年前の、あの日。
父さんと母さんを共同墓地の片隅に葬ったあと、リゼはその足でまっすぐ教会の慈善箱へ向かった。
日曜のミサが行われる礼拝堂の後ろに置かれている大きな木箱は、教区に住む善男善女から寄付された古着や靴が入れてある。たいがいはひどくぼろぼろで、古着屋も買い取ってくれないようなシロモノだ。それでも、教区の婦人会の方々が大釜で洗濯――というよりぐらぐら煮立てて消毒してあるので、とりあえずは清潔だ。礼拝堂付きの助司祭に一言ことわれば、誰でもそこから好きなものを持っていくことができる。貧民街の路上生活者には、とてもありがたい箱なのだ。空っぽの時も多いが。
リゼは運良くその中から、膝につぎのあたったズボンと、はげちょろけのツィードのジャケットを見つけ出した。
「それ、ぼくに?」
「違う。オレが着るんだよ」
――オレ?
リゼの口から飛び出した言葉に、ぼくは耳を疑った。
「だってそれ、男物だよ。いくら髪が男の子みたいになっちゃったからって、リゼ姉さん……」
「姉さん、じゃない。兄ちゃんって、呼べ」
「……え?」
ぼくはあぜんとして、リゼを見た。
けれどリゼの目は、痛いくらい真剣だった。
「いいか。今からオレはおまえの兄さんだ。間違っても、リゼなんて呼ぶな」
「ど、どうして? なんでいきなり……」
「セディのばか。先月殺されたネリーのこと、おまえ、知らないのか?」
「ネリーって……、あ!」
可哀想なネリー。その名前に、ぼくは小さく息を呑んだ。
ネル・オブライエンは、飲んだくれの藪医者コナー・オブライエンのひとり娘だった。
ろくでなしの亭主に愛想を尽かして母親が出ていったあとも、父親のそばに残り、けなげに励まし続けていた。
だがある日、診療ミスから患者を死なせてしまったオブライエンが監獄にぶち込まれ、ネリーはたったひとりでイーストエンドに取り残された。そしてみながちょっと目を離した隙に、ネリーの姿は消えていた。
見つかったのは三日後。ネリーは全裸でテムズ河に浮かんだ。
身体中に残された傷痕が、ネリーがいかにむごたらしく玩ばれ、虫けらのように殺されたかを物語っていた。……可哀想なネリーは、まだ六才にもなっていなかった。
監獄から釈放されたオブライエンは変わり果てた娘の亡骸と対面することになり、翌日、街角のガス灯で首をくくった。
ぼくは唇を噛みしめ、うつむいた。
ネリーの死は、この街ではけして珍しい事件じゃない。
まともな大人だって職がなく、飢えてテムズ河に身投げするような時代だ。一方で特権階級はぶくぶくと肥え太り、歪んだ欲望のはけ口を捜している。そしてそいつらのたるんだ腹にぶらさがり、その涎を啜って生きている連中もいる。
大陸封鎖令によって島国イングランドを飢え死に寸前に追い込んだフランスの独裁者ナポレオン・ボナパルトは、ネルソン提督によって自慢の海軍を撃破され、自国民にも裏切られてエルバ島に流された。それでも彼は執念深く流刑地を脱出し、ふたたびイングランドに戦争を挑んできた。が、今度は陸の英雄ウェリントン将軍によって完膚無きまでにたたきのめされ、ふたたびセントヘレナ島に追いやられた。
これによって、長く続いたフランスとの戦争はようやく終了した。
英国は大勝利をおさめたはずだった。
けれど故国は、歴戦の勇者たちにあまりにも冷酷だった。大陸各地の戦線から戻ってきた兵士たちの大半は、もとの仕事に復帰することもできず、路上にあふれかえった。
仕事も金もなく、中には手足を失った者もいる。彼らのほとんどは浮浪者となり、あるいは路上強盗や追いはぎに身を落とす者もいた。
地方では地主による大規模な土地の囲い込み(エンクロージャー)が起き、自作農たちですら次々に先祖伝来の土地を奪われ、流浪の身となって大都市ロンドンへ押し寄せる。
王宮には若く清廉な女王陛下が君臨し、そのもとには綺羅星のごとく有能な政治家、外交官たちがつどう。けれど一歩街へ踏み出せば、道ばたには浮浪者があふれ、がりがりにやせ細った娼婦たちが今日の食事を手に入れるため、懸命に客をひく。捨てられた赤ん坊は野良犬の餌食になり、テムズ河に死体が浮かんでいない日はない。
大人ですらまともな職が得られないこんな時代、親を失った幼い子どもが真っ当に生きていける方法なんか、あるわけがない。
救貧院から幼い子どもが連れ出されるのなんて日常茶飯事、田舎から若い娘を騙して連れてくる大がかりな誘拐団もあると聞く。親もなく、自分の身を護るすべのない子どもらなんて、食い殺してくれと言わんばかりの存在なのだ。
そして、あらためて見つめると、リゼはとてもきれいな女の子だった。
ネズミ色のブラウスを着て、薄汚れていても、その肌は透きとおるように白い。甘い香りのするハニーブロンドと、そしてこの金色の瞳。
夜明けの太陽みたいな金色の瞳は、光の加減によって淡くけぶる琥珀色から透明なシトリントパーズにまで変化する。そして感情が激昂すると、まるで鋳造したてのぴかぴかの金貨みたいに輝くのだ。
こんなにきれいな女の子が、守ってくれる大人もなく、たったひとりでスラム街をうろついていたら。
もてあそんで殺してくださいと言っているようなものだ。
男物の衣服に着替え、仕上げに破れかけた鳥打ち帽を目深にかぶって、髪も顔も半分以上隠してしまうと、リゼはどこから見てもスラム街の薄汚れた悪ガキだった。
「えーと、アル、アーニー……。うん、アーニー。アーノルド」
ショーウィンドウに自分の姿を映して確かめながら、姉さんはつぶやいた。
「アーノルド。いい名前だろ。今日からオレは、アーノルド・グレンフィールドだ」
「――アーノルド」
「そうだ。おまえも、間違っても人前でオレのこと、『リゼ姉さん』なんて呼ぶなよ!」
「うん、わかったよ。ねぇ……兄さん」
ぼくは小さくうなずいた。
けれど本当は、悔しくてならなかった。
こんな恰好、リゼにはちっとも似合わない。
可愛くてきれいで、誰よりも頭のいいリゼは、本当はそれにふさわしい恰好をするべきなんだ。
やわらかなタフタのドレスにレースのショール、アーミンの縁取りがついたコート、金色の飾りボタンのブーツ。ふわふわのハニーブロンドには、シルクと真珠を編み込んで。
そういう姿で、笑いながら街を歩くべきなんだ。
でもぼくには、彼女にそれを与えてあげることができない。たった一枚のハンカチですら。
そしてリゼは、自分自身を守るため、薄汚いちんぴらのふりをしなくてはならないんだ。
……ぼくにもっと力があったなら。
リゼを守りきれるだけの、強く賢い、大人の男であったなら。
「どうした? セディ」
ふと気づくと、姉さんが心配そうにぼくの顔を覗き込んでいた。
「あんまり気にすんなよ。おまえが悪いわけじゃない。それにこのカッコだって、慣れればいいもんだぜ?」
「うん……、似合うよ。兄さん」
ぼくは力無く、笑顔を作って見せるしかなかった。
いつか……いつかきっと姉さんを、本来の姿に戻してあげる。
誰よりも美しい、完璧な貴婦人の姿に。本当のアネリーゼに。
ぼくはひそかにそう誓った。
その誓いは、今もぼくの胸にある。誰にも――姉さんにも、明かしたことはないけれど。
教会の軒下で数日間を過ごしたあと、やがてぼくたちはテムズ河に係留されたままの廃船にもぐり込んだ。
汚いし、ネズミは走り回るし、水漏れもする。いつ沈没するかわからない。それでも頭の上に天井があるだけ、ましだ。
その船がしばらくのあいだ、ぼくたちの家となった。
教会の慈善箱からもらってきた穴だらけのコートにふたりでくるまり、空腹を抱えて夜を過ごす。
そんな時でも、姉さんとふたりなら耐えられた。ぼくは姉さんを抱きしめ、姉さんのぬくもりがぼくをあたためてくれた。
生きていくために、なんでもやった。空き巣、置き引き、かっぱらい。美人局のまねごとまで。その日一日を生き延びるだけで、精一杯だった。
自分たちのしていることが悪いことかどうかなんて、考えている余裕すらなかった。
神様は死んだ後のことしか面倒を見てくれない。生きている人間は自分の食い扶持を稼ぐのが精一杯で、他人のことなどかまっていたら死んでしまう。ここはそういう街なのだ。
その中でぼくたちは、このイーストエンドで生きていくすべをひとつ、またひとつと学んでいった。たとえばいかさま賭博、たとえば鍵なしでも裏口のドアを開ける方法、たとえば理不尽な暴力に対抗するための、暴力。そして、知恵。
それでも最低限のルールは守った。自分たちより弱い者からは、けして奪わない。
路上で物乞いをする老人や幼い子どもたちには、たった一枚の銅貨が全財産だ。彼らは、昨日までのぼくたち自身だ。そんな人々からどうして奪うことができるだろう。
だけど、ぶくぶくと肥え太り、財布の重みでよたついているような特権階級から少々の金貨をかすめ取ったところで、連中は困るどころか金貨が減ったことにすら気づきはしないんだ。
何度も死にかけた。危うく巡査にとっつかまりそうになったこともある。
捕まったが最後、待っているのはタイバーン刑場での鞭打ちと工事現場での強制労働だ。
連中は女子どもにも容赦はない。路上で商売していたところを運悪く巡査に見つかった娼婦が、見せしめのために上半身を裸にされて、血だるまになるまで鞭打たれているのを、見たことがある。
――あんな目に遭うのはごめんだ。
ましてリゼを、これ以上酷い目に遭わせられるものか。
ただそれだけを必死に願い、生きてきた。
ごみ溜めのような貧民街には、ありとあらゆる悪徳の人間たちが集まっていた。
すりの親方に人さらい、密輸組織の下働き、アル中の娼婦とそのヒモ。みな、たった1本のジンのボトルのため、親兄弟でも売り払いかねないような連中だ。
ここで生まれた子供の半分は、五歳の誕生日を迎えられずに死んでしまう。
汚くて、危なくて、昨日道ばたで飲んだくれていた爺さんが、朝には死体になっているような街だ。
けれどぼくたちにとっては、ここは危険ではあっても、実はそれほど居心地の悪い場所ではなかった。
ごろつきどもの中には会計詐欺を得意とするぺてん師や賭博師、上流階級のご婦人方を食い物にするジゴロ、あるいはもぐりの医者、偽金造りなどもおり、彼らは自分の得意技を次々にぼくたちに教えてくれた。
上流階級に出入りしても疑われないだけのマナーや言葉遣いから、他人の筆跡をまねる方法、法律の盲点や人間の心理をつく話術、世界情勢が街の経済にどう影響するか、それによって人々の心がどう動くか。
道ばたに捨てられたロンドンタイムスやガゼット紙が、ぼくたちの教科書だった。乾いた土が水を吸い込むように、彼らの教育はぼくたちの中に染みこんでいった。
けして楽ではなかった。つねに命の危険と背中合わせだった。
表通りに出れば、杖を振り回す紳士どもに追い払われる。巡査には殴られる。まるで犬のように石を投げられる。
けれどその中で、ぼくたちは少しずつ強くなっていった。
「いいか。絶対に人を信用するな。それがロンドンで生きていく上での鉄則だ。周りの人間は全員、おまえを食い殺そうとしてると思え。だが、ひとたび誰かを信じ、信頼されたら、絶対に裏切るな。たとえ殺されてもだ。それも、この街で人間として生きていくための掟だ。互いの最後の信頼を売るヤツは、人間じゃねえ。けだものだ」
そう教えてくれたのは、ケチな賭博場の用心棒をしているおっさんだった。
「おめえらは、良いな。ガキのころからずっと一緒に育った兄弟は、信じるのに何の理由もいらねえしよ。大事にするんだぜ、お互いをよ」
そして気が付けば、ぼくの身長は姉さんを追い越してかなり高くなり、ぼくたちが一度の稼ぎで手にできる金額は少しずつ増えていった。
ふたりで暮らす場所もテムズの廃船から家賃が割り勘の共同下宿へ、それからもう少しましなアパートへとランクアップしていった。
あれから一〇年あまり。
ぼくたちは、自分たちだけの力で生き抜いてきた。この、生き馬の目を抜く大都会、ロンドンで。悪党どもの巣窟イーストエンドで。
後悔はない。生き延びてきたこと、それ自体がぼくたちの誇りだ。
ひとりきりでは、けして生きていられなかっただろう。姉さんがいたから、ぼくは生きてこられた。
そして姉さんも、ぼくがいたから生きることを諦めずにいられたんじゃないだろうか。
ぼくたちにとっては、互いが世界のすべてだった。
「ずいぶん景気がいいじゃないか、アーニー、セディ」
ワイン樽のような体格とそれに見合った気っ風の良さが魅力の女将が、わっさわっさと豊満すぎる身体を揺すりながら、ぼくたちのテーブルに近づいてきた。
彼女と夫の親爺さんは、馬具職人のマイスターだったころのダニエル・ジャクソンとその一家を知っている。当然、今、ぼくの前に座っているやや小柄な金髪の青年が、実はぼくの兄ではなく、本当はアネリーゼという美しい娘だということも。
だがこの夫婦以外に、姉さんの本当の性別を知っている人間は、この酒場にはいない。誰もがこの人を、アーノルド・グレンフィールドという青年だと信じている。
「聞いたよ、セディ。ブライトンでおもしろい稼ぎをしてきたそうだね。そうとう儲けたんだろ?」
「ああ。あれは兄さんのアイディアだったんだ」
ぼくは笑ってうなずいた。
暇をもてあました貴族や金持ち連中が大勢集まることで有名な、海岸のリゾート地ブライトン。数日前まで、ぼくたちはそこにいた。
海水浴場と摂政皇太子の豪奢な離宮で知られるブライトンには、夏になると、海水浴は温泉療法よりも健康回復に効果があると信じる金持ち連中や、特権階級のじいさんばあさんが大挙してロンドンから押し寄せる。
ほかには、賭博や可愛い踊り子にうつつを抜かす亭主をロンドンに放り出し、女友達と羽を伸ばしにきたご婦人方とか。
ぼくたちは、大陸各地を巡り歩き、修行を積んだ霊能力者という触れ込みで、ブライトンのホテルに部屋を取った。
姉さんが神秘の霊能力者ウルリッヒ・フォン・ファルケンシュタイン師、ぼくはその付き人という役どころだ。
黒ずくめの少し古風な身なりで男装した姉さんが、集会場や遊歩道、巡回図書館など、人々が集まる街のあちこちに姿を見せると、霊能力者ファルケンシュタイン師の噂はたちまちブライトンの社交界を席巻した。
だいたい霊媒師や霊能力者なんてものは――その大半がぼくらの同業者だと思うが――チョビ髭のいかにもうさんくさいおっさんや、しわくちゃの婆さんばっかりだ。
だが、我らがファルケンシュタイン師は違う。絹糸のような金髪に、神秘的な黄金色の瞳。凛とした顔立ちは性別さえ超越した雰囲気を持つ。
そりゃあ、若い娘が男装しているんだから、中性的に見えて当然だが。天使だの妖精だのおキレイなものがお好きなご婦人方には、さぞ神々しく見えたことだろう。
ほどなくして、ぼくたちが宿泊するホテルの部屋には、次々と夢見の悪さや自分の不運を嘆く貴婦人たちが訪れるようになった。
「それでは、貴女の守護霊と交信してみましょう」
やがて深い瞑想状態に入ったファルケンシュタイン師の唇から、それまでの低く、少し涸れたような声とはまるで別人の、高く澄んだ女性の声が洩れ始める。
ドルイドの仙女か、はたまたデルフォイの巫女か――なんて、ね。最初の嗄れ気味の声が無理に低く抑えた作り声で、高い女性の声が姉さんの地声に近いんだけどね。
最初は、日中もう少し運動しなさいとか、阿片チンキの量を減らしなさいとか――いや、阿片中毒の患者ってのは、一目でわかるんだよ。目つきが普通と違うし、独特の饐えたような甘ったるい臭いがするからね――とりあえず当たり障りのないことだけを言っていた姉さんが、ぼくが小さく踵を鳴らして合図した時だけ、おもむろに芝居を変えるんだ。
「……泣いている。小さな赤ちゃんが、貴女の後ろで――。ああ、ああ……っ! この子は、この世の光を知らない子、母親に一度も抱いてもらえず、露と消え去った命――!!」
このセリフで、相談に来た貴婦人方は例外なく真っ青になり、言葉を失う。
ついでにぼくが部屋の隅に張り巡らせたピアノ線の仕掛けで木片を鳴らし、ピシッ、パシッと小さなラップ音を演出すると、ほとんどの女性が絹を引き裂くような甲高い悲鳴をあげる。
その悲鳴で仕掛けが上手くいったのを確信した姉さんは、トランス状態を解き、ファルケンシュタイン師の声色でこう言うのだ。
「貴女の守護霊が告げています。貴女は過去に、望まぬお子をレテの河に流したことがありますね……!」
ここまで来ると、大概のご婦人は半狂乱、失神寸前だ。
――両親にも夫にも隠しおおせていた過去の醜聞を、誰にも知られるはずのないわたくしの過ちを、どうしてこの人物は一度で見抜いてしまったのだろう……!!
だが、なんのことはない。実はこの『王冠とアヒル』亭の近所に、堕胎専門のもぐりの産婆が住んでいる。ぼくたちはその婆さんの過去十年分の顧客リストを見せてもらっただけなのだ。上等のブランデー1本と引き替えに。
いやまったく、侯爵夫人だの伯爵令嬢だの、錚々たる名前が並んでいたよ。
で、そのリストに名前のなかったご婦人には「夢は逆夢、あまり気になさらず、日中たっぷり散歩をなさればよく眠れるようになりますよ」とだけアドバイスし、婆さんの客だったご婦人には「貴女が殺した赤ん坊が取り憑いている!!」とやったわけだ。
「可哀想に……迷っている。この世の光もぬくもりも知らず、天国へも入れてもらえない……。ああ、泣いている、母の手を恋うて……」
芝居だとわかっていても、姉さんの口振りは鬼気迫るものがあった。うっすらと涙までにじませていた。この手の才能は、ぼくは逆立ちしても姉さんに及ばない。
「この子は神に見捨てられた子……。神の御手が届かぬ暗闇に、どうして人の子に過ぎない私の手が届くだろう……」
つまり、あんたの不幸は過去の悪業の報いだからどうしようもない、あきらめろって言ってるわけだ。そして姉さんは涙をぬぐいながら、逃げるように部屋を出ていってしまう。
その次は、ぼくの出番だ。
絶望に打ちひしがれて立ち上がることもできずにいる貴婦人に、そっと耳打ちする。
「ファルケンシュタイン師はたいそうお疲れです。このように悪しき因縁をほどくには、並々ならぬ霊力が必要ですから。ですが、貴女が真に師のお導きを欲しておられるのなら、ぼくから特別にお願いしてさしあげましょう」
あとは黙っていても、ご婦人方は先を争ってお布施を持ってきてくれる。山積みされる金貨や紙幣、ダイヤモンドや真珠のネックレスまで。
なかには自分の肉体を提供しようとする女もいたが、それは丁重にお断りした。――いや、本当に全員断ったよ! つまみ食いなんかしてないってば!
女房が胡散臭い霊媒師に入れあげてさんざっぱら貢いでいるという話を聞きつけて、ご亭主殿が慌ててロンドンから駆けつけてきた時には、後の祭り。ファルケンシュタイン師は多額のお布施とともに煙のように消え失せているというわけだ。
「探せ、探せ! あのぺてん師をとっつかまえろ!」
主人に怒鳴られて乗合馬車を追いかけた従者や馬丁たちが目にしたのは、パトロンと喧嘩別れしてロンドンへ帰る蓮っ葉な女優と、そののろまな従者だけ。
「なにジロジロ見てんのさ! あたいは、金のない男にゃ用はないんだよ!」
大きく胸の開いた真っ赤なドレスで着飾ったその下品な女優こそが、昨日まで神秘のお告げをもたらしていたウルリッヒ・フォン・ファルケンシュタイン師だと、誰が信じるだろう。
僕は一応、濃い茶色のカツラと眼鏡で変装していたけど、姉さんはハニーブロンドを派手に結い上げて、少し化粧をしただけだった。
ファルケンシュタイン師の信者だったご婦人方は、あんな下品な女は声を聞くのも汚らわしいと言わんばかりに顔を背け、誰ひとりとして姉さんの正体に気づかなかった。
……いつもそばにいるぼくでさえ、時々目を疑いたくなる。このひとは本当に、自分の性別を自在に変えられるんじゃないかってね。
そしてぼくたちは、トランク一杯の金貨やダイヤモンドのネックレス、ブローチなどを手に、意気揚々とイーストエンドに帰ってきたのだ。
ロンドンに入ってすぐ、宝石類はみんなバラして故買屋に売り飛ばした。
涙の形をした見事なルビーのイヤリングは、姉さんのためにとっておきたかったんだけど。
「だめに決まってんだろ。こんな目立つモンぶら下げて歩いてみろ、オレたちがこいつを騙し取ったぺてん師でございって看板出してるようなもんじゃねえか」
姉さんは自分で器用にイヤリングをばらしてしまった。
今頃、あの女王のようなルビーはそれぞれネックレスかブレスレットの一部に加工され、離ればなれになって別々の店のショウウィンドウを飾っていることだろう。残念だ。
「はい、またぼくの勝ち」
スペードのエースをテーブルの上に投げて、ぼくは言った。
「うー……っ!」
十二連敗の姉さんは、もう言葉も出てこない。
賭けたのは、今夜一晩、相手に何でも命令できる権利。
「さーて、なにをしてもらおうかなあ」
ぼくはほくそ笑みながらカードをまとめた。我ながらそうとう底意地の悪い表情になっているだろうなと思う。
悔しそうに呻り続ける姉さんは、酔いのせいもあって目元がうっすらと紅く染まり、潤んで見える。……ひどく色っぽい。
「そうだ、このあいだの紅いドレスを着て、踊りに行こうよ。コヴェントガーデンの近くに、パリ風のダンスホールができたって話だよ」
「やだよ。おまえ、そこでまたオレに男ひっかけさす気だろ」
「そんなことしないよ」
美人局も手っ取り早い小遣い稼ぎにはいいけどね。でも、今夜はぼくが姉さんを独り占めするつもりだから。
「じゃあ……」
ぼくはしばらく考え込み、それからおもむろにテーブルに肘をついて身を乗り出した。
「そのままの恰好でいいから、ヴォクソール遊園に散歩に行こう」
「今からか?」
もう真夜中を過ぎている。バカンスシーズンが終わりかけた晩夏のこの時期、外はまだそれほど寒くはないけれど、やはりこんな時間から公園に出かけるなんて、酔狂すぎる。
けれど、ぼくはにこやかに笑ってうなずいた。
それから、姉さんにだけ聞こえるよう、低い声でそっとささやく。
「その恰好のままの貴女を、抱かせて」
「おま……っ、セ、セオドア! おまえ――っ!」
姉さんは耳元まで真っ赤になって、絶句した。
「男装した姉さんを抱くのって、凄くスリリングでどきどきする。『姉さん』も『兄さん』も、どっちもいっぺんに犯してるみたいでさ」
娼婦を買うのは男の悪癖でしかないが、同性愛は法律で禁じられたれっきとした犯罪だ。その罪に問われた男が、罰として二年間もの強制労働につかされたケースもある。女性を男装させて犯すのは、さて、どんな罪に相当するだろう?
「ば、莫迦っ! こんなとこでなに言ってんだ、おまえ!」
「大丈夫。誰にも聞こえてないよ」
『王冠とアヒル』亭は今夜も大盛況だ。酔っぱらいどもが高歌放吟、やかましくて、隣にいる人間と会話するにも大声を張り上げなくてはならない。ぼくのセリフなんか、誰も聞いているもんか。
むしろそんなふうに姉さんが真っ赤になってうろたえるほうが、人目を引いてしまうんじゃない?
勝ち気で頭が良くて、どんな老獪な紳士や役人たちでさえ容易く手玉にとる姉さんが、こういうことに関してだけはひどく初心で、まるで田舎から出てきたばかりの小娘みたいだ。まったく可愛いったら、ない。
できることなら今すぐこのひとを抱きしめて、息ができなくなるまでキスしたい。
でも、あんまり無茶ばかり言って苛めると、そのあと三日くらい口もきいてくれなくなるから。
「じゃあ、家でいいよ。そのかわり、ぼくが良いというまでベッドから出ないで」
テーブルの上で、かすかにふるえる姉さんの手に自分の手をかさね、そっと握りしめる。姉さんはうつむき、何も答えず、けれど逃げようとはしなかった。
「そろそろ帰ろうか、アーノルド兄さん」
今、ぼくたちが暮らす部屋は、軍人の未亡人が経営する賄い付きの下宿屋だ。
ウエストエンド、セント・ジェームズ・パークからさほど遠くないところにあり、間取りは居間と寝室がふたつ、予備の小部屋がひとつ。
この部屋を、ぼくたちはジェントリ階級出身の兄弟というふれこみで借りている。地元領主の求めに応じて手放した土地の代金を投資に回し、生計を立てている、と家主のオルソン夫人には説明してある。
もっとも、彼女がその説明を鵜呑みにしているかどうかは疑わしい。だがほかの下宿人も、高級娼婦ばかりを顧客に持つ弁護士だの、演奏より色事のほうが得意そうなバイオリン教師だの、みんな叩けば埃の出そうな連中ばかりだ。
第一、軍人の未亡人というオルソン夫人の経歴自体、怪しいんじゃないかとぼくは思っている。
彼女が数人の下宿人を置いているこの屋敷は最新のヴィクトリアン様式、半地下の倉庫と屋根裏の使用人部屋を抜かしても、一階と二階を合わせて十部屋を越える広さだ。建材や備え付けの家具にもけっこう金がかかっている。地方に領地を持つ貴族のタウンハウスが、借金返済のために売りに出されたか、賭博のカタにまきあげられたか、といったところだろう。
たかが軍人の遺族年金で、こんなでかい屋敷が買えるものだろうか。
この屋敷を買った資金は、微々たる遺族年金なんかじゃないだろう。もっと別の、おそらくは彼女自身の美貌と才覚で稼ぎ出した金のはずだ。
だが、彼女に面と向かってそれを問い質す下宿人は、もちろんひとりもいない。
そしてオルソン夫人も、ぼくたちがきちんと部屋代を払っている限り、グレンフォード兄弟を若い投資家の紳士として扱ってくれるはずだ。
ぺてんで稼いだ金の一部は投資に回して、堅実に利益をあげてもいるから、ぼくたちはあながち嘘だけを言っているわけでもない。
「でも、今の姉さんを見たら、ミセス・オルソンは泡を吹いて卒倒するだろうな。彼女、兄さんを男だと信じきっているから」
「まさか。じゃあ、ときどきこの部屋に出入りしてる、派手なドレスの女は、ありゃ誰だよ」
「あれは、兄さんの留守を見計らってぼくが連れ込んでる、高級娼婦(コーティザン)。ぼくは兄さんよりお行儀が悪いんだ」
寝室へ行くのももどかしく、ぼくたちは居間のソファーで抱き合っていた。床にはふたり分の衣服が脱ぎ散らかされている。
紙一枚も入らないほどぴったりと体を重ね合い、互いの髪に指を絡めて溶け合うようなキスをする。
ゆたかな金髪を奔放に乱し、一糸まとわぬ姿の姉さんは、まるでカーマ・スートラに登場する淫らな女神だ。
「セディ――」
ふと、姉さんがぼくの名をつぶやく。
「その、瞳(め)……」
「ん? 目? ぼくの?」
姉さんはこくんとうなずいた。
「おまえの、その瞳(め)――大好き」
ぼくのほほに両手を添えて、姉さんはぼくのまぶたに軽くついばむようなキスをした。
「こういう時ってさ、おまえの瞳、いつもより色が濃くなって、ほとんど黒に近くなるんだ。でもそれが、好き」
ぼくの瞳は少し暗く見える緑だ。姉さんは「深い森みたいな色」と表現する。が、感情が激すると、やや毒々しいまでの明るいエメラルドグリーンに変わる。まじまじと鏡で確かめたことはないが。
この瞳の色は、どうやら顔も名前も知らない父親に似たらしい。そのため、母さんは生前ずっと、この目を直視するのをためらっていた。
けれど。
「きれいだ。おまえの瞳(め)。見てると、吸い込まれそうな気がする」
姉さんはそう言う。
ぼくに言わせれば、姉さんの金色の瞳ほど美しい眼はないのに。
「姉さん――!!」
全身を、ふるえるような戦慄が駆け抜ける。
ぼくはたまらず、姉さんを抱きしめた。
いとしい人の全身を、頭のてっぺんから爪先まで、そのはちみつ色の髪の一房一房まで、キスと愛撫で覆い尽くす。そうやって、この人のすべてにぼくのすべてを刻印してしまえたらと願う。
姉さんとこういう関係になることは、ぼくにとってはごく自然なことだった。
ぼくが初めての女は、姉さんだ。――姉さんの初めての男は、ぼくではないけれど。
あれは、ぼくたちがまだテムズ河に係留された廃船で寝起きしていたころ。
凍り付くような風が吹く冬、ぼくはひどい熱を出した。
ロンドンでは毎年のようにたちの悪い病気が流行る。チフス、赤痢、百日咳、コレラ。人口が密集するイーストエンドではなおさらだ。
衛生環境は悪く、医療環境はさらに悪い。医師も薬屋も相手にするのは裕福な人々だけであり、貧しいスラム街の住人などさっさと死ね、自分の前に顔も見せるなと言わんばかりの態度だ。
まして決まった住居もない浮浪児など、医療など受けられるはずもなかった。
高熱に浮かされ、かろうじてぜいぜいと苦しい呼吸を続けながら、ぼくもそのまま死ぬのだろうかと思っていた。
けれど姉さんは、ぼくを医者のところへ連れていった。
自分の体を代価にして、ぼくに治療を受けさせてくれたのだ。
姉さん自身と引き替えにぼくたちを自分の屋敷に泊め、ぼくの治療に当たった医者は、女王陛下の宮殿にも出入りが許され、貴顕の人々の病気や怪我を治してきた名医として知られていた。が、その実、貧民街の年端もいかない少女を金で買うような野郎だったわけだ。
栄養状態が悪かったため、ぼくはそいつの屋敷で二ヶ月ほど寝たきりになっていた。
そのあいだ、姉さんは自分がなにをされているか、けしてぼくに語ろうとはしなかった。
「おまえが謝ることなんか、なんもねえだろ、セディ。なんにも心配するな。おまえはただ、病気を治すことだけを考えていればいいんだ」
そう言ってぼくの額にキスした姉さんの唇が、かすかにふるえていた。
あの時の悔しさを、ぼくはけして忘れない。姉さんをもてあそぶ男が、そして誰よりも、姉さんを犠牲にしてのうのうと生き延びる自分自身が、許せなかった。
最初は母さん。そして、姉さん。いつもそうだ。ぼくの無力のせいで、ぼくの大切な人たちが犠牲になる。
悔しくて、歯がゆくて、自分が情けなくて、いっそこのまま死んでしまいたいと思った。
けれど、ぼくの熱が下がったと言って喜び、ぼくが食事を残さないようにとずっと付き添ってくれる姉さんを見ていると、それもできない。
強くなりたい。賢く、強く、姉さんを守れる男になりたい。
ただ、繰り返しそう願うしかなかった。
ぼくがベッドから起きあがれるようになっても、くだんの医者は姉さんを手放そうとはしなかった。よほど姉さんが気に入ったらしい。ぼくたちを遠縁の子どもといつわり、屋敷に住まわせていた。――女房も子どももいたのに。
ぼくたちがそこに居候していたのは、半年あまり。
ついに我慢できなくなった姉さんとぼくは、そいつの頭を銀の燭台でぶん殴り、屋敷から逃げ出した。もちろん、凶器に使った燭台そのほかを頂戴して。
ちなみにその医者は、そのあと何度かガゼット紙に名前が載っていたから、死にはしなかったらしい。ぼくは今でも殺してやりたいと思っているが。
姉さんがいまだにかたくなに男装を続けているのは、あの時の悲痛な記憶を心の奥底に封印してしまいたいからなのかもしれない。
そしてぼくは誓った。
もう二度と、ほかの男に姉さんをさわらせたりしない。
姉さんはぼくが守る。
このひとを、ぼくだけのものにする。
たしかに、このひとだけに貞節を守り抜いているわけじゃない。商売柄、娼婦を買うこともあるし、金持ちのご婦人のベッドに忍び込まなくてはならない時もあった。
けれど、ぼくの心を、魂を捧げるひとは、この世にただひとりだ。
姉さんが――金色の瞳をした美しいアネリーゼだけが、ぼくの永遠の恋人だ。
「姉さん、好きだ。愛してる。ぼくの……ぼくの、リゼ。大好きだよ――!」
同じ言葉を何度も何度も繰り返しながら、ぼくは一晩中姉さんを離さなかった。
アメンバー限定公開版と歩調を合わせるため、少し短くしました。切った部分は次回に載せます。
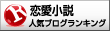
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いします♪
ACT 1 アーニーとセディ
「ああ、ちくしょう、また負けたぁっ!」
派手にカードをまき散らし、姉さんはばったりとテーブルに突っ伏した。
「だから言ったじゃないか。兄さんはカード賭博には向いてないって」
ぼくは笑いながらカードをまとめ、軽くシャッフルする。
「おまえ、いかさましてねーだろうな」
「兄さん相手にいかさまして、どうするの。兄さんの財布とぼくの財布は一緒だろ」
この人を「兄さん」「姉さん」と呼び分けるのも、もう慣れた。
今みたいに長めのシヴィルコートにクラヴァットで男装している時は「兄さん」、ドレス姿の時は「姉さん」だ。
……ぼくとしては、奇麗なドレス姿のほうがより嬉しいのだが。
ひげ面の無愛想な親爺さんが経営する居酒屋(タヴァーン)『王冠とアヒル』亭は、イーストエンドを含むテムズ河添いのロンドン・ドッグ地帯では、かなりランクが上のほうだ。オランダ産のジンやビールのほかに、金さえ払えば上物のブランデーも出してくれる。もちろん、真夜中にドーヴァーを越えてくる密輸品だが。料理もなかなか美味しく、ぼくたちのお気に入りだ。
煙草の煙が白く立ちこめ、キッチンの奥でスモークされる鴨の匂いがあふれる店内は、今夜もかなりの盛況だった。
あちこちのテーブルでカード賭博の小銭がやりとりされ、運良く儲けた男をカモろうとカウンターでは精一杯めかし込んだ娼婦たちが待ちかまえている。もうしばらくすれば、二階に設けられた休憩用の小部屋はどこもいっぱいになるだろう。
「親爺さん、おかわり。同じものね」
ぼくはブルゴーニュ産のブランデー、姉さんは甘いマデイラワインが好みだ。
「もう一度だ、セディ! もう一回!」
負けず嫌いの姉さんがしつこく食い下がる。
「いいよ、何度でも。ピケ? それともホイスト?」
――何度やっても結果は同じだと思うけどね。思ったことが全部顔に出る姉さんは、カード賭博には向いてないよ。
いつもはぼくよりずっと頭の回転が速くて、並の男など足下にも近寄れないほど度胸も思い切りも良い姉さんが、こうしてぼくとふたりで遊んでいる時だけは、まるで子どもみたいだ。
客を待つ娼婦たちが、ちゅっちゅっと唇を鳴らしてぼくたちの気を引こうとする。
ぼくは、今夜は用はないよ、と彼女らの胸元に銀貨を放ってやった。
「そいつで一杯やってなよ」
娼婦たちははしゃいできゃあっと歓声を上げた。一杯どころか、安物のジンならボトル五、六本は買える金額だ。
姉さん――ぼくの兄、アーノルド・グレンフィールドは物理的に彼女らの客になることはできないが、ぼくは何度かお世話になったことがある。上流階級の紳士どもの醜聞を手に入れるには彼女たちに聞くのが一番だし、ご婦人方をたらし込むためのベッドテクニックを教わるのにも、ね。
そう。
初めて出逢った時、無惨に刈られてしまった髪を汚いスカーフで隠し、つぎあてだらけのエプロンとスカートを着ていた貧民街の少女は、今は仕立ての良いシヴィルコートに磨き上げられたヘシアンブーツ、ジェットストーンのタイピンと、地味だが趣味の良い身なりをして、どこから見ても金に不自由しない都会の紳士だ。
もっともその衣服にも靴にも詰め物がしてあって、本当はほっそりとして華奢な姉さんのプロポーションを少しでも大柄に見せられるよう、工夫してあるのだが。
「女将、オレはもうワインはいいや。ホットトディ、作ってくれ」
低く抑えた作り声も、見事に男の声に聞こえる。
イーストエンド中の娼婦が羨むはちみつ色の髪だけは、ひと昔前に流行ったように、長く伸ばして黒のリボンでひとつに括っている。
これは、髪だけはもったいないから切らないでくれと、ぼくが必死に頼み込んだからだ。姉さんはいつも、背まで届く長い髪のブラッシングを面倒くさがっている。
「おまえみたいに短く切っちまったほうが、ずーっと便利だって。よけいな印象を残さずにすむし。女に戻ってドレスを着る時は、カツラかぶりゃいいんだから」
と、姉さんは言うけれど。
そんなの、ぼくは絶対に認められない。
この、天使の花冠みたいなハニーブロンドを短く刈り込んでしまうなんて、もったいなさすぎてバチが当たるよ。
こうして男のふりをするのは、姉さんが自分で言い出したことだ。
――一〇年前の、あの日。
父さんと母さんを共同墓地の片隅に葬ったあと、リゼはその足でまっすぐ教会の慈善箱へ向かった。
日曜のミサが行われる礼拝堂の後ろに置かれている大きな木箱は、教区に住む善男善女から寄付された古着や靴が入れてある。たいがいはひどくぼろぼろで、古着屋も買い取ってくれないようなシロモノだ。それでも、教区の婦人会の方々が大釜で洗濯――というよりぐらぐら煮立てて消毒してあるので、とりあえずは清潔だ。礼拝堂付きの助司祭に一言ことわれば、誰でもそこから好きなものを持っていくことができる。貧民街の路上生活者には、とてもありがたい箱なのだ。空っぽの時も多いが。
リゼは運良くその中から、膝につぎのあたったズボンと、はげちょろけのツィードのジャケットを見つけ出した。
「それ、ぼくに?」
「違う。オレが着るんだよ」
――オレ?
リゼの口から飛び出した言葉に、ぼくは耳を疑った。
「だってそれ、男物だよ。いくら髪が男の子みたいになっちゃったからって、リゼ姉さん……」
「姉さん、じゃない。兄ちゃんって、呼べ」
「……え?」
ぼくはあぜんとして、リゼを見た。
けれどリゼの目は、痛いくらい真剣だった。
「いいか。今からオレはおまえの兄さんだ。間違っても、リゼなんて呼ぶな」
「ど、どうして? なんでいきなり……」
「セディのばか。先月殺されたネリーのこと、おまえ、知らないのか?」
「ネリーって……、あ!」
可哀想なネリー。その名前に、ぼくは小さく息を呑んだ。
ネル・オブライエンは、飲んだくれの藪医者コナー・オブライエンのひとり娘だった。
ろくでなしの亭主に愛想を尽かして母親が出ていったあとも、父親のそばに残り、けなげに励まし続けていた。
だがある日、診療ミスから患者を死なせてしまったオブライエンが監獄にぶち込まれ、ネリーはたったひとりでイーストエンドに取り残された。そしてみながちょっと目を離した隙に、ネリーの姿は消えていた。
見つかったのは三日後。ネリーは全裸でテムズ河に浮かんだ。
身体中に残された傷痕が、ネリーがいかにむごたらしく玩ばれ、虫けらのように殺されたかを物語っていた。……可哀想なネリーは、まだ六才にもなっていなかった。
監獄から釈放されたオブライエンは変わり果てた娘の亡骸と対面することになり、翌日、街角のガス灯で首をくくった。
ぼくは唇を噛みしめ、うつむいた。
ネリーの死は、この街ではけして珍しい事件じゃない。
まともな大人だって職がなく、飢えてテムズ河に身投げするような時代だ。一方で特権階級はぶくぶくと肥え太り、歪んだ欲望のはけ口を捜している。そしてそいつらのたるんだ腹にぶらさがり、その涎を啜って生きている連中もいる。
大陸封鎖令によって島国イングランドを飢え死に寸前に追い込んだフランスの独裁者ナポレオン・ボナパルトは、ネルソン提督によって自慢の海軍を撃破され、自国民にも裏切られてエルバ島に流された。それでも彼は執念深く流刑地を脱出し、ふたたびイングランドに戦争を挑んできた。が、今度は陸の英雄ウェリントン将軍によって完膚無きまでにたたきのめされ、ふたたびセントヘレナ島に追いやられた。
これによって、長く続いたフランスとの戦争はようやく終了した。
英国は大勝利をおさめたはずだった。
けれど故国は、歴戦の勇者たちにあまりにも冷酷だった。大陸各地の戦線から戻ってきた兵士たちの大半は、もとの仕事に復帰することもできず、路上にあふれかえった。
仕事も金もなく、中には手足を失った者もいる。彼らのほとんどは浮浪者となり、あるいは路上強盗や追いはぎに身を落とす者もいた。
地方では地主による大規模な土地の囲い込み(エンクロージャー)が起き、自作農たちですら次々に先祖伝来の土地を奪われ、流浪の身となって大都市ロンドンへ押し寄せる。
王宮には若く清廉な女王陛下が君臨し、そのもとには綺羅星のごとく有能な政治家、外交官たちがつどう。けれど一歩街へ踏み出せば、道ばたには浮浪者があふれ、がりがりにやせ細った娼婦たちが今日の食事を手に入れるため、懸命に客をひく。捨てられた赤ん坊は野良犬の餌食になり、テムズ河に死体が浮かんでいない日はない。
大人ですらまともな職が得られないこんな時代、親を失った幼い子どもが真っ当に生きていける方法なんか、あるわけがない。
救貧院から幼い子どもが連れ出されるのなんて日常茶飯事、田舎から若い娘を騙して連れてくる大がかりな誘拐団もあると聞く。親もなく、自分の身を護るすべのない子どもらなんて、食い殺してくれと言わんばかりの存在なのだ。
そして、あらためて見つめると、リゼはとてもきれいな女の子だった。
ネズミ色のブラウスを着て、薄汚れていても、その肌は透きとおるように白い。甘い香りのするハニーブロンドと、そしてこの金色の瞳。
夜明けの太陽みたいな金色の瞳は、光の加減によって淡くけぶる琥珀色から透明なシトリントパーズにまで変化する。そして感情が激昂すると、まるで鋳造したてのぴかぴかの金貨みたいに輝くのだ。
こんなにきれいな女の子が、守ってくれる大人もなく、たったひとりでスラム街をうろついていたら。
もてあそんで殺してくださいと言っているようなものだ。
男物の衣服に着替え、仕上げに破れかけた鳥打ち帽を目深にかぶって、髪も顔も半分以上隠してしまうと、リゼはどこから見てもスラム街の薄汚れた悪ガキだった。
「えーと、アル、アーニー……。うん、アーニー。アーノルド」
ショーウィンドウに自分の姿を映して確かめながら、姉さんはつぶやいた。
「アーノルド。いい名前だろ。今日からオレは、アーノルド・グレンフィールドだ」
「――アーノルド」
「そうだ。おまえも、間違っても人前でオレのこと、『リゼ姉さん』なんて呼ぶなよ!」
「うん、わかったよ。ねぇ……兄さん」
ぼくは小さくうなずいた。
けれど本当は、悔しくてならなかった。
こんな恰好、リゼにはちっとも似合わない。
可愛くてきれいで、誰よりも頭のいいリゼは、本当はそれにふさわしい恰好をするべきなんだ。
やわらかなタフタのドレスにレースのショール、アーミンの縁取りがついたコート、金色の飾りボタンのブーツ。ふわふわのハニーブロンドには、シルクと真珠を編み込んで。
そういう姿で、笑いながら街を歩くべきなんだ。
でもぼくには、彼女にそれを与えてあげることができない。たった一枚のハンカチですら。
そしてリゼは、自分自身を守るため、薄汚いちんぴらのふりをしなくてはならないんだ。
……ぼくにもっと力があったなら。
リゼを守りきれるだけの、強く賢い、大人の男であったなら。
「どうした? セディ」
ふと気づくと、姉さんが心配そうにぼくの顔を覗き込んでいた。
「あんまり気にすんなよ。おまえが悪いわけじゃない。それにこのカッコだって、慣れればいいもんだぜ?」
「うん……、似合うよ。兄さん」
ぼくは力無く、笑顔を作って見せるしかなかった。
いつか……いつかきっと姉さんを、本来の姿に戻してあげる。
誰よりも美しい、完璧な貴婦人の姿に。本当のアネリーゼに。
ぼくはひそかにそう誓った。
その誓いは、今もぼくの胸にある。誰にも――姉さんにも、明かしたことはないけれど。
教会の軒下で数日間を過ごしたあと、やがてぼくたちはテムズ河に係留されたままの廃船にもぐり込んだ。
汚いし、ネズミは走り回るし、水漏れもする。いつ沈没するかわからない。それでも頭の上に天井があるだけ、ましだ。
その船がしばらくのあいだ、ぼくたちの家となった。
教会の慈善箱からもらってきた穴だらけのコートにふたりでくるまり、空腹を抱えて夜を過ごす。
そんな時でも、姉さんとふたりなら耐えられた。ぼくは姉さんを抱きしめ、姉さんのぬくもりがぼくをあたためてくれた。
生きていくために、なんでもやった。空き巣、置き引き、かっぱらい。美人局のまねごとまで。その日一日を生き延びるだけで、精一杯だった。
自分たちのしていることが悪いことかどうかなんて、考えている余裕すらなかった。
神様は死んだ後のことしか面倒を見てくれない。生きている人間は自分の食い扶持を稼ぐのが精一杯で、他人のことなどかまっていたら死んでしまう。ここはそういう街なのだ。
その中でぼくたちは、このイーストエンドで生きていくすべをひとつ、またひとつと学んでいった。たとえばいかさま賭博、たとえば鍵なしでも裏口のドアを開ける方法、たとえば理不尽な暴力に対抗するための、暴力。そして、知恵。
それでも最低限のルールは守った。自分たちより弱い者からは、けして奪わない。
路上で物乞いをする老人や幼い子どもたちには、たった一枚の銅貨が全財産だ。彼らは、昨日までのぼくたち自身だ。そんな人々からどうして奪うことができるだろう。
だけど、ぶくぶくと肥え太り、財布の重みでよたついているような特権階級から少々の金貨をかすめ取ったところで、連中は困るどころか金貨が減ったことにすら気づきはしないんだ。
何度も死にかけた。危うく巡査にとっつかまりそうになったこともある。
捕まったが最後、待っているのはタイバーン刑場での鞭打ちと工事現場での強制労働だ。
連中は女子どもにも容赦はない。路上で商売していたところを運悪く巡査に見つかった娼婦が、見せしめのために上半身を裸にされて、血だるまになるまで鞭打たれているのを、見たことがある。
――あんな目に遭うのはごめんだ。
ましてリゼを、これ以上酷い目に遭わせられるものか。
ただそれだけを必死に願い、生きてきた。
ごみ溜めのような貧民街には、ありとあらゆる悪徳の人間たちが集まっていた。
すりの親方に人さらい、密輸組織の下働き、アル中の娼婦とそのヒモ。みな、たった1本のジンのボトルのため、親兄弟でも売り払いかねないような連中だ。
ここで生まれた子供の半分は、五歳の誕生日を迎えられずに死んでしまう。
汚くて、危なくて、昨日道ばたで飲んだくれていた爺さんが、朝には死体になっているような街だ。
けれどぼくたちにとっては、ここは危険ではあっても、実はそれほど居心地の悪い場所ではなかった。
ごろつきどもの中には会計詐欺を得意とするぺてん師や賭博師、上流階級のご婦人方を食い物にするジゴロ、あるいはもぐりの医者、偽金造りなどもおり、彼らは自分の得意技を次々にぼくたちに教えてくれた。
上流階級に出入りしても疑われないだけのマナーや言葉遣いから、他人の筆跡をまねる方法、法律の盲点や人間の心理をつく話術、世界情勢が街の経済にどう影響するか、それによって人々の心がどう動くか。
道ばたに捨てられたロンドンタイムスやガゼット紙が、ぼくたちの教科書だった。乾いた土が水を吸い込むように、彼らの教育はぼくたちの中に染みこんでいった。
けして楽ではなかった。つねに命の危険と背中合わせだった。
表通りに出れば、杖を振り回す紳士どもに追い払われる。巡査には殴られる。まるで犬のように石を投げられる。
けれどその中で、ぼくたちは少しずつ強くなっていった。
「いいか。絶対に人を信用するな。それがロンドンで生きていく上での鉄則だ。周りの人間は全員、おまえを食い殺そうとしてると思え。だが、ひとたび誰かを信じ、信頼されたら、絶対に裏切るな。たとえ殺されてもだ。それも、この街で人間として生きていくための掟だ。互いの最後の信頼を売るヤツは、人間じゃねえ。けだものだ」
そう教えてくれたのは、ケチな賭博場の用心棒をしているおっさんだった。
「おめえらは、良いな。ガキのころからずっと一緒に育った兄弟は、信じるのに何の理由もいらねえしよ。大事にするんだぜ、お互いをよ」
そして気が付けば、ぼくの身長は姉さんを追い越してかなり高くなり、ぼくたちが一度の稼ぎで手にできる金額は少しずつ増えていった。
ふたりで暮らす場所もテムズの廃船から家賃が割り勘の共同下宿へ、それからもう少しましなアパートへとランクアップしていった。
あれから一〇年あまり。
ぼくたちは、自分たちだけの力で生き抜いてきた。この、生き馬の目を抜く大都会、ロンドンで。悪党どもの巣窟イーストエンドで。
後悔はない。生き延びてきたこと、それ自体がぼくたちの誇りだ。
ひとりきりでは、けして生きていられなかっただろう。姉さんがいたから、ぼくは生きてこられた。
そして姉さんも、ぼくがいたから生きることを諦めずにいられたんじゃないだろうか。
ぼくたちにとっては、互いが世界のすべてだった。
「ずいぶん景気がいいじゃないか、アーニー、セディ」
ワイン樽のような体格とそれに見合った気っ風の良さが魅力の女将が、わっさわっさと豊満すぎる身体を揺すりながら、ぼくたちのテーブルに近づいてきた。
彼女と夫の親爺さんは、馬具職人のマイスターだったころのダニエル・ジャクソンとその一家を知っている。当然、今、ぼくの前に座っているやや小柄な金髪の青年が、実はぼくの兄ではなく、本当はアネリーゼという美しい娘だということも。
だがこの夫婦以外に、姉さんの本当の性別を知っている人間は、この酒場にはいない。誰もがこの人を、アーノルド・グレンフィールドという青年だと信じている。
「聞いたよ、セディ。ブライトンでおもしろい稼ぎをしてきたそうだね。そうとう儲けたんだろ?」
「ああ。あれは兄さんのアイディアだったんだ」
ぼくは笑ってうなずいた。
暇をもてあました貴族や金持ち連中が大勢集まることで有名な、海岸のリゾート地ブライトン。数日前まで、ぼくたちはそこにいた。
海水浴場と摂政皇太子の豪奢な離宮で知られるブライトンには、夏になると、海水浴は温泉療法よりも健康回復に効果があると信じる金持ち連中や、特権階級のじいさんばあさんが大挙してロンドンから押し寄せる。
ほかには、賭博や可愛い踊り子にうつつを抜かす亭主をロンドンに放り出し、女友達と羽を伸ばしにきたご婦人方とか。
ぼくたちは、大陸各地を巡り歩き、修行を積んだ霊能力者という触れ込みで、ブライトンのホテルに部屋を取った。
姉さんが神秘の霊能力者ウルリッヒ・フォン・ファルケンシュタイン師、ぼくはその付き人という役どころだ。
黒ずくめの少し古風な身なりで男装した姉さんが、集会場や遊歩道、巡回図書館など、人々が集まる街のあちこちに姿を見せると、霊能力者ファルケンシュタイン師の噂はたちまちブライトンの社交界を席巻した。
だいたい霊媒師や霊能力者なんてものは――その大半がぼくらの同業者だと思うが――チョビ髭のいかにもうさんくさいおっさんや、しわくちゃの婆さんばっかりだ。
だが、我らがファルケンシュタイン師は違う。絹糸のような金髪に、神秘的な黄金色の瞳。凛とした顔立ちは性別さえ超越した雰囲気を持つ。
そりゃあ、若い娘が男装しているんだから、中性的に見えて当然だが。天使だの妖精だのおキレイなものがお好きなご婦人方には、さぞ神々しく見えたことだろう。
ほどなくして、ぼくたちが宿泊するホテルの部屋には、次々と夢見の悪さや自分の不運を嘆く貴婦人たちが訪れるようになった。
「それでは、貴女の守護霊と交信してみましょう」
やがて深い瞑想状態に入ったファルケンシュタイン師の唇から、それまでの低く、少し涸れたような声とはまるで別人の、高く澄んだ女性の声が洩れ始める。
ドルイドの仙女か、はたまたデルフォイの巫女か――なんて、ね。最初の嗄れ気味の声が無理に低く抑えた作り声で、高い女性の声が姉さんの地声に近いんだけどね。
最初は、日中もう少し運動しなさいとか、阿片チンキの量を減らしなさいとか――いや、阿片中毒の患者ってのは、一目でわかるんだよ。目つきが普通と違うし、独特の饐えたような甘ったるい臭いがするからね――とりあえず当たり障りのないことだけを言っていた姉さんが、ぼくが小さく踵を鳴らして合図した時だけ、おもむろに芝居を変えるんだ。
「……泣いている。小さな赤ちゃんが、貴女の後ろで――。ああ、ああ……っ! この子は、この世の光を知らない子、母親に一度も抱いてもらえず、露と消え去った命――!!」
このセリフで、相談に来た貴婦人方は例外なく真っ青になり、言葉を失う。
ついでにぼくが部屋の隅に張り巡らせたピアノ線の仕掛けで木片を鳴らし、ピシッ、パシッと小さなラップ音を演出すると、ほとんどの女性が絹を引き裂くような甲高い悲鳴をあげる。
その悲鳴で仕掛けが上手くいったのを確信した姉さんは、トランス状態を解き、ファルケンシュタイン師の声色でこう言うのだ。
「貴女の守護霊が告げています。貴女は過去に、望まぬお子をレテの河に流したことがありますね……!」
ここまで来ると、大概のご婦人は半狂乱、失神寸前だ。
――両親にも夫にも隠しおおせていた過去の醜聞を、誰にも知られるはずのないわたくしの過ちを、どうしてこの人物は一度で見抜いてしまったのだろう……!!
だが、なんのことはない。実はこの『王冠とアヒル』亭の近所に、堕胎専門のもぐりの産婆が住んでいる。ぼくたちはその婆さんの過去十年分の顧客リストを見せてもらっただけなのだ。上等のブランデー1本と引き替えに。
いやまったく、侯爵夫人だの伯爵令嬢だの、錚々たる名前が並んでいたよ。
で、そのリストに名前のなかったご婦人には「夢は逆夢、あまり気になさらず、日中たっぷり散歩をなさればよく眠れるようになりますよ」とだけアドバイスし、婆さんの客だったご婦人には「貴女が殺した赤ん坊が取り憑いている!!」とやったわけだ。
「可哀想に……迷っている。この世の光もぬくもりも知らず、天国へも入れてもらえない……。ああ、泣いている、母の手を恋うて……」
芝居だとわかっていても、姉さんの口振りは鬼気迫るものがあった。うっすらと涙までにじませていた。この手の才能は、ぼくは逆立ちしても姉さんに及ばない。
「この子は神に見捨てられた子……。神の御手が届かぬ暗闇に、どうして人の子に過ぎない私の手が届くだろう……」
つまり、あんたの不幸は過去の悪業の報いだからどうしようもない、あきらめろって言ってるわけだ。そして姉さんは涙をぬぐいながら、逃げるように部屋を出ていってしまう。
その次は、ぼくの出番だ。
絶望に打ちひしがれて立ち上がることもできずにいる貴婦人に、そっと耳打ちする。
「ファルケンシュタイン師はたいそうお疲れです。このように悪しき因縁をほどくには、並々ならぬ霊力が必要ですから。ですが、貴女が真に師のお導きを欲しておられるのなら、ぼくから特別にお願いしてさしあげましょう」
あとは黙っていても、ご婦人方は先を争ってお布施を持ってきてくれる。山積みされる金貨や紙幣、ダイヤモンドや真珠のネックレスまで。
なかには自分の肉体を提供しようとする女もいたが、それは丁重にお断りした。――いや、本当に全員断ったよ! つまみ食いなんかしてないってば!
女房が胡散臭い霊媒師に入れあげてさんざっぱら貢いでいるという話を聞きつけて、ご亭主殿が慌ててロンドンから駆けつけてきた時には、後の祭り。ファルケンシュタイン師は多額のお布施とともに煙のように消え失せているというわけだ。
「探せ、探せ! あのぺてん師をとっつかまえろ!」
主人に怒鳴られて乗合馬車を追いかけた従者や馬丁たちが目にしたのは、パトロンと喧嘩別れしてロンドンへ帰る蓮っ葉な女優と、そののろまな従者だけ。
「なにジロジロ見てんのさ! あたいは、金のない男にゃ用はないんだよ!」
大きく胸の開いた真っ赤なドレスで着飾ったその下品な女優こそが、昨日まで神秘のお告げをもたらしていたウルリッヒ・フォン・ファルケンシュタイン師だと、誰が信じるだろう。
僕は一応、濃い茶色のカツラと眼鏡で変装していたけど、姉さんはハニーブロンドを派手に結い上げて、少し化粧をしただけだった。
ファルケンシュタイン師の信者だったご婦人方は、あんな下品な女は声を聞くのも汚らわしいと言わんばかりに顔を背け、誰ひとりとして姉さんの正体に気づかなかった。
……いつもそばにいるぼくでさえ、時々目を疑いたくなる。このひとは本当に、自分の性別を自在に変えられるんじゃないかってね。
そしてぼくたちは、トランク一杯の金貨やダイヤモンドのネックレス、ブローチなどを手に、意気揚々とイーストエンドに帰ってきたのだ。
ロンドンに入ってすぐ、宝石類はみんなバラして故買屋に売り飛ばした。
涙の形をした見事なルビーのイヤリングは、姉さんのためにとっておきたかったんだけど。
「だめに決まってんだろ。こんな目立つモンぶら下げて歩いてみろ、オレたちがこいつを騙し取ったぺてん師でございって看板出してるようなもんじゃねえか」
姉さんは自分で器用にイヤリングをばらしてしまった。
今頃、あの女王のようなルビーはそれぞれネックレスかブレスレットの一部に加工され、離ればなれになって別々の店のショウウィンドウを飾っていることだろう。残念だ。
「はい、またぼくの勝ち」
スペードのエースをテーブルの上に投げて、ぼくは言った。
「うー……っ!」
十二連敗の姉さんは、もう言葉も出てこない。
賭けたのは、今夜一晩、相手に何でも命令できる権利。
「さーて、なにをしてもらおうかなあ」
ぼくはほくそ笑みながらカードをまとめた。我ながらそうとう底意地の悪い表情になっているだろうなと思う。
悔しそうに呻り続ける姉さんは、酔いのせいもあって目元がうっすらと紅く染まり、潤んで見える。……ひどく色っぽい。
「そうだ、このあいだの紅いドレスを着て、踊りに行こうよ。コヴェントガーデンの近くに、パリ風のダンスホールができたって話だよ」
「やだよ。おまえ、そこでまたオレに男ひっかけさす気だろ」
「そんなことしないよ」
美人局も手っ取り早い小遣い稼ぎにはいいけどね。でも、今夜はぼくが姉さんを独り占めするつもりだから。
「じゃあ……」
ぼくはしばらく考え込み、それからおもむろにテーブルに肘をついて身を乗り出した。
「そのままの恰好でいいから、ヴォクソール遊園に散歩に行こう」
「今からか?」
もう真夜中を過ぎている。バカンスシーズンが終わりかけた晩夏のこの時期、外はまだそれほど寒くはないけれど、やはりこんな時間から公園に出かけるなんて、酔狂すぎる。
けれど、ぼくはにこやかに笑ってうなずいた。
それから、姉さんにだけ聞こえるよう、低い声でそっとささやく。
「その恰好のままの貴女を、抱かせて」
「おま……っ、セ、セオドア! おまえ――っ!」
姉さんは耳元まで真っ赤になって、絶句した。
「男装した姉さんを抱くのって、凄くスリリングでどきどきする。『姉さん』も『兄さん』も、どっちもいっぺんに犯してるみたいでさ」
娼婦を買うのは男の悪癖でしかないが、同性愛は法律で禁じられたれっきとした犯罪だ。その罪に問われた男が、罰として二年間もの強制労働につかされたケースもある。女性を男装させて犯すのは、さて、どんな罪に相当するだろう?
「ば、莫迦っ! こんなとこでなに言ってんだ、おまえ!」
「大丈夫。誰にも聞こえてないよ」
『王冠とアヒル』亭は今夜も大盛況だ。酔っぱらいどもが高歌放吟、やかましくて、隣にいる人間と会話するにも大声を張り上げなくてはならない。ぼくのセリフなんか、誰も聞いているもんか。
むしろそんなふうに姉さんが真っ赤になってうろたえるほうが、人目を引いてしまうんじゃない?
勝ち気で頭が良くて、どんな老獪な紳士や役人たちでさえ容易く手玉にとる姉さんが、こういうことに関してだけはひどく初心で、まるで田舎から出てきたばかりの小娘みたいだ。まったく可愛いったら、ない。
できることなら今すぐこのひとを抱きしめて、息ができなくなるまでキスしたい。
でも、あんまり無茶ばかり言って苛めると、そのあと三日くらい口もきいてくれなくなるから。
「じゃあ、家でいいよ。そのかわり、ぼくが良いというまでベッドから出ないで」
テーブルの上で、かすかにふるえる姉さんの手に自分の手をかさね、そっと握りしめる。姉さんはうつむき、何も答えず、けれど逃げようとはしなかった。
「そろそろ帰ろうか、アーノルド兄さん」
今、ぼくたちが暮らす部屋は、軍人の未亡人が経営する賄い付きの下宿屋だ。
ウエストエンド、セント・ジェームズ・パークからさほど遠くないところにあり、間取りは居間と寝室がふたつ、予備の小部屋がひとつ。
この部屋を、ぼくたちはジェントリ階級出身の兄弟というふれこみで借りている。地元領主の求めに応じて手放した土地の代金を投資に回し、生計を立てている、と家主のオルソン夫人には説明してある。
もっとも、彼女がその説明を鵜呑みにしているかどうかは疑わしい。だがほかの下宿人も、高級娼婦ばかりを顧客に持つ弁護士だの、演奏より色事のほうが得意そうなバイオリン教師だの、みんな叩けば埃の出そうな連中ばかりだ。
第一、軍人の未亡人というオルソン夫人の経歴自体、怪しいんじゃないかとぼくは思っている。
彼女が数人の下宿人を置いているこの屋敷は最新のヴィクトリアン様式、半地下の倉庫と屋根裏の使用人部屋を抜かしても、一階と二階を合わせて十部屋を越える広さだ。建材や備え付けの家具にもけっこう金がかかっている。地方に領地を持つ貴族のタウンハウスが、借金返済のために売りに出されたか、賭博のカタにまきあげられたか、といったところだろう。
たかが軍人の遺族年金で、こんなでかい屋敷が買えるものだろうか。
この屋敷を買った資金は、微々たる遺族年金なんかじゃないだろう。もっと別の、おそらくは彼女自身の美貌と才覚で稼ぎ出した金のはずだ。
だが、彼女に面と向かってそれを問い質す下宿人は、もちろんひとりもいない。
そしてオルソン夫人も、ぼくたちがきちんと部屋代を払っている限り、グレンフォード兄弟を若い投資家の紳士として扱ってくれるはずだ。
ぺてんで稼いだ金の一部は投資に回して、堅実に利益をあげてもいるから、ぼくたちはあながち嘘だけを言っているわけでもない。
「でも、今の姉さんを見たら、ミセス・オルソンは泡を吹いて卒倒するだろうな。彼女、兄さんを男だと信じきっているから」
「まさか。じゃあ、ときどきこの部屋に出入りしてる、派手なドレスの女は、ありゃ誰だよ」
「あれは、兄さんの留守を見計らってぼくが連れ込んでる、高級娼婦(コーティザン)。ぼくは兄さんよりお行儀が悪いんだ」
寝室へ行くのももどかしく、ぼくたちは居間のソファーで抱き合っていた。床にはふたり分の衣服が脱ぎ散らかされている。
紙一枚も入らないほどぴったりと体を重ね合い、互いの髪に指を絡めて溶け合うようなキスをする。
ゆたかな金髪を奔放に乱し、一糸まとわぬ姿の姉さんは、まるでカーマ・スートラに登場する淫らな女神だ。
「セディ――」
ふと、姉さんがぼくの名をつぶやく。
「その、瞳(め)……」
「ん? 目? ぼくの?」
姉さんはこくんとうなずいた。
「おまえの、その瞳(め)――大好き」
ぼくのほほに両手を添えて、姉さんはぼくのまぶたに軽くついばむようなキスをした。
「こういう時ってさ、おまえの瞳、いつもより色が濃くなって、ほとんど黒に近くなるんだ。でもそれが、好き」
ぼくの瞳は少し暗く見える緑だ。姉さんは「深い森みたいな色」と表現する。が、感情が激すると、やや毒々しいまでの明るいエメラルドグリーンに変わる。まじまじと鏡で確かめたことはないが。
この瞳の色は、どうやら顔も名前も知らない父親に似たらしい。そのため、母さんは生前ずっと、この目を直視するのをためらっていた。
けれど。
「きれいだ。おまえの瞳(め)。見てると、吸い込まれそうな気がする」
姉さんはそう言う。
ぼくに言わせれば、姉さんの金色の瞳ほど美しい眼はないのに。
「姉さん――!!」
全身を、ふるえるような戦慄が駆け抜ける。
ぼくはたまらず、姉さんを抱きしめた。
いとしい人の全身を、頭のてっぺんから爪先まで、そのはちみつ色の髪の一房一房まで、キスと愛撫で覆い尽くす。そうやって、この人のすべてにぼくのすべてを刻印してしまえたらと願う。
姉さんとこういう関係になることは、ぼくにとってはごく自然なことだった。
ぼくが初めての女は、姉さんだ。――姉さんの初めての男は、ぼくではないけれど。
あれは、ぼくたちがまだテムズ河に係留された廃船で寝起きしていたころ。
凍り付くような風が吹く冬、ぼくはひどい熱を出した。
ロンドンでは毎年のようにたちの悪い病気が流行る。チフス、赤痢、百日咳、コレラ。人口が密集するイーストエンドではなおさらだ。
衛生環境は悪く、医療環境はさらに悪い。医師も薬屋も相手にするのは裕福な人々だけであり、貧しいスラム街の住人などさっさと死ね、自分の前に顔も見せるなと言わんばかりの態度だ。
まして決まった住居もない浮浪児など、医療など受けられるはずもなかった。
高熱に浮かされ、かろうじてぜいぜいと苦しい呼吸を続けながら、ぼくもそのまま死ぬのだろうかと思っていた。
けれど姉さんは、ぼくを医者のところへ連れていった。
自分の体を代価にして、ぼくに治療を受けさせてくれたのだ。
姉さん自身と引き替えにぼくたちを自分の屋敷に泊め、ぼくの治療に当たった医者は、女王陛下の宮殿にも出入りが許され、貴顕の人々の病気や怪我を治してきた名医として知られていた。が、その実、貧民街の年端もいかない少女を金で買うような野郎だったわけだ。
栄養状態が悪かったため、ぼくはそいつの屋敷で二ヶ月ほど寝たきりになっていた。
そのあいだ、姉さんは自分がなにをされているか、けしてぼくに語ろうとはしなかった。
「おまえが謝ることなんか、なんもねえだろ、セディ。なんにも心配するな。おまえはただ、病気を治すことだけを考えていればいいんだ」
そう言ってぼくの額にキスした姉さんの唇が、かすかにふるえていた。
あの時の悔しさを、ぼくはけして忘れない。姉さんをもてあそぶ男が、そして誰よりも、姉さんを犠牲にしてのうのうと生き延びる自分自身が、許せなかった。
最初は母さん。そして、姉さん。いつもそうだ。ぼくの無力のせいで、ぼくの大切な人たちが犠牲になる。
悔しくて、歯がゆくて、自分が情けなくて、いっそこのまま死んでしまいたいと思った。
けれど、ぼくの熱が下がったと言って喜び、ぼくが食事を残さないようにとずっと付き添ってくれる姉さんを見ていると、それもできない。
強くなりたい。賢く、強く、姉さんを守れる男になりたい。
ただ、繰り返しそう願うしかなかった。
ぼくがベッドから起きあがれるようになっても、くだんの医者は姉さんを手放そうとはしなかった。よほど姉さんが気に入ったらしい。ぼくたちを遠縁の子どもといつわり、屋敷に住まわせていた。――女房も子どももいたのに。
ぼくたちがそこに居候していたのは、半年あまり。
ついに我慢できなくなった姉さんとぼくは、そいつの頭を銀の燭台でぶん殴り、屋敷から逃げ出した。もちろん、凶器に使った燭台そのほかを頂戴して。
ちなみにその医者は、そのあと何度かガゼット紙に名前が載っていたから、死にはしなかったらしい。ぼくは今でも殺してやりたいと思っているが。
姉さんがいまだにかたくなに男装を続けているのは、あの時の悲痛な記憶を心の奥底に封印してしまいたいからなのかもしれない。
そしてぼくは誓った。
もう二度と、ほかの男に姉さんをさわらせたりしない。
姉さんはぼくが守る。
このひとを、ぼくだけのものにする。
たしかに、このひとだけに貞節を守り抜いているわけじゃない。商売柄、娼婦を買うこともあるし、金持ちのご婦人のベッドに忍び込まなくてはならない時もあった。
けれど、ぼくの心を、魂を捧げるひとは、この世にただひとりだ。
姉さんが――金色の瞳をした美しいアネリーゼだけが、ぼくの永遠の恋人だ。
「姉さん、好きだ。愛してる。ぼくの……ぼくの、リゼ。大好きだよ――!」
同じ言葉を何度も何度も繰り返しながら、ぼくは一晩中姉さんを離さなかった。
アメンバー限定公開版と歩調を合わせるため、少し短くしました。切った部分は次回に載せます。
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いします♪